そして、この「傾き」が大きければ大きいほど、目覚めた後に「ひらめき」が起こりやすかったのです。(※考察は次ページを参照)
この結果から、脳が深い眠りの中で情報を整理整頓し、新たな発想を生み出すための準備をしている可能性が示唆されます。
「ひらめき」の根源は不規則な「ゆらぎ」
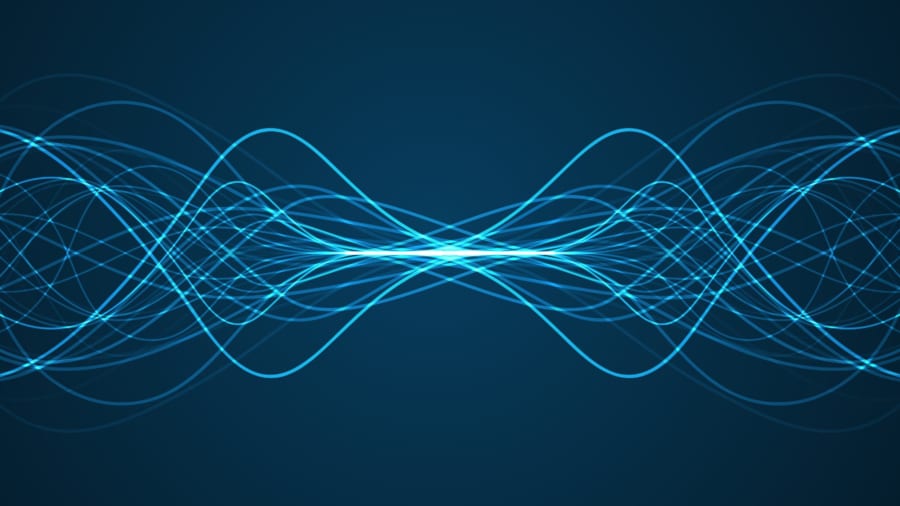
今回の研究によって、「短時間でも、少し深い睡眠(N2睡眠)に入ることが、ひらめきを引き出す鍵である」可能性が示されました。
これまで広く知られていた「ウトウトするような浅い眠りが創造的なひらめきを促す」という説に対して、全く新しい見方を提示する結果です。
なぜ今回、このように以前の研究とは異なる結果になったのでしょうか。
研究チームはその理由のひとつとして、今回使われた「問題」の性質が影響した可能性を指摘しています。
以前の研究では、浅い眠り(N1睡眠)が数学的な問題解決に有効だと報告されましたが、今回の課題は視覚的な問題でした。
つまり、問題の種類によって、必要とされる睡眠の深さや脳の働きが異なるのかもしれません。
今回の研究が明らかにしたもう一つの重要なポイントは、深い睡眠が脳の中を整理整頓している可能性です。
私たちの脳は、眠っている間に一日の情報を整理し、記憶として定着させたり不要な情報を取り除いたりしています。
特にN2睡眠のときには、脳内でシナプス(神経細胞同士のつながり)が調整され、頭の中が一旦すっきりと整理されると考えられています。
その結果、目覚めた時にはまるで「頭がリセットされたような状態」になっている可能性があります。
この状態で再び問題に取り組むことで、私たちはそれまで気づかなかった隠れた答えを見つけ出しやすくなるのかもしれません。
さらに研究者たちは、脳波に現れる「傾き」という新しい指標が、この脳内の整理の度合いを示す可能性を指摘しています。





































