アメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)で行われた研究によって、文章を書く際にAI(人工知能)に頼りすぎると、脳の活動や認知能力が育たない可能性があることが初めて科学的に示されました。
研究では、成人の参加者がAI(ChatGPT)を使ってエッセイを書く経験を重ねても、同じ時間で自力で頑張って書く練習をしてきた場合に比べて脳の活動が明らかに低く、特に創造性や批判的思考に関わる部分の活性度に差が出てしまうことが発見されました。
ただ危惧されていたように、AIの使用によって初期段階からの能力のマイナス方向への退化はみられませんでした。
当たり前のような結論に思えますが、科学的に示されたことは重要です。
研究者たちはこの現象を「認知的負債」と名付け、AIへの依存が成長への足かせになる可能性を指摘しています。
AIの普及が加速する中で、私たちはAIとの付き合い方をどのように考えていくべきなのでしょうか?
研究内容の詳細は『arXiv』にて発表されました。
目次
- 脳はAI依存で惰眠をむさぼるのか?
- AIを使うと脳の「創造力」が育たなくなる
- AI時代のサバイバル術—―脳の『筋トレ』を忘れるな
脳はAI依存で惰眠をむさぼるのか?
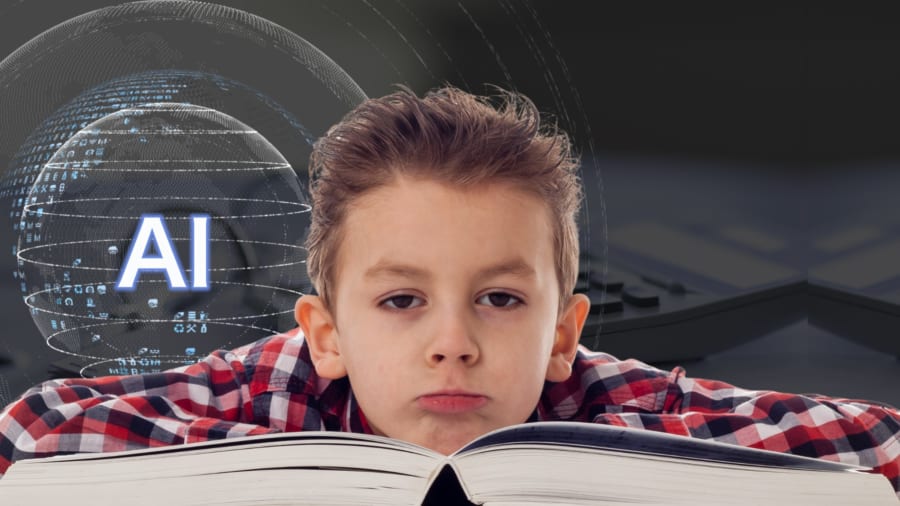
忙しい日々の中で、学校の課題や仕事のレポートを書くときに「AIが全部やってくれたらなぁ」と思ったことはありませんか?
実際、対話型AIのChatGPTなど、いわゆる生成AIの普及によって、それはもう現実になっています。
AIを使えば、複雑な文章作成もあっという間に終わりますし、ちょっとした文章の修正も簡単にできます。
この便利さから、AIは今や私たちの生活になくてはならない存在となっています。
しかし、こうした便利さの反面、少しずつ心配な声も聞かれるようになりました。
AIに頼り過ぎてしまうと、「自分の頭で考える力」や「新しいアイデアを生み出す力」が衰えてしまうのではないか、という指摘です。





































