では何が線を曲げたのか?
考えられる理由は二つに大別されます。
ひとつは電子の雲が原子核をほんとに少し押しつぶして偏極させる“核分極効果”か、それとも標準模型を越えた未知の相互作用――いわゆる『第5の力』です。
残る選択肢は、標準模型の枠内にあるもの、たとえば「二次質量シフト」と呼ばれる高次効果ですが、細かい計算をしても曲がりを全部埋めるには力不足でした。
核分極効果はこれまで精密に扱われてこなかったため不確かさが大きいものの、現時点で標準模型側から差し出せる“最後のカード”でもあります。
つまり、キングプロットのわずかな「しなり」は、見落とされてきた核の揺らぎか、まったく新しい力のささやきか、そのどちらかが本命として残ったのです。
核分極か、第5の力か
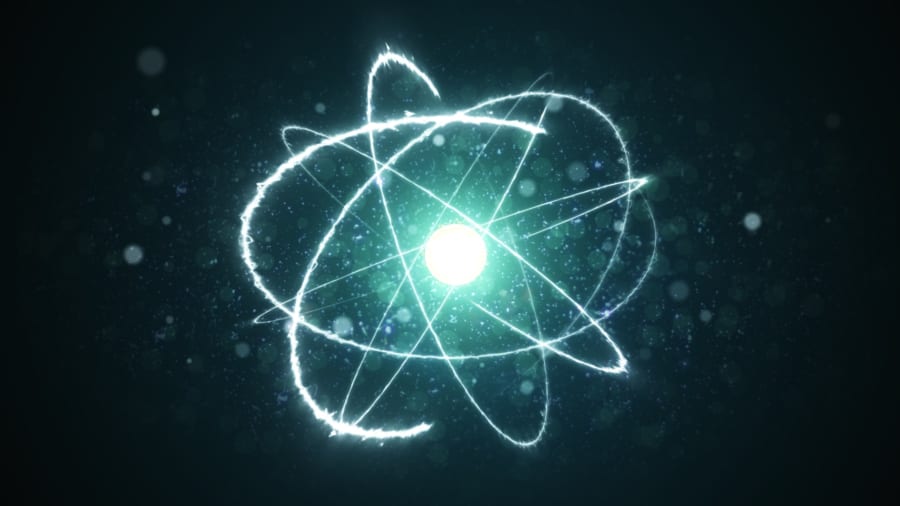
今回の研究によって発見された“まっすぐにならない線”について研究チームは、偶然ではなく物理的な原因が潜んでいると見ており、先に述べたように、2つのシナリオが想定されています。
ひとつめは、私たちがまだ知らない新しい力――電子と中性子の間でこっそり作用する“第5の力”――が関わっているという可能性です。
もしそれが正しければ、今回見つかったズレはこの未知の力の“初サイン”ということになります。
もうひとつは、従来は無視できるほど小さいと思われていた核分極効果が、実は思ったより大きく顔を出しているパターンです。
こちらが本当なら教科書を書き換える必要はありませんが、原子核の内部構造をめぐる理解が一段深まることになります。
ただし計算の不確かさが残る現段階では、核分極効果だけでズレを説明し切れるかどうかは断言できず、第5の力の芽も完全には摘み切れていません。
研究チームは「さらに高精度の測定と理論を突き詰めて、原因を絞り込む必要がある」と慎重な立場です。
仮に第5の力が本当に存在するとしても、今回の分析によりその強さや届く範囲はこれまでより厳しく絞られました。





































