東京都庁はエンジニアリングの組織
これまで行政に携わったことがなかった宮坂氏が副知事となった2019年、当初は参与として登庁したころ、都庁にはWi-Fiすら整備されておらず、オフィスは紙が積みあがっているなど昭和時代のような状況だったという。当時の写真を見せながら、都職員がより効率的に働く環境の整備や、東京都水道局アプリなどのデジタル行政サービスの提供を行ってきた。そうした中で宮坂氏が都庁各局とやり取りする中で感じたのは“東京都庁がエンジニアリングの組織”だということだ。
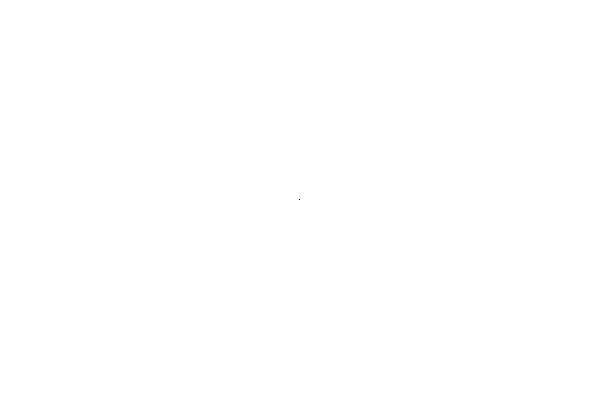
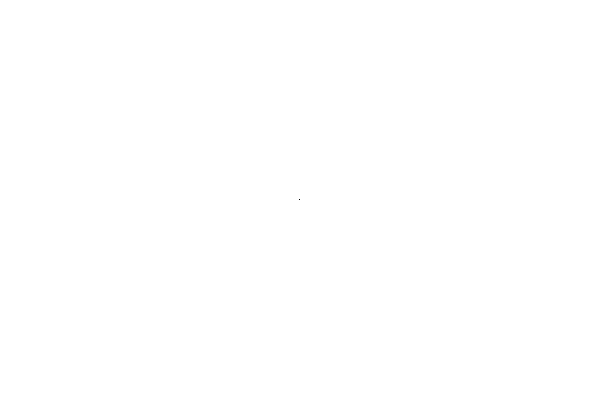
「東京都は世界に名だたるさまざまな都市と並ぶ魅力ある街だと評価されています。都市が都市として機能するために必要なインフラを構築し運用しているからです。そのためには実はエンジニアリングがとても大切なんです。水道局をはじめとする技術系の組織の職員構成は“事務職1に対して技術職2”です。世界的に魅力ある都市を形成するため、東京都はさまざまなエンジニアリング部門を内部に持ち、技術者重視の組織構造を作り上げてきたからこそ、世界一と称される優れた都市インフラがあります」(宮坂氏)
外部委託のみに依存するのではなく、組織内の技術専門家集団による持続的なサービス品質の提供を担保していることが、東京の都市機能を支えているのだ。
都本来の“強みを失っていた”IT領域
ところが「行政組織にエンジニアを抱えている強み」というノウハウは、デジタル技術導入においては十分に活用されていなかった。もちろん、ほとんどの行政のシステムにはITが導入されている。しかしそれらは長年にわたり、外部委託のみで行われていたという。
システムの予算を確保し、仕様書を提示して、応札した事業者に発注し、完成したシステムを検収して納品されたものを運用する。いわば「調達一辺倒」のアプローチは、東京都が本来持っていた本質的な強みとは真逆の構造だ。システム開発を丸投げすることで行政のIT化を自ら行うノウハウが都庁の組織には蓄積されず、入札対象のシステムごとに担当ベンダーも流動的になる。さらに検収を受けて納品が完了すると、そこで応札したベンダーの責任は果たせるため、長期的なメンテナンスやシステムの発展についてはおろそかになりがちだ。その結果として、長期的に改善していくためのスケーラビリティの確保や保守性の高さに配慮し、優れたシステムを構築するよりも、現時点の要件を過不足なく満たすシステムを納品することが優先されやすくなる。
時代に応じた柔軟なシステムの構築ができないことも大きな問題だった。GovTech東京・CTOの井原氏は「予算取り→委託→開発→納品の流れに、おおよそ3〜4年かかる状況だった」と話す。いうまでもなく現在のシステム開発においては「仮説検証の迅速な繰り返し」や「利用者の声に基づく継続的改善」は、システムの品質やエンドユーザーにとっての使いやすさを改善する上で必要不可欠な要素だ。しかし、それらを実現できない構造的問題があった。











































