昨今、カーボンニュートラルとともに耳にすることが多くなった、「カーボンクレジット」というフレーズ。現在、多くの国や企業がカーボンクレジットを通じたカーボンニュートラルに取り組む一方、「結局どういう仕組みなの?」「なぜ必要なの?」 と疑問を抱く人も多いはず。
本記事では、カーボンクレジットの基本から、制度・市場の構造、実践プレイヤーによる現場での取り組みまで徹底解説します。
そもそも、カーボンクレジットって?
カーボンクレジットとは、CO2の吸収・削減量を数値化し、排出権(クレジット)として販売・取引できる仕組みのこと。おもに企業間で行われる取引です。
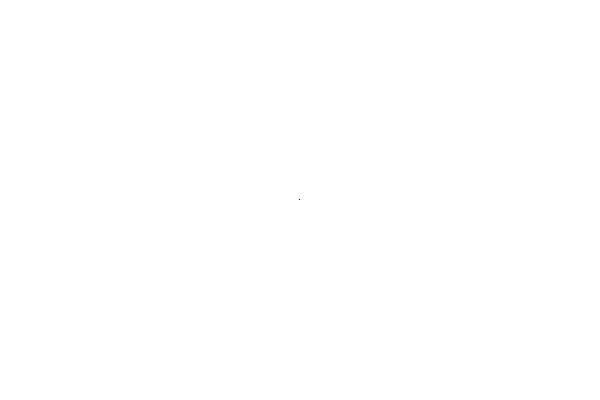
各企業、温室効果ガスに対する削減目標やカーボンニュートラルを目指しているものの、アクセンチュアの調査によると93%の企業が自社での達成は難しいというデータも出ています。目標達成に向けて、カーボンクレジットを活用し、排出量を相殺することを「カーボンオフセット」といいます。
削減目標に対応するだけでなく、消費者や投資家に対する企業やブランドイメージ向上も、企業がカーボンクレジットを購入する理由になります。
1クレジットは1t-CO2eという単位で取引されます。どの温室効果ガスであっても、CO2の値に換算されるのです。
2016年に発効されたパリ協定においても、「2050年までに温室効果ガスの実質排出量をゼロにする」という目標実現に向けて、「排出削減の成果をクレジットとして取引可能にする」という、カーボンクレジットに関する国際ルールが定められています。
京都議定書との違いって?パリ協定が“世界を本気”にさせたワケ
パリ協定にて、クレジットに関する条文が追加されたことも、カーボンクレジットに注目が集まり始めた要因の一つです。多くの人や企業がカーボンニュートラルをはじめとした環境に関わるトピックに注目するきっかけにもなっています。
しかし、パリ協定以前にあった京都議定書との違いをしっかりと理解できている人は多くありません。
パリ協定と京都議定書の違いは大きく3つあります。
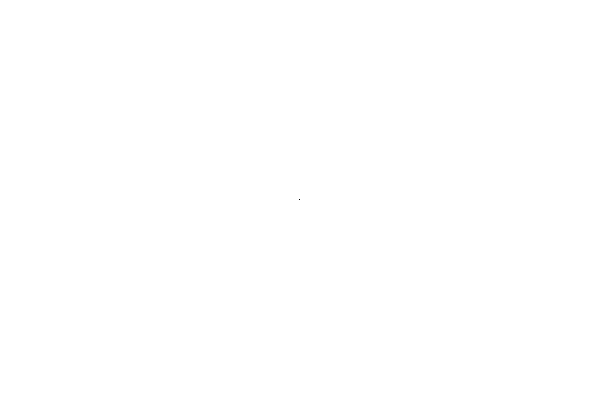
京都議定書で削減の対象ガスとされた、CO2やメタンガスなど6種類の温室効果ガスは、そのままカーボンクレジットでも対象ガスとされています。温室効果がCO2の約25倍といわれているメタンガスや、亜酸化窒素などはCO2に換算されて、クレジットが発行されます。
ゆえに、メタンガスの発生源となる稲作に関わる水田クレジット、同じくメタンガスや亜酸化窒素の発生源となる牛の飼育に関わる酪農クレジットなどが創出されているのです。







































