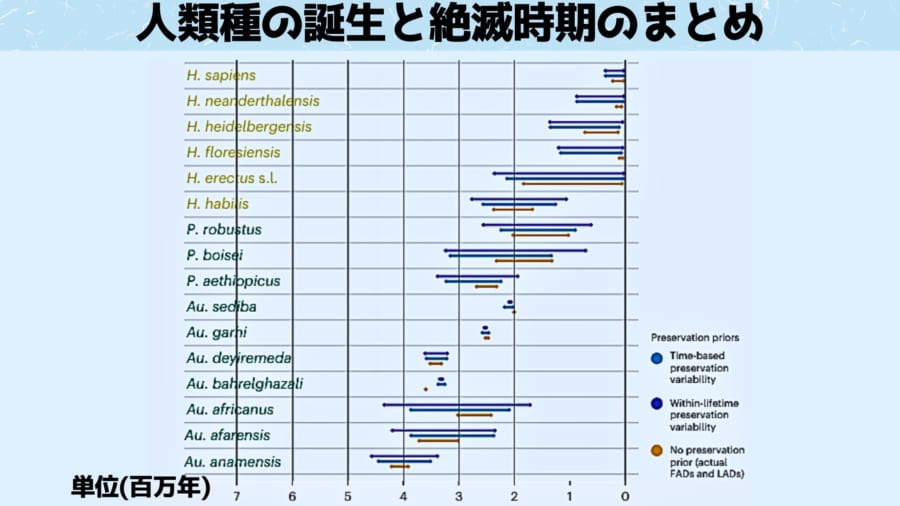この進化のパターンは、次のように進行します。「まず共通の祖先が現れ、その後、その環境に適応しながら多様化が進み、やがて進化の限界に達し、多様化が頭打ちになる」という流れです。
例えば、ダーウィンが研究したフィンチの場合、共通の祖先が島に飛来した後、ナッツを割るための大きなくちばしを持つ種や、特定の昆虫を捕食するために小さなくちばしを進化させた種が出現しました。
これらの種がそれぞれの食料源に適応すると、多様化が一段落し、新たな種が現れることが少なくなります。
環境適応が一通り完了すると、例えば大きなくちばしを持つ個体の数が種内で増加するような変化が主流となり、「新種」が出現する必要性が低くなります。
このようにして、生物多様性の限界が生じ、多様化が停止します。
そして食べられなかった木の実を食べることができるようになるなどの種内変化が起きると、それまでその食料を独占していた他の種との競争が生じます。
あるいは、食料不足により雑食だった種が新たな食料源(大きなくちばしが有利な大きな木の実など)を求めるようになることもあります。
体の変化が起きなくても、主食のシフトは起こり得ます。
最終的には、これらの変化が種間の競争を激化させ、敗れた種が絶滅に向かうことがあります。
つまり「共通先祖の出現➔多様化➔多様化の限界➔種間競争の激化➔絶滅する種の増加」となるわけです。
このような種間競争による絶滅は、環境変化によるものとは異なる性質を持っています。
研究では、この進化のパターンが特に脊椎動物に普遍的であることが示されており、逸脱は主に環境の変化によってのみ説明されます。
そこで今回、ケンブリッジ大学の研究者たちは、このパターンが人類にも当てはまるかどうかを調べて見ました。