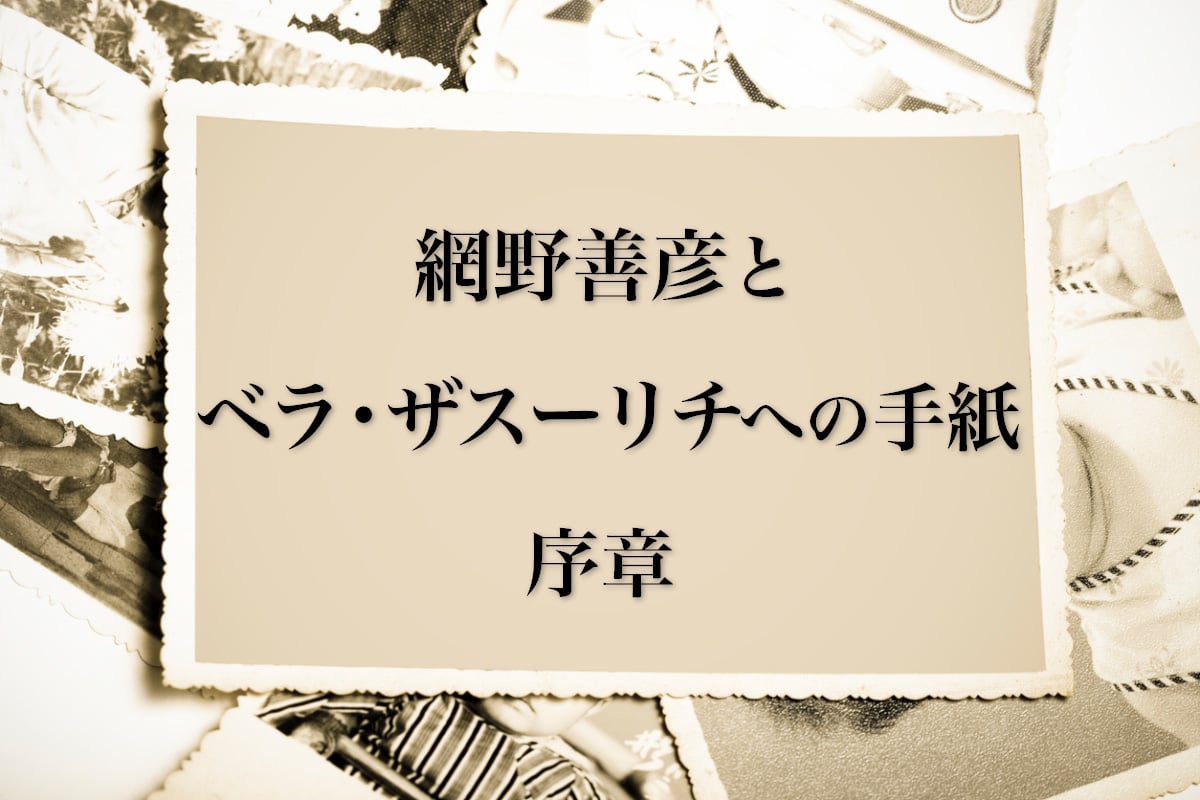
私はコロナ禍以前に「網野善彦とベラ・ザスーリチへの手紙」という論文を執筆したのだが、諸事情により論文が宙に浮いてしまい、この論文をどこかの雑誌・書籍に掲載する見込みが立たない。
今回、この場を借りて冒頭部分を公開し、掲載を検討してくれる媒体を探してみることにしたい。
1.はじめに――「老マルキスト」網野善彦
網野善彦(1928-2004)は、日本で最も著名な歴史家の一人である。網野の学問的業績は多岐にわたるが、戦後日本の歴史学界の主流であったマルクス主義歴史学を批判し、新しい歴史像を提示した歴史学者として一般には知られている。芸能民や被差別民、女性などマイノリティの歴史を独自の観点から考察したその研究スタイルは、アナール学派の「社会史」との類似性を指摘されている※1)。
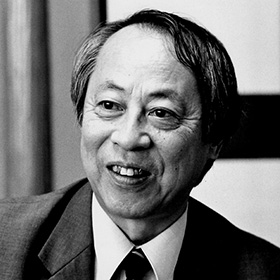
網野善彦新潮社
網野は、この世界の全ては神仏のものであり人間によって所有されるべきではないという原始的な信仰が文明社会においても生き続けたと主張した。そして、この「原始以来の無主・無所有の原思想」の日本的な表現が「無縁」であると説き、私的所有の論理である「有縁」と「無縁」の対立を軸に日本史を捉え直した。
この網野の学説は、農業生産力の拡大が経済発展の原動力であるというマルクス主義歴史学の通説と大きく異なるもので、日本の歴史学界から批判が相次いだ。
しかし網野本人にはマルクス主義を捨てたという自覚はなく、後年になっても「老マルキスト」※2)と自称し、「私はマルクス主義から完全に離脱したという意識は全然ありません」※3)と語っている。
網野が批判したのは、あくまで日本の歴史学界の教条的・硬直的なマルクス主義であった。網野はマルクス・エンゲルスの古典を旧来の解釈に囚われずに独学で読み直し、学界主流の歴史観よりも自身の歴史観の方がマルクスの真意に沿ったものであると考えた。そのような主張をする時に、網野が好んで引き合いに出したのが、マルクスが1881年にベラ・ザスーリチに宛てた書簡である。










































