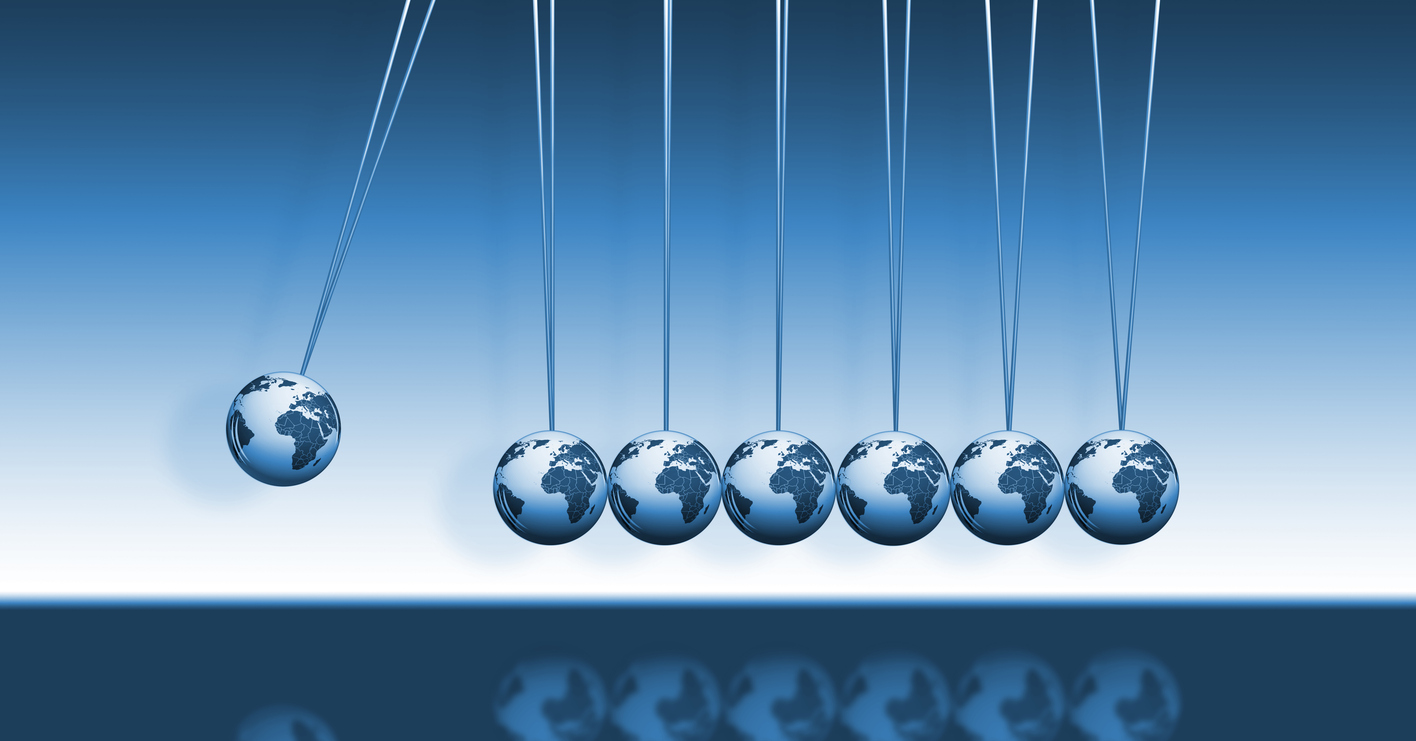
mekcar/iStock
気候変動対策を巡る議論は、IPCC報告書や各種の「気候モデル」が示す将来予測を前提として展開されている。しかし、その根拠となる気候モデルは、科学的厳密性を装いながらも、実は数々の構造的な問題点と限界を抱えている。
本稿では、気候モデルの基本構造とその問題点、さらにそれが政策や世論に与える影響について概説する。
1. 気候モデルとは何か?
気候モデルとは、地球全体の大気・海洋・陸面・氷床などのシステムをコンピュータ上で再現し、温室効果ガスの濃度変化などに応じた気温・降水・海面上昇などの将来予測を行う数理的ツールである。これらは「GCM(General Circulation Model)」と呼ばれ、現在の気候科学の中核に位置づけられている。
しかし、「モデル」は現実そのものではなく、仮定とパラメータを前提にした数値的なシミュレーションにすぎない。したがって、モデルの前提・条件・構造を理解しないまま結果だけを信じ込むことは、極めて危険である。
2. 気候モデルの構造的な問題点
(1) 初期条件の不確実性とカオス性気候は「初期値感度系」に属し、わずかな初期条件の違いが長期的に大きな差を生む。これは天気予報が数日先しか当てられないのと同様、気候モデルにおいても50年先の予測は本質的に不確実性を含んでいる。
(2) 境界条件の仮定と恣意性未来のCO₂排出量、経済成長、人口、技術進展などの「境界条件」は、SSP(共有社会経済経路)やRCP(代表的濃度経路)という仮定ベースで設定されている。RCP8.5のように、現実性が乏しい「極端シナリオ」が長年主流として使われたことは、科学的誠実性に疑問を投げかける。
(3) 太陽活動の影響を軽視多くの気候モデルは、全太陽放射照度(TSI:Total Solar Irradiance)を定数もしくは小さな周期変動としてしか扱っておらず、大規模な太陽活動の変動(例:マウンダー極小期※1)など)を十分に再現していない。





































