これは、意図的に頭をクリアにする行為であっても、脳の通常機能の大半を積極的に停止させる必要がある可能性を示唆しているのです。
こうしたさまざまな経路を結びつけ、頭が真っ白になるという共通点をもたらしているのは何なのでしょうか。
研究者たちは、その答えとして脳の覚醒レベルの揺らぎに注目しています。
覚醒度が低下しすぎ(たとえば眠気や精神的疲労など)たり、高まりすぎ(刺激や認知負荷が過剰な状態)たりすると、意識の流れを保つネットワークの微妙なバランスが崩れてしまうのです。
そうした瞬間に、記憶や注意、内なる声などの主要な認知機能が「うまく働かなくなる」可能性があり、その結果、主観的に「何も考えていない」という感覚をもたらすと考えられています。
要するに、マインド・ブランキングとは、脳の明かりが暗くなりすぎたり、逆に強すぎたりしたときに起こる現象であり、そのどちらの極端も通常の思考の流れを途切れさせてしまうのです。
“無”が語る意識:静寂もまた脳の声
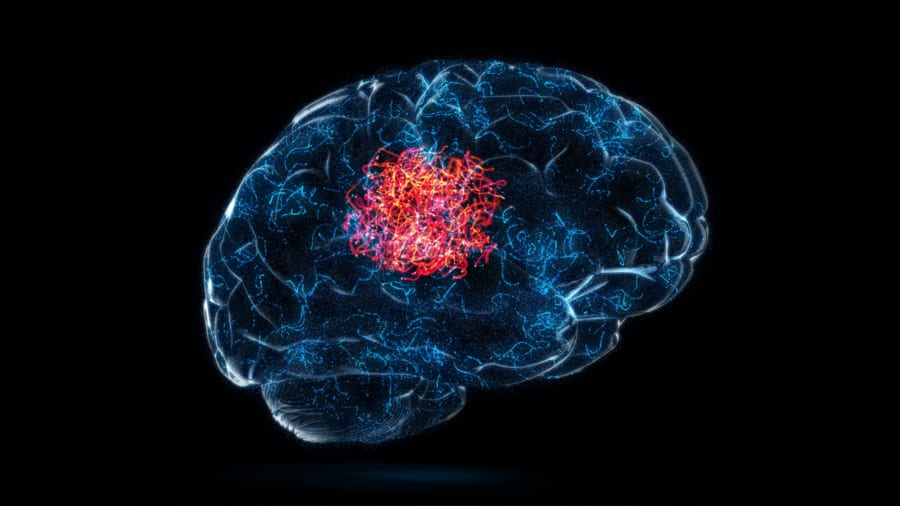
この新たな「マインド・ブランキング」を独立した精神状態と認める見方は、大きな示唆をもたらします。
まず、起きている限り何かを考えているものだという直感的な考えを覆します。
「マインド・ブランキングは、目が覚めている間は常に思考が流れているという一般的な概念に挑戦します」と、本報告の主執筆者であるトマ・アンドリオン氏は指摘しています。
実際に、私たちの覚醒時の経験には定期的に“空白の時間”が含まれるのです。
こうしたブランクの瞬間を研究することで、科学者たちは意識そのものの理解をより洗練させたいと考えています。
意識はすべてあるかないかの二択ではなく、思考の豊かさにさまざまな段階があるように見えるからです。
ときには頭の中が鮮やかな考えや感覚で満ちあふれ、ときにはぼんやりと空虚になる。





































