もともと物理学は、自然界で実際に起きる現象を説明しようとする試みから生まれました。
ガリレオ・ガリレイは、物体の落下運動を「ただ観察する」のではなく、自分で実験し、記録し、法則性を見いだしました。
ニュートンは、天体の運動が地上のリンゴの落下と同じ重力法則で説明できることを、理論と観測を結びつけて示しました。
つまり、物理学は誕生のときから、理論と現実の間に橋を架けることを使命としてきたのです。
この伝統は、何世紀にもわたって守られてきました。
どんなに美しい理論でも、現実の世界と一致しなければ「真理」とは認めない。
だからこそ、物理学はただの思考の遊びではなく、自然界の確かな理解を目指す学問になったのです。
思考の中でどんなに完璧に見える理論でも、自然界がその通りに動かなければ、意味がない。
だから物理学者は「実際に確かめる」ことを最優先します。
この価値観の違いは、数学者との比較でよく際立ちます。
数学は、論理が正しければ証明は成立します。現実世界で起きるかどうかは関係ありません。
一方、物理学は「現実に起きるか」がすべてです。
この違いが面白く表れた例が、「四色定理」の問題です。
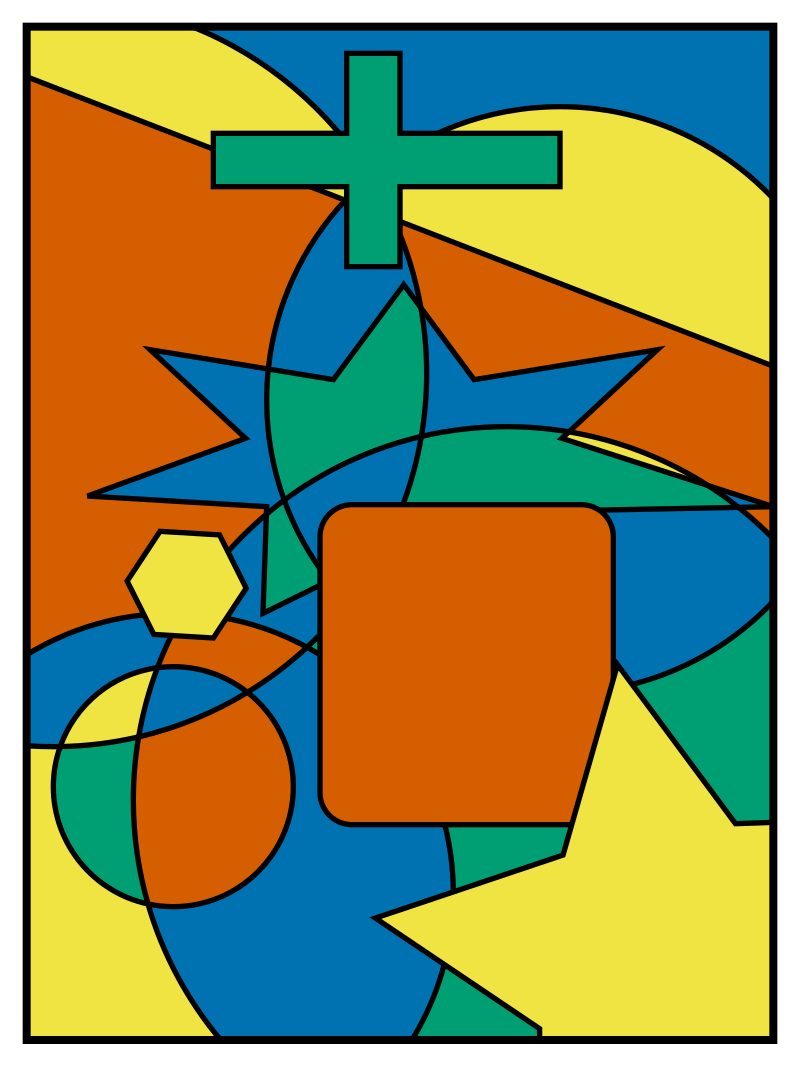
四色定理とは、「平面上ならどんな地図でも、4色あれば隣り合う領域を違う色で塗り分けることができる」という数学の定理です。
これは実は19世紀頃の地図製作者の間では経験的に知られていた事実でしたが、1852年、フランシス・ガスリーという数学者が正式に発表しました。
ただこれは予想であって、本当にあらゆるパターンで絶対に4色で塗り分け可能なのか? については長い間、誰も証明できずにいたのです。
そして1976年、ついにコンピュータを使ってあらゆる地図パターンを総当たりで検証することで、四色定理は正しいことが確認されました。





































