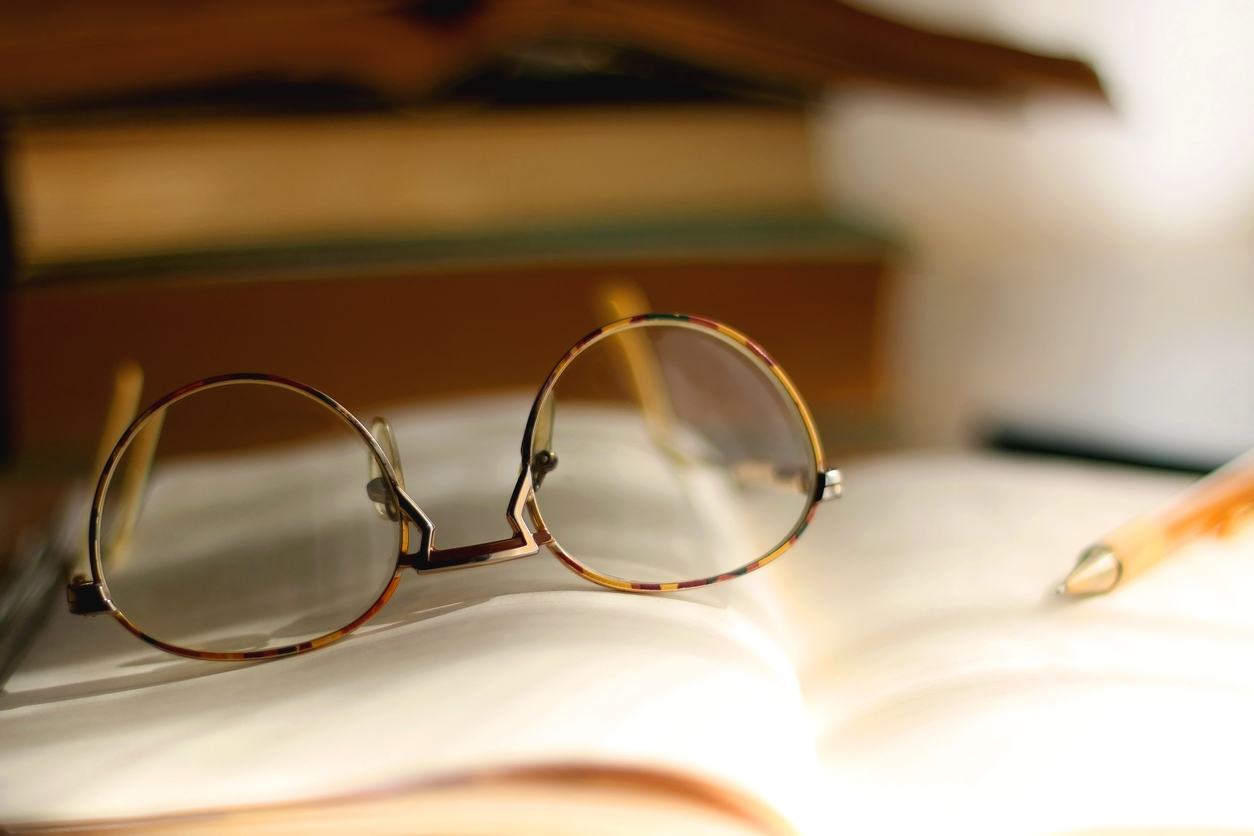
Jelena990/iStock
(前回:『高齢化の社会設計』の「縁、運、根」)
行動科学科の社会学講座
1984年10月に文学部の社会学担当として出発した際の著書は、『コミュニティの社会理論』と『高齢化の社会設計』の2冊であった。
ただ九大文学研究科の社会学専攻とは異なり、北大文学研究科では行動科学科のなかでの社会学専攻として、心理学、社会心理学、人類学、地理学などと共存するシステムになっていた。そのため、教授も助教授も含めて行動科学所属のスタッフ全員が、何らかの方法によるデータ処理の技術と統計学的基礎を踏まえた業績を出されているように感じられ、この2冊のデータ処理レベルでは不十分なのではないかと自問自答する数日が続いた。
データ処理技術が未熟
実際のところ、私の大学院時代も久留米大学でもコンピューターがなく、それまでに統計学の授業も受けたことがなかった。そのため調査データはIBMカードに穴をあけて、それを最新のカードセレクターで分類する作業をいくどか経験したに過ぎなかった。
それで、北大赴任後の心配事の筆頭は、行動科学に所属する社会学専攻で果たして実証研究者としてやっていけるだろうかという点にあった。かりに学説や理論への関心が強ければ、それなりに北大でも生きていけるだろう。しかし都市社会学を専攻して、都市の諸現象を科学的に解明するという専門家を指向していたのだから、どうしてもデータ処理の技術とそれを支える統計学の基礎だけは身につけたいと思うようになった。
コンピューター操作の個人授業
幸いに北大では大型コンピューターセンターに出かければ、そこでの端末装置を使い、データ処理の練習ができることを知り、授業の合間に15分歩いてそこに出かけて、端末装置の動かし方から使い方を学び始めた。
しかし、どうしても独学では無理な技術があり、その習得には社会学講座の二人の助手に個人授業をお願いした。数理社会学の盛山助教授(現・東大名誉教授)の教え子たちであり、諸事情を考慮して勤務時間外の夕方5時過ぎからや土曜日の午後などに、1回1時間で半年間に10回くらい教えてもらった。もちろん時間外の個人授業なので、薄謝だが毎回お礼をした。




































