そういう意味では、この解釈は間違ってはいません。
しかしこの宇宙には基本的に「外部からの力を全く受けることがない物体」は存在しません。
このことはニュートン自身が発見した万有引力からも示されています。どんな物体も何かに引かれており、そして自分自身も何かを引き付ける力を発しているのです。
リンゴが木から落ちたのは、誰も触っていないリンゴという物体にも、引力という見えない力が働いている、それがニュートンの考え方でした。
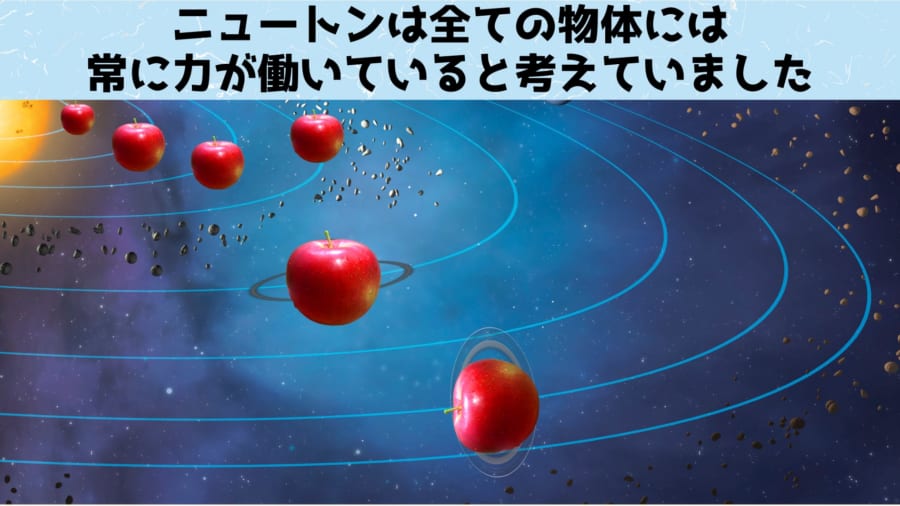
そうなると奇妙なことが起こります。
どんなものにも力が働いていると考えていたニュートンが、なぜ運動法則の第一の対称として「力が働いていない(架空のありえない)物体」と読めてしまう危険な表現を行ったのでしょうか?
他にも疑問点はあります。
古くから、既存の解釈による第一法則は、循環論法に陥ると指摘されていました。
Q:力が働いていない物体は静止するか直線的に動くと言っていますが、力がかかっていないことはどうやったら解るか?
A:答えは「静止しているか直線的に移動しているか」です。
ここでも「力が働いていない物体」という表現が議論をおかしくしています。
法則を表現する言葉は法律用語のような「厳密さ」が求められることを、ニュートンが知らないわけがありません。
答えを得るためバージニア工科大学の研究者たちは、ラテン語の原典を改めて精査しました。
するとオリジナルのラテン語においてニュートンは「運動は外力によって強制される限りにおいてのみ変化する」言い換えれば「あらゆる物体の運動は外部から働く力で変化する」と記していたことが判明します。
つまり既存の解釈は「力が働いていない物体」と読めてしまうのに対し、実際の第一法則は「外部からの力が働いている物体」について述べていたのです。





































