イスラエルのテルハイ大学(Tel-Hai College)で行われた研究によって、ADHD(注意欠如・多動症)を抱える成人がピアノやギターなどの楽器を練習すると、薬物療法や脳トレに代わる“脳のジム”として働き、認知テストの成績を総じて向上させる可能性があることが明らかになりました。
集中力や計画力を伸ばす新たな手段として音楽を活用できるとしたら、その仕組みはいったいどのように脳を変えるのでしょうか?
研究内容の詳細は『Psychological Research』にて発表されました。
目次
- 音楽×ADHDが着目されている理由
- ADHD治療に足りなかったのは“リズム”
- リズムが脳回路を鍛える仕組み
音楽×ADHDが着目されている理由
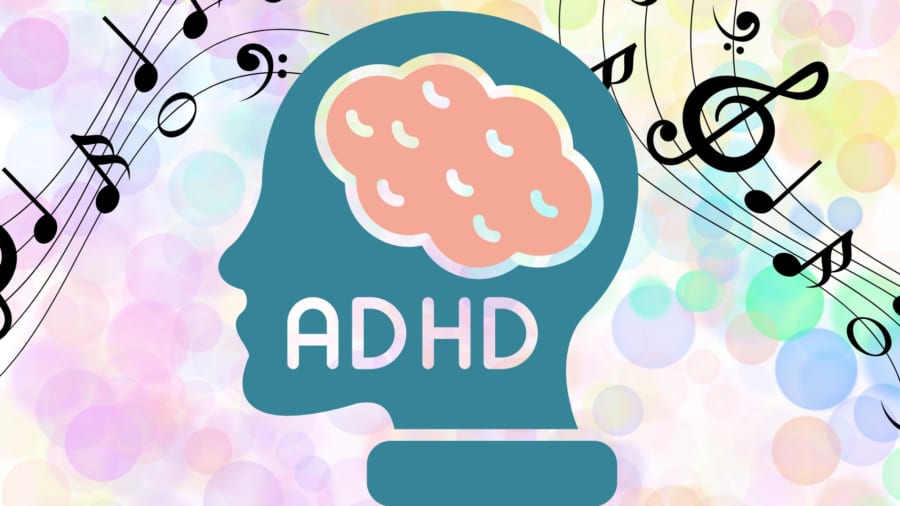
ADHDは注意力の維持や衝動のコントロールが難しい発達障害で、子どもだけでなく大人にも見られます。
大人のADHD当事者は、学業や仕事、人間関係など様々な場面で集中力の低下や不注意による困難を抱えがちです。
その治療には主に薬物療法(例えば神経刺激薬の投与)や行動療法(認知行動療法など)が用いられてきましたが、それだけでは十分でない場合も多く、脳の認知機能そのものを鍛える新たなアプローチに注目が集まっています。
一方、音楽が脳に与える良い影響については以前から知られています。
楽器演奏や音楽訓練は脳の可塑性を高め、記憶力を伸ばし、情動を安定させる効果が報告されています。
例えば子ども時代に楽器を習うと、空間認知や言語、数学の能力が長期的に向上するとの研究もあります。
またADHDでは集中力を維持しにくいとされますが、音楽を聴いたりリズムをとったりしているとき、脳の覚醒度がちょうどよいレベルに保たれやすいという説があります。
音楽を活用することで脳内報酬系を刺激し、注意や集中を助ける効果が期待できるのです。





































