お米の値上がりが家計を直撃している。しかし、先日、財務省が政府に、「お米の値段が上がったなら、日本人は安い輸入米をもっと食べればいい」というような提言をしたとか。ただでさえ日本の食料自給率は38%と低いのに、これ以上、下げるような事をして良いはずがない。そこで、コメ問題についておさらいしてみた。
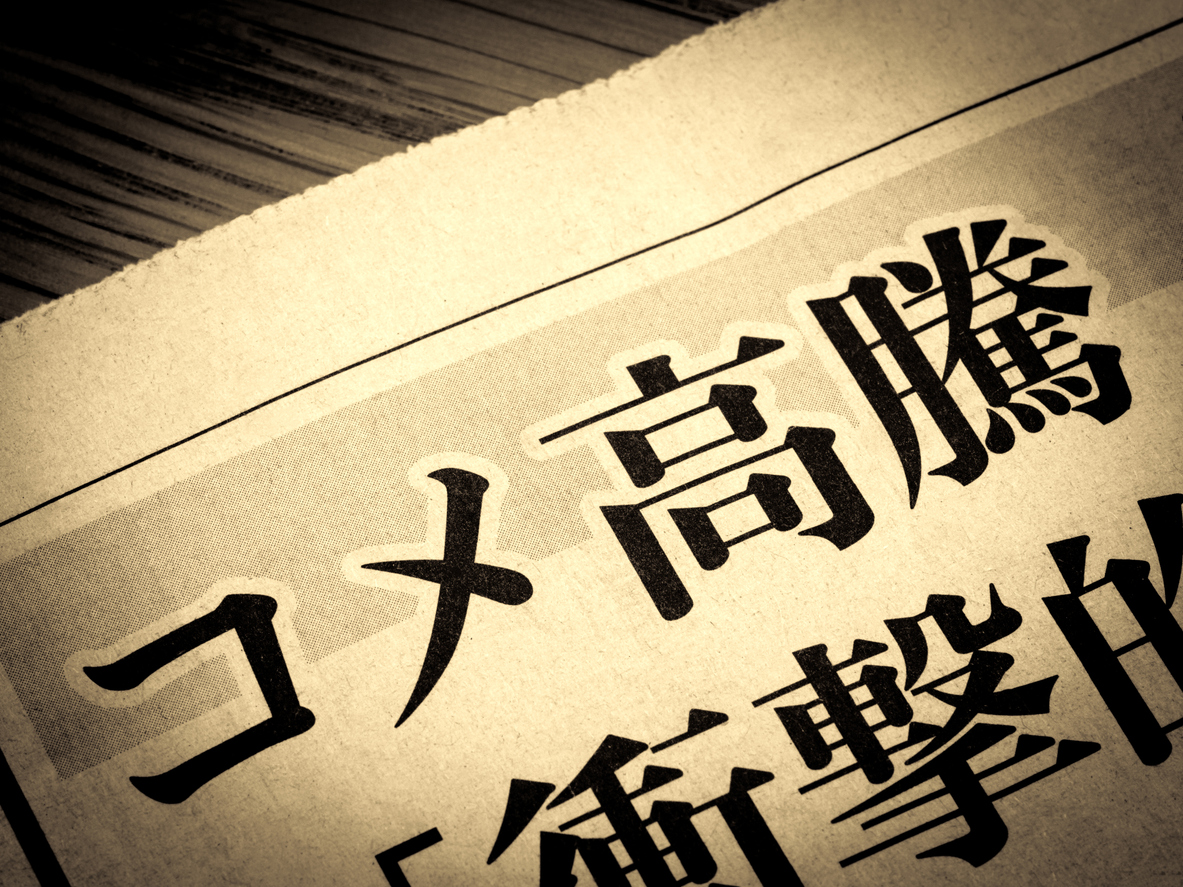
y-studio/iStock
1. コメが高いのは、なぜ?
最近、「お米の値段が上がっている」「スーパーでコメが少ない」という声を耳にする。
いま日本では、“コメ不足”が静かに起きている。でも、“米どころ”日本で、なぜコメが足りなくなるのだろうか?
ニュースでは「猛暑の影響」や「インバウンド需要」などの言葉が並ぶが、実はこの問題、もっと深い歴史的な背景があるようだ。
お米の問題は、単なる天候や景気の話ではなく、私たちの暮らし方や国の政策、そして戦後日本の歩みに深く関わっている。
2. お米の国・日本が「米余り」から「コメ不足」に至るまで
日本は古来よりお米を主食としてきた国だ。祭りや行事、日常の食卓に至るまで、米は文化と密接に結びついていた。ところが戦後、日本の農政は大きく変質した。その背後にあったのが、「アメリカの影響」である。
MSA法とアメリカからの“食料援助”1954年、日本はアメリカとMSA協定(Mutual Security Agreement:相互安全保障協定)を結んだ。 この協定に基づいて、アメリカから小麦・トウモロコシ・大豆・綿花など、いわゆる「食料援助」と称して余剰農産物の提供が始まった。
しかし、これは単なる無償の援助ではなく、実質的にはアメリカが自国の余剰作物を日本に“買わせ”、外貨を稼ぐための経済戦略だった。 「援助」という表現は形式的なもので、アメリカにとっては農業生産の過剰問題を解消し、かつ同盟国を経済的に従属させる巧妙な仕組みでもあったようだ。
これらの農産物は、当時の日本人の食生活にはなじみの薄いものだったが、学校給食や都市部の食卓を通じて急速に浸透していった。 やがて日本人の食生活そのものが「パン・肉・油」を中心とするアメリカ型に変わっていった。
































