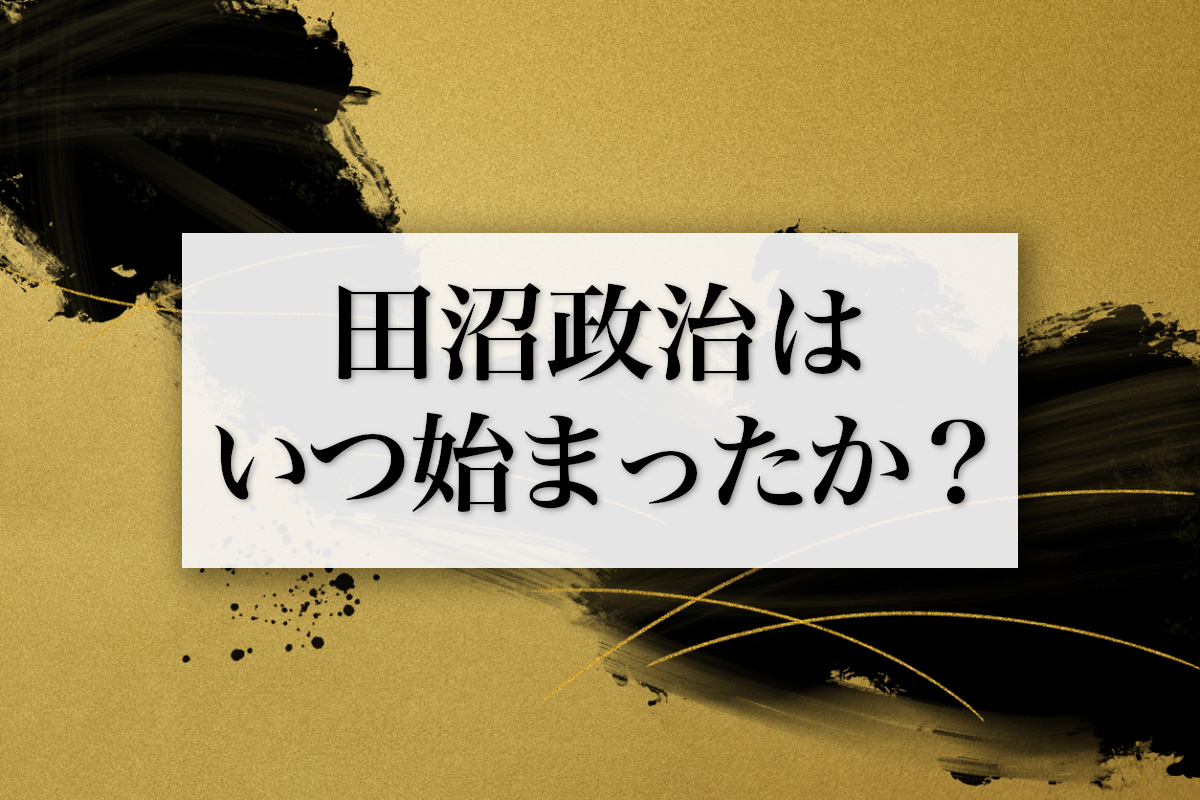
田沼意次(1719~88年)が江戸幕府を牛耳っていた時代・政治は俗に「田沼時代」「田沼政治」と言われる。しかし「田沼政治」がいつ始まったかという点については諸説あり、必ずしも明確ではない。今回はこの問題を論じてみたい。
1. 田沼意次の異例の昇進
田沼意次の父は、紀州藩の足軽であった田沼意行である。意行は紀州藩主徳川吉宗が享保元年(1716)に将軍職を継ぐ際(8代将軍)、紀州から随従して幕臣となり、小姓から主殿頭に昇進し、晩年には600石の知行を与えられて小納戸頭取となった。享保19年(1734)12月に没した。
意次は父の縁故により、享保19年3月13日、16歳で吉宗の嫡子家重付きの西城小姓に取り立てられた。翌享保20年(1735)3月4日、父の遺領600石を継ぎ、元文2年(1737)12月16日に従五位下に叙され、主殿頭に改称した。
家重が将軍に就任した延享2年(1745年)9月1日、意次は27歳で本丸勤仕となり、ここから目覚ましい昇進が始まる。延享4年(1747)9月15日、小姓組番頭格に昇格し、諸事執啓見習(御用取次見習)を務めた。寛延元年(1748年)10月1日、小姓組番頭となり、実禄2,000石に加増され、将軍の側近くに控える地位を得た。以後、前後10回の加増を受け、9代将軍家重時代に3回、10代将軍家治時代に7回の昇進を果たした。
宝暦元年(1751)7月18日、側衆側用申次(御用取次)に進み、宝暦8年(1758)9月3日、美濃郡上一揆の裁定に関わるため1万石の大名に列し、以後、幕府評定所に出席して訴訟を審理する権限を与えられた。意次は将軍の日常的な執務を支える「奥」の人間でありながら、幕府の公式の政治空間である「表」にも関わるようになったのである。同年10月28日、意次は美濃郡上一揆に関連して改易された本多忠央の旧領・遠江相良に領地を移された。
意次の昇進は家治時代に特に顕著で、前後7回の加増は綱吉時代の大老格柳沢吉保(元禄元年から宝永元年までに7回加封、15万1,000石)に匹敵する。また、家重の側用人だった大岡忠光も宝暦元年(1751)に1万石に列したが、3回の加封で2万石止まりであり、最終的に57000石に達した意次の異例の昇進が際立つ。










































