私たちは地球儀を見るとき、まず目が向くのは大陸です。
アジア、アメリカ、アフリカ、オーストラリア。さまざまな陸地が散らばる現代の地球は見慣れた姿です。
しかし、かつての地球にはこれらの大陸がすべて一カ所に集まった超大陸という時代がありました。
そのとき地球の裏半分はすべて海という、信じがたい光景が広がっていたのです。
そこまで巨大な海というものは、現代の私たちには想像ができません。空と見分けがつかないほど青く、どこまでも続く、何もない水の世界。
そこはどんな世界だったのでしょうか? そんな場所を航海したらどんな感じになるのでしょうか?
超大陸の時代というと、陸地に注目が集まりがちですが、「その裏にあった空白の海」はあまり知られていません。
現代の外洋との比較から、パンゲア時代に存在した巨大なパンサラッサ海がどんな海だったかを考察してみましょう。
目次
- 超大陸パンゲアの裏側に広がる巨大なパンサラッサ海
- 生物のいない「海の砂漠」だったパンサラッサ海
超大陸パンゲアの裏側に広がる巨大なパンサラッサ海
地球の大陸は、プレートに乗って絶えず移動しているというのは有名な話ですが、プレートを動かすマントルの上昇位置は時代によって変わってきます。
そのため地球上の大陸は数億年の周期で集合と分裂を繰り返しています。この「超大陸サイクル」と呼ばれる現象では、大陸は一度集まり、再びバラバラになることを繰り返します。
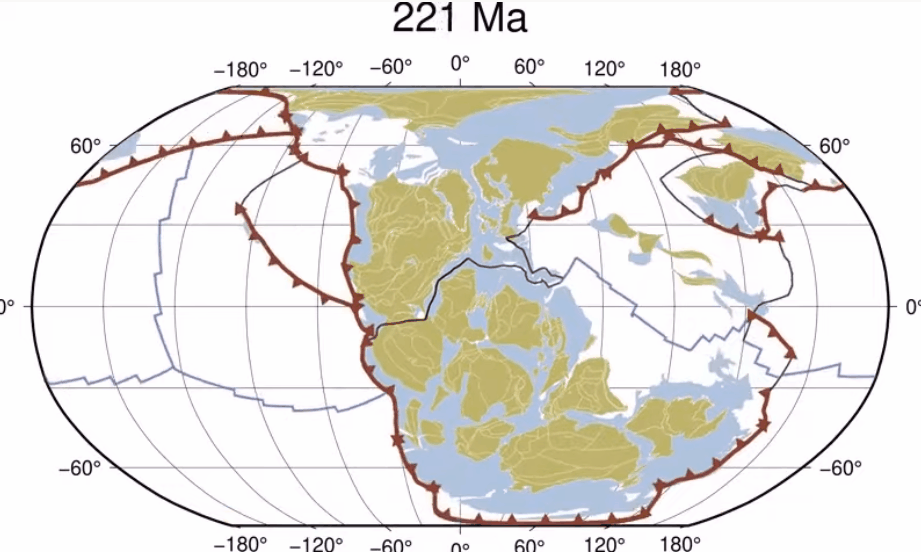
私たちが暮らす現代は、大陸が分かれていく「離散期」にあたります。
そして約3億年前、恐竜たちの時代はすべての大陸が合体して「パンゲア」という超大陸が形成されていました。
しかし、こうした時代については、陸地ばかりに注目が集まり、その裏側に広がっていたとんでもなく広大な海がどんなものだったのかという話はあまり聞く機会がありません。















































