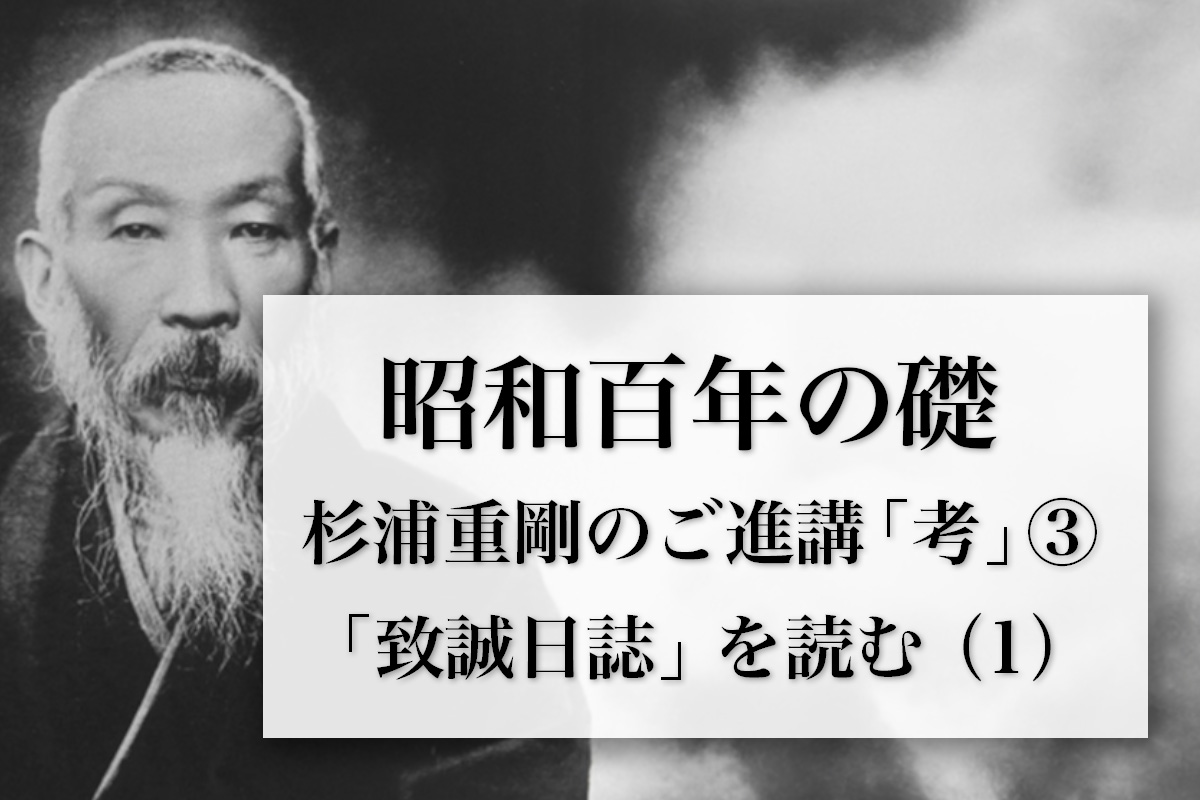
(前回:昭和百年の礎:杉浦重剛のご進講「考」② ご進講の題目と内容)
「致誠日誌」は杉浦重剛が東宮御学問所御用掛を拝命した1914年5月15日から日々欠かさず記した「日誌」である。
皇太子への進講は21年2月に終了するが、18年4月の婚約と同時に初等科を退学した良子女王への進講がなお約3年間続いたため、「日誌」は22年6月20日まで記された。それは皇太子と女王への足掛け9年間に亘る進講準備の記録である。
このうち14年5月から12月までと15年1月から3月までの約1年分の「日誌」が、「昭和天皇の学ばれた『倫理』御進講草案抄」に掲載されているので、杉浦が如何に進講準備に粉骨砕身注力し、工夫に腐心したかを知るべく、その全部を出来るだけ原文通りに掲げてみる。
※()は解説した所功氏の補足、【】は筆者のコメント、太字は筆者)。
大正三年甲寅(1914年)
5月15日 浜尾男爵より午前九時、東宮御学問所倫理科担当の件に付き、所談あり。事、突然に出づるを以て、一両日の猶予を請ひ、(日本中学校に)出校の上、千頭(清臣)氏、猪狩(又蔵)氏に内話し、更に国学院大學に於いて、山田・石川両氏に内話し、何れも賛成を表せらる。
【千頭清臣(1856年生)は東大文学部卒後に東大予備門で教え、1886年英国留学。帰国後一高教諭や二高教授などを歴任した後、内務書記官、栃木・宮城・新潟・鹿児島各県知事を務めた】
18日 午前、猪狩氏に履歴書の謄写を托し、これを浜尾氏に致す。
23日 午前、国学院大学に於て、今井氏と出会し、同紙と共に宮内省に出頭し、波多野宮内大臣より辞令拝受。御礼の後、高輪御殿に到り、学問所諸氏に面会し、且内部を参観し、午後一時、(皇太子殿下の)拝謁仰せつかる。
6月8日 出校。猪狩氏、深井寅蔵氏、井上雅二氏、青戸氏に参考資料を相談す。
【猪狩氏(1873年生)は本稿(その2)で述べた猪狩史山のこと。青戸氏は芝大神宮社司、国学院大学教授を務めた国学者の青戸波江(1857年生)で、称好塾に籍を置いた。深井寅蔵も称好塾に籍を置いた日本中学校教員】












































