後期高齢者だと全身麻酔を避けるため手術ができず、痛み止めを使いながら骨がくっつくのを待ち、そのまま車椅子生活、寝たきりになってしまうこともあるため、軽視できないのが大腿骨骨折。
大腿骨骨折は本人にとっても家族にとっても大きな負担になるので、骨折はなるべく防ぎたいもの。そのため、股関節を柔軟に保ったり、筋肉を鍛えたりしておくというのもひとつの方法です。
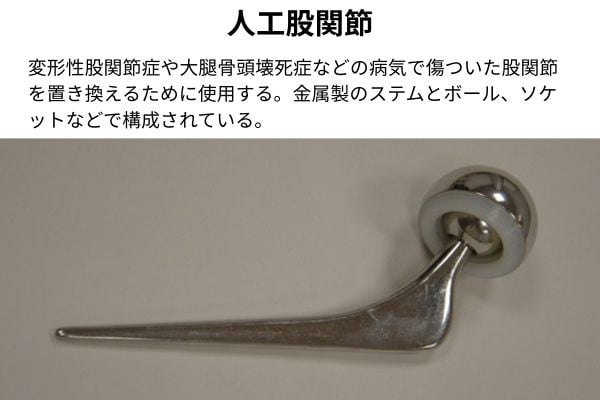
おしりの話に戻りますが、このおしりと股関節を一番鍛えているのは誰だかわかるでしょうか。
それはズバリ、お相撲さんです。
お相撲さんの体が柔らかいのを見て驚いたことのある人も多いのではないかと思いますが、お相撲さんは「股割り」といって股関節を柔らかくし、左右に大きく開脚する練習をしています。
筋肉に柔軟性を持たせて股関節の可動域を広げるための準備運動ですが、同時に、押されて俵ぎりぎりになっても脚をふんばり押し返したり、逆に相手を投げたりするための筋力を鍛えること、さらには怪我をしにくくするという理由もあります。

元大相撲力士の小錦八十吉さんは、現役時代に一番重かった時の体重が285kgあったそうです。歩くだけで股関節に855kgの重さがかかっていたことになります。これは小型の競走馬2頭分ぐらいの重さです。
転べばオスのアフリカゾウ以上の重さが股関節にかかることになります。例え一瞬でもアフリカゾウの重さが体にかかれば普通はまともではいられないでしょう。
相撲はよく転ぶスポーツです。重い体で転ぶため、筋肉やじん帯、骨の損傷を防ぐために筋肉を鍛え、柔軟性を保っておくことが非常に大切だといえるでしょう。













































