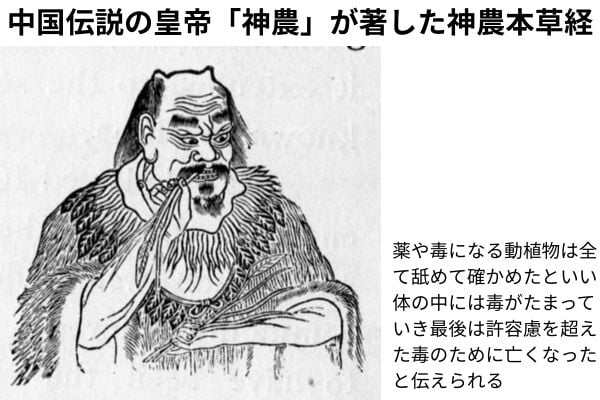この時、「これって鴆では」とピンときた人々がいたことも事実です。しかしまだSNSがなかったこととマニアックな内容だったことで人々の話題には上らず、大ニュースとはならないまま終わりました。
鴆毒は中国伝説の猛毒で、毒殺に用いられたものとして知られます。
そして伝説となった時代でもレアな毒で、実際に知る人が当時から少ないものでした。毒殺とはイコール暗殺のこと。「毒を飲んで死ぬことを命ずる」というような、裁判による公然とした刑罰では使われませんでした。

そのため鴆毒には恐ろしい、陰惨なイメージがつきまとうこととなったのです。
「鴆毒は鴆という鳥の羽を1枚、酒に浸したもの」で、羽を浸した酒は無味無臭の毒が溶け出し「猛毒となる」ということ以外の情報がほとんどありませんでした。
また、明らかに入手しにくそうな毒でもありました。鴆という鳥の存在もよくわかっていないうえ、鴆や鴆毒を揚子江の北側地域に持ちこんではならないという法律があったからです。
鴆は中国の南方、現代だとベトナムや広東、広西チワン族自治区あたりに棲息していた鳥だったようです。あまりに危険過ぎるため、鴆毒は帝の毒物倉庫で厳重に管理されているだけのようでした。
宗の帝も鴆の駆除には熱心だったようで、当時、毒殺がどれほど恐れられたかを伺い知ることができます。駆除の結果、鴆はいなくなったようで、鴆毒も使われなくなったことにより、文献にも登場しなくなりました。
「だったようだ」が多すぎたんですね。情報はほぼ伝聞でした。
もうひとつ、中国では毒も薬になるものは『神農本草経』に掲載され、その後も改定で見直されていました。