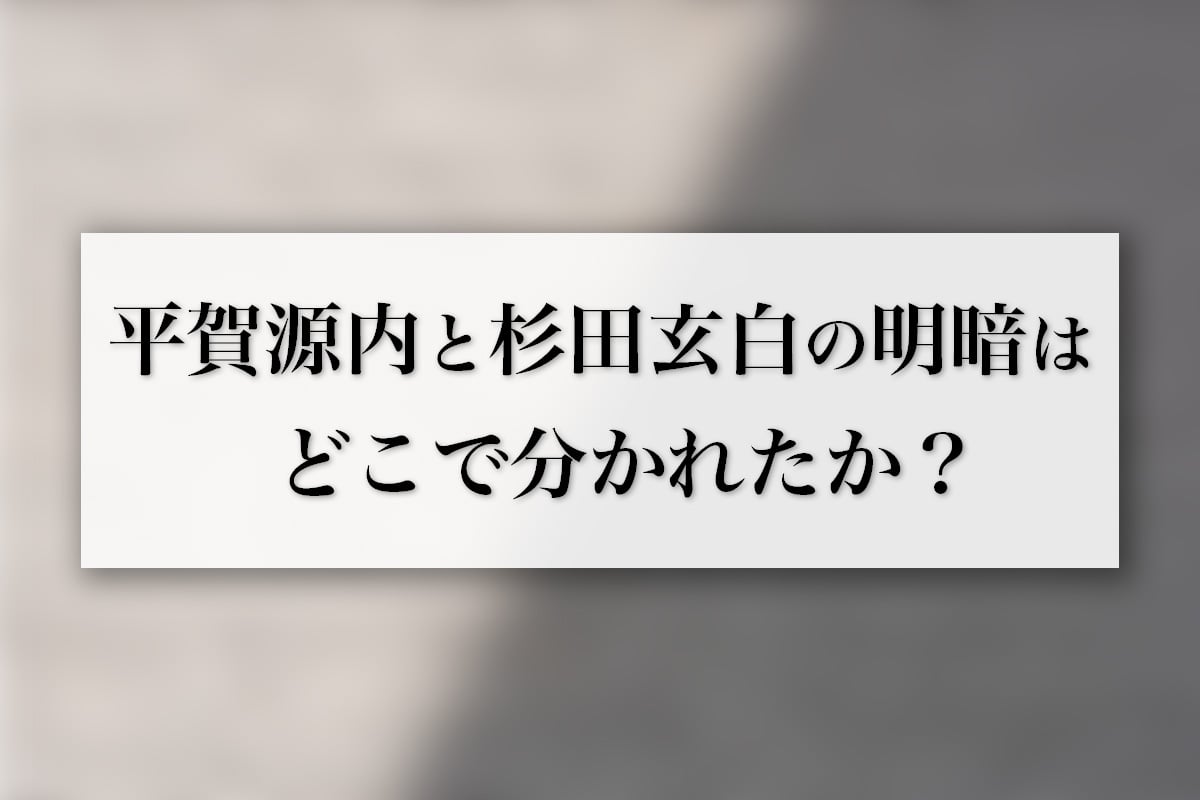
現在(2025年)放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう」で言及があったように、平賀源内と杉田玄白は親友だった。源内が亡くなった時、玄白は私財を投じて墓碑を建てたほどである。
二人の交流の始まりは明確でないが、源内主催の物産会(全国各地の薬種や産物を展示し交換する博覧会)あたりで知り合ったものと見られる。
二人の関係は、当初、才気煥発な源内の方が主導権を握っていたようである。明和2年(1765)の春、源内や玄白らは、オランダ商館長の江戸参府に随行して来たオランダ語通訳の吉雄幸左衛門を旅宿長崎屋に訪ねた。吉雄幸左衛門はオランダ製タルモメートル(温度計)を自慢げに披露したが、源内は笑いながらその製法を即座に説明して、同行の玄白ら一座を驚かせた。源内は明和5年には、所蔵の蘭書(オランダ語書籍)を参照して、実際に温度計を造っている。

平賀源内Wikipediaより
もっとも源内はオランダ語を読解する能力はほとんどなかったらしく、彼が買い集めた蘭書は基本的に図譜(図鑑)または挿絵入りの本である。オランダ語が読めなくても、図だけである程度内容の見当はついたのだろう。分からないところは通訳に尋ねれば事足りると思っていたようである。
両者の関係が逆転したのは、言うまでもなく、安永3年(1774)の玄白らによる『解体新書』の刊行である。『解体新書』は、ドイツ人医師・ヨハン・アダム・クルムスによる解剖学書のオランダ語訳書『ターヘル・アナトミア』を日本語に翻訳したものである。彼らの共同翻訳の様子は、玄白の回顧録『蘭学事始』に詳しい。
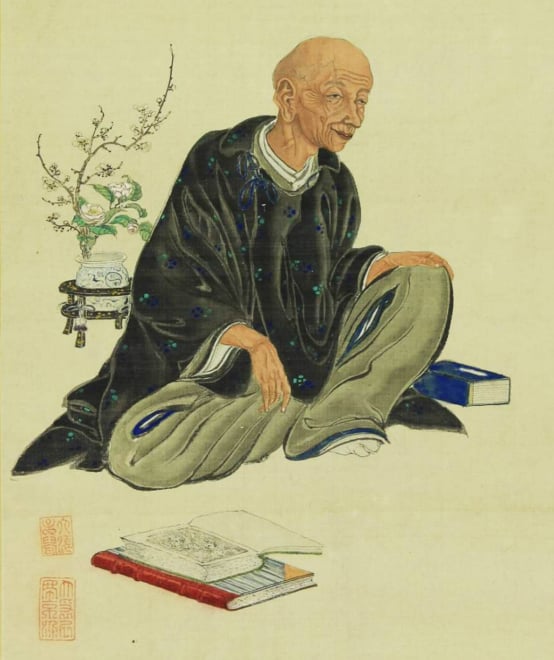
杉田玄白Wikipediaより
小浜藩医だった杉田玄白は、同僚の中川淳庵がオランダ人から借りてきた『ターヘル・アナトミア』を、江戸の小浜藩邸で見て驚いた。文字は一字も読めなかったが、そこに掲載されている精緻な解剖図に目を見張ったのである。その洋書はとても高価で玄白には手が出ないものだったが、玄白は藩に事情を話し、藩の予算で購入してもらった。








































