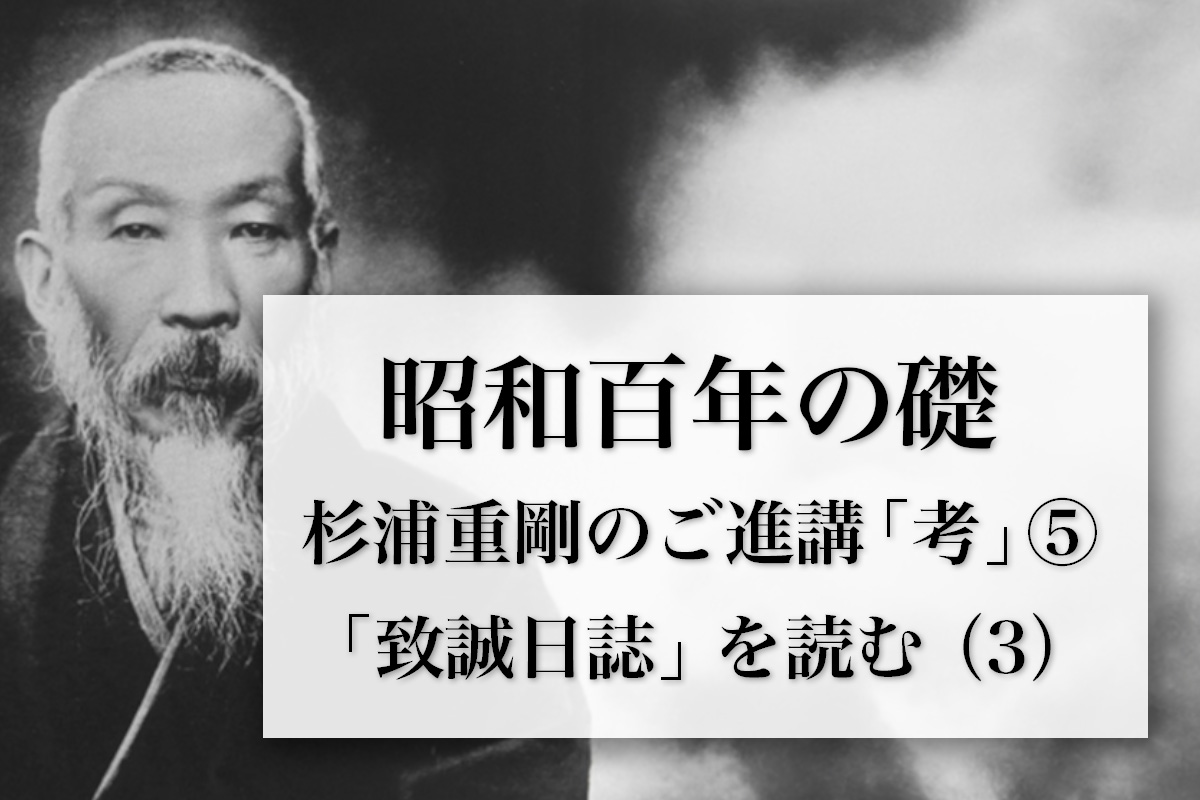
「致誠日誌」は杉浦重剛が東宮御学問所御用掛を拝命した1914年5月15日から日々欠かさず記した「日誌」である。
皇太子への進講は21年2月に終了するが、18年4月の婚約と同時に初等科を退学した良子女王への進講がなお約3年間続いたため、「日誌」は22年6月20日まで記された。それは皇太子と女王への足掛け9年間に亘る進講準備の記録である。
このうち14年5月から12月までと15年1月から3月までの約1年分の「日誌」が、「昭和天皇の学ばれた『倫理』御進講草案抄」に掲載されているので、杉浦が如何に進講準備に粉骨砕身注力し、工夫に腐心したかを知るべく、その全部を出来るだけ原文通りに掲げてみる。
※()は解説した所功氏の補足、【】は筆者のコメント、太字は筆者)。
(前回:昭和百年の礎:杉浦重剛のご進講「考」④:「致誠日誌」を読む(2))
大正四年乙卯(1915年)
1月2日 夜、山田新一郎氏著の『神社祭祀の意義』なる論文を熟読す。
【山田新一郎(1864年生)は日本の神職、教育者、内務官僚で、鳥取県知事も務めた。称好塾に籍を置いた】
7日 前日、本年御進講の準備に着手。猪狩・山田両氏に談ず。有賀氏の祭祀論を読む。
8日 寒中御機嫌伺の為め参内。夜、準備。 9日 夜、猪狩・中村両氏と商量す。
11日 沼津御用邸東付属邸に於て、御始業式後挙行。
12日 前同断に於て、第二十七回(崇倹か)御進講。山根、土屋、小笠原、亀井諸氏、参列。
13日 浜尾氏の病を訪し、且つ相談する所あり。
14日 夜、(教育)勅語研究。 15日 猪狩氏に整理を托す。
16日 教習科茶話会に臨み、参考を求む。夜、中村氏と商量す。
17日 松平直亮伯来訪。談ずる所あり。光雲寺に於て、猪狩・中村二氏と商量。帰宅後、猶研究。
19日 第二十八回(教育勅語か)御進講。入江子(爵)、小笠原、亀井外両氏、参列。後、入江子に談ずる所あり。
2月16日 第二十九回(尚武か)御進講。小笠原子、外一両氏、参列。後、入江子に談ずる所あり。








































