10分ほど連続で刺激を与えると、収縮力は徐々に落ちてしまいます。
しかし、1時間程度休ませると力が戻るというサイクルも確認されました。
これはまさに人間の筋肉が運動後に休息をとることで回復する仕組みに近く、“生体を使う”ならではのメリットと同時に、運用時の制約も示す結果といえます。
一方で、まだ克服すべき課題も残っています。
まず、このバイオハイブリッドハンドは現在、水中で浮かせた状態で実験されています。
筋組織に十分な栄養を供給し、乾燥や衝撃から守るためです。
今後、空気中でも安定して動かせる技術を確立する必要があります。
さらに、指を曲げた後に“元の位置に戻す”力が弱いことも指摘されています。
生物の指は、屈筋と伸筋が拮抗しあうことで曲げ伸ばしがスムーズですが、今回のハンドでは伸筋にあたる構造が充分に整っていません。
今後は拮抗筋を取り付けたり、弾性素材を使って復元力をもたせたりする改良が期待されます。
義手や義足が生体材料になるかもしれない
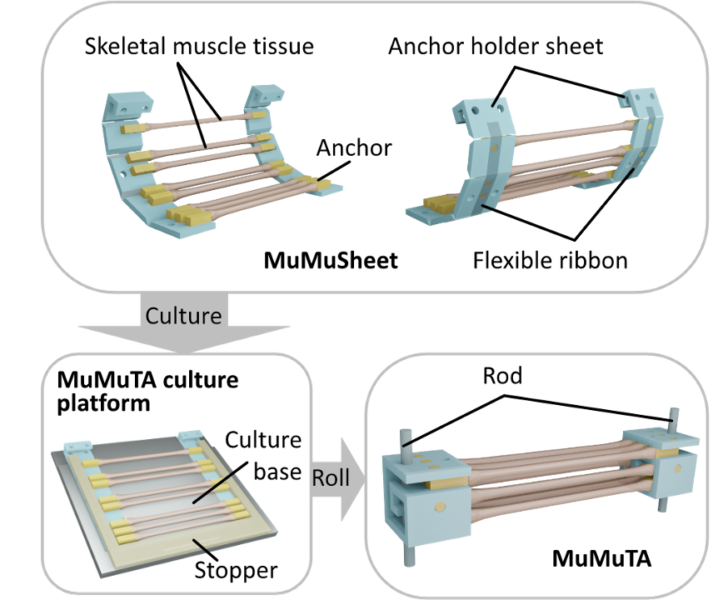
今回の研究成果は、バイオハイブリッドロボットが“単なる実験的なガジェット”を超えて、実用的な大きさと機能を獲得しつつあることを示しています。
とりわけ、義手・義足などの医療分野での応用が期待されており、生体筋肉の柔軟性を備えた高性能な義手が登場すれば、利用者の負担は大幅に軽減されるでしょう。
また、筋肉の運動をリアルに再現できることから、薬物試験やリハビリテーション研究にとっても大きな前進となる可能性があります。



































