研究内容の詳細は『Cognition』にて公開されました。
目次
- 偏見の中でも強力な「政治的偏見」を利用する
- 相手の偏見を信頼に変換する「心理メカニズム」
偏見の中でも強力な「政治的偏見」を利用する
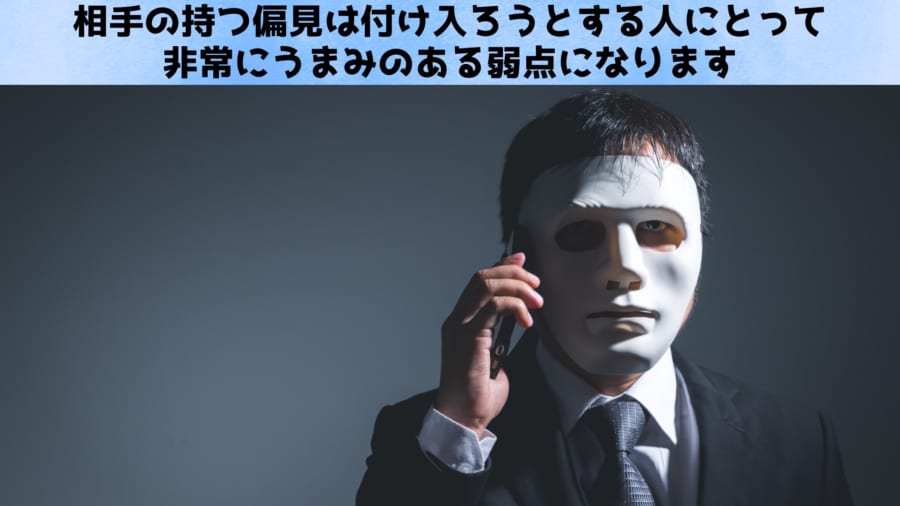
近年、米国をはじめ世界の多くの国で、政治的立場の対立が顕在化・先鋭化しつつあります。
いわゆる「政治的二極化」が進むと、政治家やコメンテーターのみならず、SNSや一般メディアにおいても、自分たちの支持者をより強く惹きつけるために“党派的言語”が積極的に用いられるようになります。
たとえば、同じ出来事を「抗議」と呼ぶか「暴動」と呼ぶかで、聞き手が感じる意味合いや重みがまったく変わってしまうのは、その好例といえます。
この背景には、「分断を煽るような内容のほうが目を引きやすく、拡散されやすい」という情報拡散メカニズムが存在しているという指摘もあります。
不特定多数の大勢を味方にするよりも、争っている一方から好かれるようにするほうが、低コストかつ短期間で多くの指示を得られるからです。
ソーシャルメディアのアルゴリズムやオンラインでの情報消費パターンに関する過去の研究(Brady, Crockett, & Van Bavel, 2020 など)によれば、感情的な内容ほど“バズ”を起こしやすく、結果として対立や偏見を増幅する投稿や報道が注目を集めやすい傾向があります。
党派的言語は、こうしたメディア環境の中で特に有効であり、同じ立場の人々の結束を高める一方、異なる立場の人々との距離をさらに広げるリスクを孕んでいます。
政治的二極化が深まるほど、党派的な表現によって得られる「同調のメリット」はますます大きくなる一方で、異なる意見を持つ人々や中立的立場の人々に対しては、過度なバイアスや“不公正なレッテル貼り”として受け止められる恐れがあります。














































