たとえば文脈性側で
セット(質量, 長さ) で測った場合 → 質量が100gだった
セット(質量, 色) で測った場合 → 質量が105gに変わる
という古典的に両立しない結果が得られた場合、上の対応付けや矛盾を、非局在性シナリオに現れる矛盾」、つまり「遠く離れているのにそんな関連性があるはずが…」という矛盾と同じ構造を持っていることを発見したわけです。
言い換えるならば
文脈性で見られる“矛盾”
非局在性で見られる“矛盾”
この2つが実は「同じタイプの論理的構造」を持っていて、一方で起こる不思議な結果をそのまま他方でも再現できる、というわけです。
このことは「文脈性があるからこそ、非局在性(遠く離れた場所の結びつき)を成り立たせる」あるいは「非局在性は文脈性に含むことができる」可能性を示します。
そして「文脈性 ⇔ 非局在性変換」がうまくいくということは、離れた粒子の強い相関(もつれ)を、単一粒子の文脈依存という同じ原理で説明できるかもしれない、という意味です。
もし両者が本質的に同じ仕組みによって成り立つなら、もつれがなぜ壊れず、どんな条件で強い相関を保つのかも、文脈性を理解することで解明できる可能性があります。
つまり、1粒子の測定の不思議(文脈性)が複数粒子のもつれにもそのまま当てはまり、もつれを維持する“秘密”が共通のルールとして説明できるようになるわけです。
要は、スゲーってことです。
ただ数学的にそれが確かであっても、現実世界で変換が可能であるかは実証できていませんでした。
そこで今回、厦門大学の研究者たちは、文脈性と非局在性の変換を現実世界で成し遂げるための実験を行うことにしました。
そのための鍵になったのが「6次元の光」です。
6次元の光を使うと見えてくる新事実
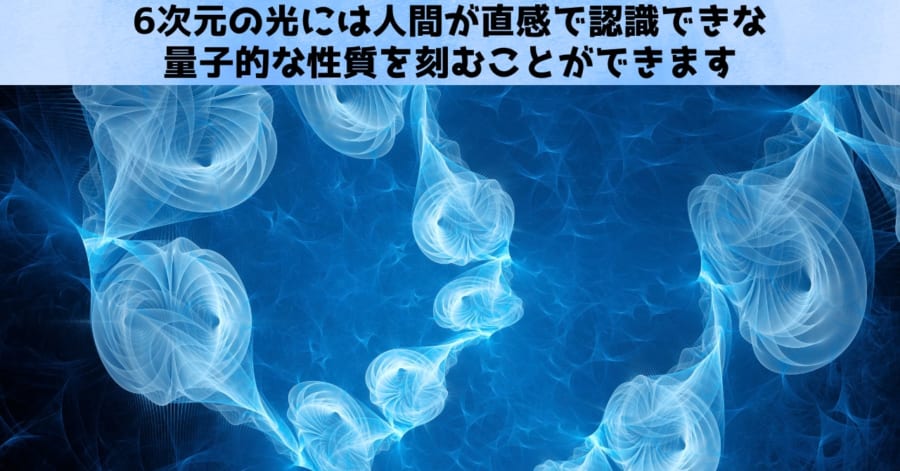
人間が直感的に扱える次元とは、たとえば「上下・左右・前後」という空間的な3次元や、色の3成分(R・G・B)など、少数の次元に限られます。










































