このように、纏足には憧れと嫌悪という二面性が絡み合っていました。
纏足に憧れる者にとっては、それは達成感や自己肯定感をもたらすものだったのです。
一方で、纏足に耐えかねた者にとっては、抑圧と苦痛の象徴でした。
だが、いずれの場合にも、彼女たちの小さな足は社会的な価値を具現化する存在であり、家族の中でも、地域社会でも、その役割を果たしていたのです。
結局のところ、纏足は個人の美意識だけでなく、家族や社会の問題でもありました。
親は纏足を通じて娘に家族の名誉を背負わせようとし、女性たちはその枠組みの中で、苦しみながらも己の価値を見出そうとしたのです。
この複雑怪奇な文化を、ただの過去の奇習として片付けてしまうのは惜しいです。
それは、現代の私たちの美や価値観にも、何かしらの問いを投げかけているように思えます。
名実ともに痛みを伴うものであった、纏足からの解放
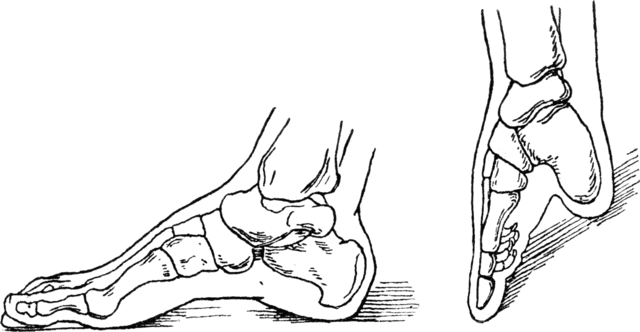
しかし1920年代に入ると、状況は一変します。
纏足の伝統が中華民国が主導した「放足運動」という波にさらわれ、一転して解放を強いられる時代が訪れたのです。
この放足運動は単なる通達では済まされず、人を派遣して徹底的に纏足をやめさせるという強制的なものでした。
これまで「纏足しなければならない」という社会規範に縛られていた女性たちは、今度は「纏足を解かなければならない」という別の圧力に苦しむことになったのです。
纏足を解くという行為は、女性たちに新たな痛みを強いました。
何十年も縛られて変形した足が完全に元に戻ることはなく、逆に歩行が困難になる場合もあったのです。
さらに、これまで足を隠すことが「正しい」とされていた社会において、人前に足を晒さなければならないという状況は、女性たちにとって大きな精神的苦痛となりました。
「解くこと」は解放ではなく、また別の形の束縛だったのです。









































