- ふたつめのテーマは「グリーディジョブ」こそが元凶だとする分析
これは日本における「男女の賃金差別」みたいな話でも同じなんですが、例えばある企業に新卒で入った男女がいたとして、じゃあ太郎くんと花子さんの初任給が性別を理由に違うなんてことがあるわけではないんですよね。それは違法です。
例えば5年目とかまで普通に出世していって、同じ職階で同じ残業時間とかなら、これも男女で給与が違うということはありえない。
そういう形で条件を揃えて、ゴールディン氏の本の中では色んな「同じ年に同じロースクールを出た男女カップルが同じ法律事務所に就職したとして」みたいな事例がかなり定量的に分析されています。
そういうデータ上でも、「子育て」問題が発生するまでは、男女の賃金差はほとんどない。
一方で、子供ができると、夫婦のどちらかが「柔軟な働き方」をせざるを得なくなり、それを女性側が担う可能性が高まり、結果として給与の男女格差が広まり始める事が示されている。
そして、現代社会において非常に高給である「グリーディジョブ(Greedy Jobs 貪欲な仕事)においては、「24時間365日いつでも駆けつけられる状態を維持する」ような献身こそが求められがちであると。
その時にそのカップルは選択を迫られる。
夫婦ともに時間に融通の効く仕事にシフトして子育てする(グリーディジョブから夫婦ともに撤退する) 夫婦どちらか(現状は夫の場合が多い)がグリーディジョブに挑戦し、もう一方は時間に融通がきく仕事にシフトする
上記のABの選択肢が出てくるわけだけど、今のアメリカでは、そして多分日本でも、「A」を選ぶと夫婦合計の世帯年収がかなり下がっちゃうんですね。
だからある意味で「カップル内公平性」を放棄することでBを選ぶと、「世帯年収を最大化」できて、かつ少なくともカップルの片方はちゃんと子育てに参加できる・・・というある種の「夫婦にとっての”最適”な選択」が生まれてしまう。
で、これはカップル間の納得づくの協力関係で生まれることだから、別に「性差別が原因」とも言えないところがあるから難しいわけですよね。
「女性の側がケア役割を担うべき」という”差別的な性規範”ゆえにこうなってるのが許せないというのなら、じゃあ女性側が「グリーディジョブ」に挑戦して男が負担減する選択肢を選べばいいじゃん、という話になるからですね。(もちろん、そうやって”片方がキャリアを譲った”にも関わらず、グリーディジョブを担ってる方の人が後々”誰が稼いでると思ってるんだ”みたいな態度を取るのは良くない、みたいな話は、男女逆の場合も含めて人間の信義として良くないことではあります)
この記事の冒頭で、ゴールディン氏の研究には日本の「反フェミニズム論壇」の意見がある程度含まれている側面があると書いたのはそういうところです。
で、確かにこの分析結果を素直に読むと、一種の論理的帰結として「じゃあ女性側がグリーディジョブに挑戦して男側が雇用調節してケア役割になればいいじゃん」という話は当然出てくるんですが、その方向性についてゴールディン氏は、そうする事で男女の賃金格差自体がバランスする可能性はある事は認めています。
現実にも私の知り合いにもそういう例はチラホラ出てきていますし、今後増える例であることは間違いない。
ただ一方で、ゴールディン氏は時代の流れとして、男女両方ともに「もっと子供に時間を使いたい」と思っている人が増えていて、優秀な人材を確保したければそういう方向にシフトする事が必要ですね…という流れがあることから、「女もグリーディジョブやれよ」論にはあまり乗り気じゃない感じなんですね。
そうじゃなくて、社会全体が「グリーディジョブでなくても成果を出せる形」に転換していく方向を考えるべきだ、という立場。
そして、ど うすれば「グリーディジョブの非グリーディジョブ化」が可能になるのか?という例で事例化されているのは、アメリカにおける「薬剤師」関連の仕事です。
- 仕事の標準化・システム化で「取替可能」になる事でグリーディジョブから解放される?
アメリカにおける薬剤師関連の仕事は、今は男女の給料差がほとんどなく、また、「子育てのために時間に融通の効く仕事のスタイル」を選んでいても、時間給あたりのペナルティはほとんどないらしい。
この変化が起きたここ数十年の間に何があったかというと、薬剤師業が「標準化・システム化」されて、個々人のワーカーが取替可能な存在になったからなんですね。
昔の薬剤師は、一人ずつの顧客に対して特別に調合したりする仕事が多く、顧客から見て「指名」で仕事をしている薬剤師が多かった。
でも今の薬剤師はもっと圧倒的に標準化されており、そもそも零細事業者の薬局がほとんどなくなり、巨大なチェーンビジネスがどんどん買収してシステム化が進み、「誰がやっても同じ」仕事になった。
結果として、「顧客から指名を受ける薬剤師」みたいな存在は消滅した事によって、「グリーディジョブの非グリーディジョブ化」が完成した、ということらしい。
そうすると、全体的に平均給料は増えるし、なにより時間に融通がきく仕事になることで、男女の給与格差もほとんどない状態になったという。
ゴールディン氏の著作の中で、この話が「本当にうまく行っている例」というのは薬剤師ぐらいで、そこの説得力はイマイチ弱いように思うんですが、この「標準化によって取り替え可能な存在になる」事がむしろ「男女賃金格差を解消する上で重要」というのは、一般的に思われている以上に応用可能な方法だと思います。
- 「標準化・システム化」による効率上昇が役に立つ側面は必ずある
以下の私の本でも詳しく書いてあるんですが、日本の中小企業が他国に比べて「零細」サイズのまま放置されている企業が多く、結果として「取替不可能」な状態の仕事であるゆえに長時間労働や薄給から抜け出せない例が多いということは、かねてから色んなところで指摘されている点ではあります。
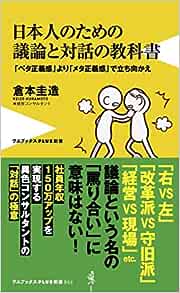
『日本人のための議論と対話の教科書』
上記の本では、実際にクライアント企業で10年で平均給与を150万円ほど引き上げられた事例などを紹介しつつ、そのあたりの変化について述べていますのでご興味があればぜひ。
例えば「経理の人が一人しかいない」サイズの会社なら、繁忙期にその人が死ぬ思いをするのは避けられないので、その人が「柔軟な働き方」ができるわけがない。
これは単に「子育てのために」というだけじゃなく、別に子供がいない人でも休日の取りやすさといった観点からも同じ問題があるといえるでしょう。
それが、経理の人が数人いて、仕事を抱え込まずにお互い取り替え可能な状態が維持できる規模であるなら、比較的状況に応じて融通効かせることは可能になる。
また、そのぐらいのサイズになれば「当たり前のIT投資」とかも可能になるので、そもそも経理作業みたいなものひとつとっても同じ作業とは思えないぐらい効率化している可能性も高い。
「標準化」に全然なじまないように思われている「営業」の仕事みたいなものも、最近は「個々人のスキルと度胸」でフルコミッションで売るみたいな世界はだんだん少なくなってきてはいて、見込み客集めからそこへのコンタクト、契約からのアップセルのタイミングまですべてシステム化されていて、
素人を集めて言ったとおりに動いてもらう
…事でむしろ成果を出す流れになりつつある。「顧客」を「担当者」だけで囲い込ませないようにする流れも普通に起きている。
先述した私の本でも書きましたが、今日本中で「あまりに零細のまま放置されてきた日本企業を”資本の力”で統合して”戦えるサイズ”にし、新時代風の仕組みを導入して効率化していく」流れは絶賛進行中なので、その「動き」と丁寧にジェンダームーブメントは協業していく事が今後必要になってくるでしょう。
ビジネス
2023/11/13
日本の賃金の男女差別の解消法をノーベル経済学賞研究に学ぶ
『アゴラ 言論プラットフォーム』より
関連タグ
関連記事(提供・アゴラ 言論プラットフォーム)
今、読まれている記事
もっと見る










































