ドラッガー
資本主義体制の理論的守護者とみられながら、資本主義の後の世界を考え続けていたもう一人の巨人、それはドラッガーである。
主著『ポスト資本主義社会-21世紀の組織と人間はどう変わるか』(P.F.ドラッガー、ダイヤモンド社、1993年。原書も1993。)は1993年に出版されている。
社会主義・共産主義の崩壊を受けて生き残ったとみなされる資本主義が、ポスト資本主義社会にとってかわられるのである。(春日、前掲書、p.98~99)
春日によれば、ドラッガーは『断絶の時代-いま起こっていることの本質』(上田惇生訳、ダイヤモンド社、1999年。初版は1969年)以来、非経済至上主義社会を主張していた。皮肉なことに、その後の新自由主義は全く逆の方向に進んだ。
ドラッガーは、本書で資本主義から知識社会へ進むことを主張し、それを実行するビジネス界のエグゼクティブに期待を寄せた。エグゼクティブ達が教育ある人間であることを期待したのである。
第一段階 産業革命 生産への知識適用
第二段階 生産性革命 仕事への知識適用
第三段階 マネジメント革命 知識の知識の適用
(5)終焉論
21世紀の初頭から、さまざまな立場による「資本主義の終焉論が流行している。(金子、前掲書、p.41)
水野和夫は終焉をタイトルにして何冊もの本を書いている注8)。しかし、終焉のプロセスと、その後については言及を避けている。
中谷巌は「『資本主義以後の世界』が訪れることは確実である」と言いながら、正直に「あまりにも複雑な問いであり、正確に見通すことは難しい」と回避している。(中谷巌、『資本主義以後の世界』、徳間書店、2019年、p.4)
広井良典の新書、『ポスト資本主義』(岩波新書、2015年)の副題は“科学・人間・社会の未来”だ。結末を知りたくて最後まで読むと、そこにあるのは「持続可能な福祉社会」という一言だけだ。
マルクス派の宇野派の論客、加藤栄一、馬場宏二、三和良一は共著で『資本主義はどこに行くのか』(東京大学出版会、2004年)を発表した。副題は、“二十世紀資本主義の終焉”だ。これはリーマンショックの前に書かれている。結論がふるっている。「資本主義がどこに行くのか」と問われれば、「どこにも行かない」という。
まったく同じタイトルの本を滝川好夫が書いている。『資本主義はどこに行くのか』(PHP研究所、2009年)。協同組合に理解を示す論客だけあって、道徳的に退廃した資本主義を批判し、道徳経済の構築を提唱、最後は“自立・互助・自制のすすめ”で終る。著者の願いが書かれているが、資本主義がどこに行くのかは不明である。
諸富徹の新著、『資本主義の新しい形』(岩波書店、2020年)の書き出しも「資本主義はどこへ向かうのか?」だ。上の2冊と違い、分析がある。日本の主要企業の利益剰余金が1980年の44兆円から、1990年128兆円、2017年440兆円、つまり最近の30年で3.5倍になったことを示す。ところが、これが投資されない。投資を主軸にフロンティアを拡大するという資本主義とは“異質な芽”が再登場している。この傾向を諸富は「資本主義の非物質的展開」という難解な用語で説明ようとする。
諸富の示した図3-2は興味深い事実を示している。1990年代の初めまでは、企業は儲かるから投資したがそれ以降はそうでなくなった。それは成長企業群よりリストラ企業群が多くなったからである。
これは私達流に言えば、利潤原理の短絡化であり、つまりは楽して儲けるということだ。不祥事の背景にあるのは、資本主義の倫理の後退であり、衰退の明らかな証である。
投資不足という問題を取り扱いきわめて興味深い分析を小川和男がしている。これについては別の論文でふれた注9)。
終焉を論じて圧倒的、かつ優れているのは本シリーズでしばしば言及するD.ハーヴェイとW.シュトレークだが、ここでは論じきれない。内容が深く、提起されている論点が広いからである。
ハーヴェイは、資本主義がなぜ“おしまい”になるのか、その必然性を豊富な研究と考察で展開する。シュトレークは、やはり深い考察の上で、長い過渡期の必然性を展望している。
この二人に比べると、ジェイソン・ヒッケルの著書はかなり見劣りする。邦訳のタイトルは『資本主義の次に来る世界』注10)だが、原題は『Less Is More』、少ない方が豊かだ、である。最後にアミニズムまで登場する人類学者らしい構成だが、説得力は乏しいし、次に来る世界は示されていない。
社会主義失敗の教訓旧ソ連は言うに及ばず、現在でも社会主義を標榜する国々の現状が一部の例外を除いて“失敗”であることは明白だ。中国を除けば経済状況は低迷だし、多くの国で環境の問題などは全く考慮されていない。
なにより問題なのは人権問題だ。これらの国の人々に自由は少ないようだ。少なくとも政治的自由はない。看板に民主主義と書いてあっても、そこに独裁者の肖像はあっても人々の姿は描かれていない。
未来は人々が自由で幸せで経済的には豊かでなければならない。旧社会主義国は、この理想から遠ざかっているように見える。対照的に現代の資本主義先進国には、未来を構築するためのピース・要素はかなりの程度まで揃っている。資本主義のままで、一定の修正・修復で行こうという論調が多いのはこのためだろう。しかし、第4楽章に悪化した病理は、もはや資本主義の枠内では解決できないものが多いし、さらに悪化する懸念が高い。それは人類にとって危険なことだ。
暴力革命は過去の遺物であるが、議会で多数を得て変革の道を進もうとするとき、保守派の支配下にある軍隊がこれを阻止するという事態が世界ではしばしば起きている。民主勢力を軍隊が暴力的に排除する。選挙で選ばれ、国民に圧倒的に支持されているアウンサン・スー・チーさんは、いまだに囚われの身だ。
変革に際して軍隊の中立をどうやって保つか。軍隊はほとんどの国にあるのだから、これは慎重に検討されるべきだ。同時に、あらゆる革新の道は非暴力でなければならない。
資本主義の全否定。ロシア革命当時の状況からすれば仕方がないのだが、旧ソ連の失敗の原因の一つは資本主義を全否定したことだ。しかし、資本主義が発明した制度はそれなりに効率的だ。経済的には、銀行制度と証券・株式制度、政治的には代議制と民主主義、社会的には社会保障などである。この観点から、資本主義の諸制度で残すべきものはどれで、どう修正していくかを検討する注11)。
避けられない課題どのような未来を描くにしても避けられない課題がある。
環境の制約。地球が人類の生存に適さないようになる。もし、人工的にその方向に進んでいるなら、未来構想以前の問題として、これを止めるのは当然である。
人々の孤独。その昔、人々はコミュニティの一員であった。しかし、それは束縛でもあった。人々がどこの階級にいるかで束縛の程度は大いに異なった。でも、概ね安全ではあったし、孤立もしていなかった。
現代社会の孤立感は深まっている。コミュニティが壊され、家族までもがその危険にある。老後の一人暮らしは常態になり、都会に出て行った若者の多くも“ひとり”だ。
こうした状況を金子勇は“粉末状況”と表現した。ロバート・パットナムが『孤独なボーリング』注12)で示した状況である。人々を粉末のままにしておいては、明るい未来は描けない。
先導的試み未来を語ることは、どのみち試論である。それでも、これまでに発表された様々な論考には描かれるべきものが描かれていないという不満を持つ。看板に見出しがない。封建主義から資本主義と歴史は進んだ。その次は、社会主義だったが、それは失敗した。となれば、歴史が終わったと主張しない限り、将来は資本主義でもない社会主義でもない何かなのだ。
そこで勇気を持って〇〇主義と見出しをつけてみる試みは、やってみる価値がある。例をひとつあげる。かなり前から、人体に良い作用を及ぼす微量の成分があることは知られていた。ある日、それにビタミンという総称がつけられた。そこからビタミンの研究が進み、数多くの種類とそれらの効果が発見されたという。
試みの第1号は廣田の本だ。(廣田尚久、『共存主義論-ポスト資本主義の見取り図』、信山社、2021年)。これについては別の論文(注5)で論評した。
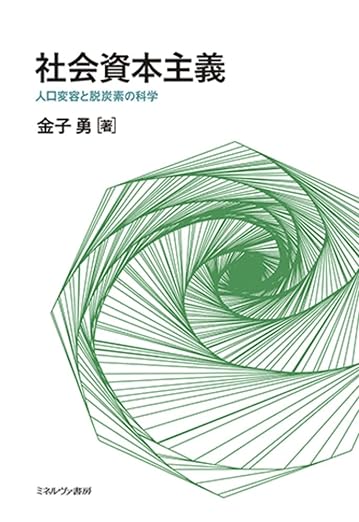
もう一人は金子勇だ。『社会資本主義:人口変容と脱炭素の科学』(ミネルヴァ書房、2023年)は400ページという大著であり、金子の生涯の研究を凝縮したものであるから、生半可なコメントなど受け付けないのだが、ここでも本稿との関わりに限定して“短評”を記しておきたい。
まず注意すべきは、資本の理解が経済学者とは違うことだ。経済学では、資本は価値の運動体であり、現象としては貨幣から始まる(狭義の資本)。金子の考える、資本はそんな狭いものではない。社会の福祉の向上に貢献する何かを生み出す、広い意味での資源のようなものを資本とみなす。それには次の三つがある。
社会共通資本(Social Common Capital)、これは道路などのインフラで人々の生活の質を支えるもの、それが示すのは物的なものだから、公共世界にある固定資本である。
社会関係資本、これは『孤独なボーリング』に描かれた人々の関係だ。人間は一人では生きにくいから、人々との関係があった方が幸せに近い状態になる。いわばソフトな資本だ。
最後は人間文化資本。これは人々の知的・体力的な質を高めるもので、要は教育のシステムを示している。住む世界がよくなっても、人間がよくなっていなければ意味はない。教育を“資本”とするのは、もはや経済学者にはついていけないが、敢えてそうしたところに金子の狙いもある。
この三つの“社会資本”が、狭義の資本の運動場として開発された舞台で機能し、剰余ならぬ人々の幸せの糧を再生産するシステム、それを社会資本主義と呼んでいる。
金子は、資本主義の後も資本主義と言明している。しかし、金子の方向は、資本主義の次を想定しているように見える。社会学の考える“資本主義”は、経済学者の考える資本主義とは、拡大されているという意味で、異なる。単に拡大されているだけでなく質的にも異なるのだが、それらが機能する社会を次の世界だと構想している。
金子は“資本”を経済学から解放しようとしている。別の表現をすれば、資本を社会で取り囲もうとしている。それは、ポランニーの埋め戻しの試みと共通している。資本を残しながら非資本で取り囲むという発想は本シリーズの基調でもある。
金子による資本主義の拡張はハーヴェイの示した、三つの循環を結合した図を重用しているところにも、よく表れている。
この「社会資本主義」で人口変容の生じるであろう未来、CO2 の充満しそうな世界を乗り越えていくべきだというのである。
金子の「社会資本主義」は具体的な目標を持っているところが秀れている。どんな構想、見取図を示そうと、この二つの課題に立ち向かえないのなら、話にならないという訳だ。とにかく、来るべき世界に名前をつけて進もうとするのである。シュトレークは現代の社会学を小さな領域にとじこもっていると批判した。『社会資本主義』はそれへの金子の答えでもある。










































