目次
フリーランスは課税事業者への転換を迫られる?
じつは企業側も、インボイス制度はデメリットだらけ!?
フリーランスは課税事業者への転換を迫られる?
齊藤:
インボイス制度の導入によるフリーランスへの影響はすでにいろいろ明らかになっていますが、改めて先生方の見解を教えてください。
山内:
まず、ハッキリ言って良い影響は殆どないと思ってください。例外的に消費者相手のビジネスや免税事業者同士のビジネスでは、インボイス登録の要請が強くないと考えられますので悪影響が出にくいと予想されています。
ただ、そうでない場合、つまり事業者相手のビジネス全般では基本的に悪影響が多く、インボイス登録を行い、課税事業者になった場合は通常以下の3点のいずれか、または全てが問題になるでしょう。
- 利益が減る可能性がある
- 税負担が増える可能性がある
- 消費税申告による事務負担が発生する
また、「利益が減る可能性がある」という問題ともリンクしますが、競合他社との価格競争でも不利になる可能性が高いです。いままでは消費税相当額分を利益にできたため、商品やサービスの価格を割安に設定できました。だから事業が成立しやすく、同時に「ちょっと値引サービスしておきますね」みたいなある種の「ゆるさ」があっても生活していけたんです。

齊藤:
インボイス制度の導入で、小規模事業者は事業そのものの成立が危ぶまれる……と。
山内:
はい。生活のために価格を上げざるを得なくなるので、ビジネスモデルを見直し、経営努力をするしかない状況が到来する可能性は高いです。同時に、ビジネスはドライになり、「ゆるさ」は失われていくでしょう。なかには、廃業を選択せざるを得ない人も出てくると思います。
消費税を納税せず、免税事業者のまま事業を続けるという選択肢もありますが、取引先の税負担のことを考えると中・長期的には課税事業者への転換を迫られることになりそうです。
齊藤:
その「課税事業者への転換を迫られる」という意見はよく耳にするのですが、どうしてフリーランスは課税事業者を選択する必要があるのでしょうか?
伊沢:
インボイス制度の導入後は、課税事業者との取引以外で「仕入税額控除」という控除が制限されます。これは、取引先に払った消費税を、客先から受け取った消費税から差し引きできる制度で、取引先が課税事業者でも免税事業者でも、仕入税額控除が制限されないから消費税を納めなくてもいいフリーランスに消費税を払っていたんです。
しかし、仕入税額控除が制限されるとどうなるか。免税事業者に払った消費税は、損になってしまいます。そうなれば事業者は当然、消費税分を支払いたくないので、消費税の請求をさせてもらえなくなる可能性があります。

じつは企業側も、インボイス制度はデメリットだらけ!?
齊藤:
インボイス制度といえば、なにかとフリーランスの負担だけにクローズアップされがちです。しかし、「課税事業者への転換をお願いする立場」ともいえる企業側にとって、インボイス制度はどのような影響を与えるのでしょうか?
山内:
意外かもしれませんが、じつは企業側にとってもインボイス制度はデメリットだらけなんです。
先ほどもお話ししたように、課税事業者登録をしていない仕入先や外注先に支払った消費税は、原則として仕入税額控除ができなくなります。そして、取引先が課税事業者なのか、免税事業者なのかを把握し、管理する事務手続きも増えます。
「全員に課税事業者への転換を迫ればいい」「免税事業者を切ってしまえばいい」と思われるかもしれませんが、話はそんなに単純じゃないんです。
齊藤:
それはなぜですか?
山内:
たとえば、取引上優越的な立場にある発注側が、免税事業者である取引相手に対して、「課税事業者にならないなら取引を打ち切る」といったことを一方的に通告する行為は独占禁止法に抵触するおそれがあります。
また、発注側が免税事業者である下請事業者に対して、インボイス制度開始後に一方的な値下げを通告したり、課税事業者になったにもかかわらず価格交渉に応じず据置きを通知するといった行為は、下請法に抵触するおそれもあります。
そこで企業側は、免税事業者の負担にも配慮し、丁寧に協議や交渉をおこなう必要があるわけですが、そもそもそうした協議や交渉をおこなうこと自体が大きな手間でありストレスですよね。言い方を一歩間違えれば法律違反になるリスクがあり、法律には抵触しない場合も、交渉の過程で取引先と険悪な関係になってしまう可能性があるからです。
こうした影響が無視できないことから、インボイス制度には経過措置が設けられており、当初の3年間は免税事業者の消費税相当額の8割が控除でき、その後の3年間は5割を控除できるとされています。価格交渉においてはそうした点も考慮し、取引当事者双方が落としどころを協議していくことになるかと思います。
伊沢:
インボイス制度に関連して、フリーランスのみなさんはピリピリしています。そんな状態でヘタな対応をすれば、SNSやクリエイター向けのプラットフォームなどで「こんな酷い対応をされた!」と告発されるリスクがある。たとえ法律的にはOKでも、告発されれば炎上する可能性は十分ありますよね。
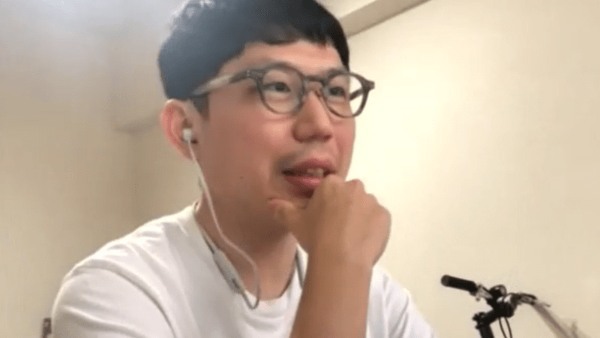
齊藤:
たしかに、SNSの時代だからこそ告発のリスクはあまりにも大きいですね……。インボイス制度は企業側にも大きな負担だと分かりました。
伊沢:
当面は免税事業者に支払った消費税の8割を仕入税額控除できるという経過措置もありますが、企業側もゆるやかに首が絞められていくような状態だと思ってください。
山内:
インボイス制度の良い効果を強いてあげるならば、請求書の保管などのために企業事務のDXが推進される可能性はあります。多くの企業において電子インボイスが普及すれば、事務コスト軽減も図りやすくなります。一方、業務フローの電子化には大きな投資が必要ですし、いまだコロナ禍の混乱期が続く中で、早急にそこまで対応できる企業がどこまであるのかといった点は気になります。
ただし、取引のグローバル化が進む以上、電子取引自体は避けられない流れ。この局面をどう乗り切るかで、企業の将来が変わるともいえます。改正電子帳簿保存法の猶予期間も残りわずかですので、いずれにしても何らかの対応が必要となることでしょう。









































