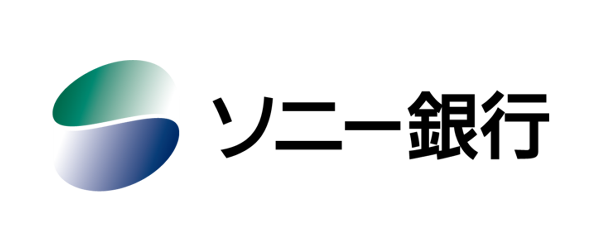日本には、都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行など、あわせて120行を超える銀行が存在しており、間接金融の担い手として日本経済を支えている。日本国内の銀行のうち、信用格付や時価総額、自己資本比率など、さまざまな指標ごとのTOP10を紹介する。
目次
- 「信用格付」ランキングTOP10……債務の支払い能力が高いのはどこ?
- 「時価総額」ランキングTOP10……三菱UFJ銀行を擁する金融グループが第1位
- 「預金口座数」ランキングTOP10……ネット銀行の人気の高さを口座数で比較
- 「経常収益」ランキングTOP10……一般企業の「売上高」に相当、三菱UFJが強い
- 5,「業務粗利益」ランキングTOP10……決算説明資料で確認できる業務上のネット収益
- 「自己資本比率」ランキングTOP10……銀行の財務基盤の安全性を示す指標
- 「預金残高」ランキングTOP10……預金残高NO.1は国内最多店舗数のゆうちょ銀行
- 「貸出金残高」ランキングTOP10……融資の多さでも圧倒的存在感の三菱UFJ銀行
- メガバンク3行の規模と収益力は桁違い、特性を活かした地方銀行などにも注目
- ネット銀行で口座を開設するなら
「信用格付」ランキングTOP10……債務の支払い能力が高いのはどこ?
信用格付とは、債券の発行体が債務を返済する能力を、第三者機関である格付会社が客観的に評価したものである。世界3大格付会社としてはMoody's、S&P、FITCHが、国内ではR&I(格付投資情報センター)やJCR(日本格付研究所)が有名だ。
銀行が債券を発行する際には、債券市場の金利水準だけでなく、発行体となる銀行の支払い能力を示す信用格付も、利率などの発行条件に影響を及ぼす。
さらに、機関投資家や一般投資家が銀行債券を購入する際には、各行の信用格付をチェックして債務返済能力を評価した上で購入の判断を下すため、銀行にとって、信用格付の果たす役割は重要だ。
以下の信用格付ランキングTOP10では、2021年6月2日現在で銀行が開示している信用格付情報を収集し、高い評価を得ている銀行や、多くの格付会社から格付を取得している順に上位10行を紹介する。
「信用格付」ランキングTOP10
| 順位 | 銀行名 | Moody’s | S&P | FITCH | R&I | JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期 | 長期 | 長期 | 長期 | 長期 | ||
| 短期 | 短期 | 短期 | 短期 | 短期 | ||
| 1 | 三井住友銀行 | A1 | A | A | AA- | AA |
| P-1 | A-1 | F1 | a-1+ | J-1+ | ||
| 2 | 三菱UFJ銀行 | A1 | A | A- | AA- | AA |
| P-1 | A-1 | F1 | a-1+ | ― | ||
| 2 | 三菱UFJ信託銀行 | A1 | A | A- | AA- | AA |
| P-1 | A-1 | F1 | a-1+ | ― | ||
| 2 | みずほ銀行 | A1 | A | A- | AA- | AA |
| P-1 | A-1 | F1 | a–1+ | ― | ||
| 2 | みずほ信託銀行 | A1 | A | A- | AA- | AA |
| P-1 | A-1 | F1 | a–1+ | ― | ||
| 6 | 三井住友信託銀行 | A1 | A | A- | A+ | AA- |
| ― | A-1 | F1 | a-1 | ― | ||
| 7 | ゆうちょ銀行 | A1 | A | ― | ― | ― |
| P-1 | A-1 | ― | ― | ― | ||
| 8 | 千葉銀行 | A1 | A- | ― | ― | ― |
| P-1 | A-2 | ― | ― | ― | ||
| 9 | りそな銀行 | A2 | A | ― | A+ | AA- |
| P-1 | A-1 | ― | a-1 | ― | ||
| 10 | 横浜銀行 | A2 | ― | ― | AA- | AA |
| P-1 | ― | ― | a-1+ | ― |
上位6銀行には国内の3大メガバンクと信託銀行3行が含まれている。いずれも格付の取得数やランクにほとんど違いはなく、債務の支払能力が高く評価されていることがわかる。
第7位から第10位までの銀行も日本国内では認知された銀行ばかりであり、信用力の高さに大きな差は見られない。
第1位,三井住友銀行:外貨建シニア債などを多数発行
三井住友銀行は、三井住友フィナンシャルグループの100%子会社であり、グループの中核的な銀行でもある。
高格付を背景にした、米ドル建てもしくはユーロ建てのシニア債(低リスク・低利回りの高格付債券)を中心に、円貨建劣後債や米ドル建劣後債も多数の発行実績がある。
三井住友銀行は2016年以降、円貨建てか、外貨建てかを問わず、新発債券を発行していない。
第2位,三菱UFJ銀行:国内普通社債と米ドル建普通社債が中心
三菱UFJ銀行は、三菱UFJフィナンシャル・グループの中核銀行である。
社債の発行は三菱UFJ銀行の主な資金調達手段になっており、現在も、償還前の社債を数多く抱えている。
過去10年間に発行した社債は国内普通社債と米ドル建普通社債であるが、2016年以降は新規の社債発行実績はない。
第3位,三菱UFJ信託銀行:三菱UFJ FGの信託銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループの信託銀行であり、グループ内では三菱UFJ銀行に次ぐ規模の銀行である。国内の3大信託銀行のうちの一角。
社債の発行実績は決して多くないが、過去10年間に国内普通社債とユーロ米ドル建てとユーロ豪ドル建ての普通社債を中心にした資金調達を行っている。
2017年以降の社債発行実績はなく、すべての社債は2021年中に償還を迎える予定である。
(公式サイトへ)
「時価総額」ランキングTOP10……三菱UFJ銀行を擁する金融グループが第1位
時価総額は、「上場企業の株価×発行済株式数」で算出され、上場企業の市場規模を示すもっともわかりやすい指標である。
国内のメガバンクや信託銀行、規模の大きな地方銀行は、銀行を中心とする金融グループを形成しており、銀行の持株会社が東京証券取引所に上場する形態をとりながら、グループ全体を束ねている。
したがって、金融グループ持株会社の100%子会社であるメガバンクや大規模地方銀行については、持株会社の時価総額で市場規模を確認する。
2021年6月2日終値を基準とする時価総額による、ランキング上位10行は以下のとおりである。
「時価総額」ランキングTOP10
| 順位 | 銀行名<コード> | 時価総額 | 株価 | 発行済株式数 (2021年3月末) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・ グループ<8306> |
8兆6,069億 1,300万円 |
633.7円 | 135億8,199万 5,120株 |
| 2 | 三井住友フィナンシャル グループ<8316> |
5兆5,263億 8,900万円 |
4,022.0円 | 13億7,404万 61株 |
| 3 | みずほフィナンシャル グループ<8411> |
4兆3,332億 3,000万円 |
1,706.5円 | 25億3,924万 9,894株 |
| 4 | ゆうちょ銀行<7182> | 4兆1,625億円 | 925円 | 45億株 |
| 5 | 三井住友トラスト・ ホールディングス<8309> |
1兆4,426億 2,000万円 |
3,844.0円 | 3億7,529万 1,440株 |
| 6 | りそなホールディングス<8308> | 1兆1,902億 900万円 |
473.8円 | 23億282万 9,191株 |
| 7 | 千葉銀行<8331> | 5,863億 6,000万円 |
719円 | 8億1,552万 1,087株 |
| 8 | 静岡銀行<8355> | 5,320億 4,500万円 |
894円 | 5億9,512万 9,069株 |
| 9 | コンコルディア・フィナンシャル・ グループ<7186> |
5,019億 9,100万円 |
415円 | 12億961万 6,065株 |
| 10 | SBI新生銀行<8303> | 4,429億 4,900万円 |
1,710円 | 2億5,903万 4,689株 |
時価総額ランキングでも、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行それぞれの持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャル・グループが第1位から第3位にランクインした。
上位10行には、第6位にりそなホールディングス(メガバンク3行以外、唯一の都市銀行、りそな銀行の持株会社)の名前も見られる。
第7位~第9位は、地方銀行の千葉銀行、静岡銀行、そして横浜銀行を擁するコンコルディア・フィナンシャル・グループがランクインしている。
第10位は、前身が日本長期信用銀行であるSBI新生銀行(金融庁による「その他」に区分される)がランクインした。
時価総額TOP10には、いずれも全国的に見て認知度の高い銀行、あるいは有名銀行を中核とする金融グループが名を連ねた。
◇スタートアップ円定期預金金利3か月もの1.2%、1年もの0.85%
>>「SBI新生銀行」の詳細を見る(公式サイトへ)
第1位,三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306>:国内最大の巨大金融グループ
三菱UFJフィナンシャル・グループ(通称MUFGグループ)は、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行を中心とする巨大金融グループである。それ以外の100%子会社には、三菱UFJ証券ホールディングス(三菱UFJモルガン・スタンレー証券の持株会社)や、決済サービスの三菱UFJニコスがある。
MUFGの中期経営計画は「金融とデジタルのチカラで未来を切り拓くNo.1ビジネスパートナー」。目標達成に向けて「企業変革」、「成長戦略」、「構造改革」を主要戦略として打ち出している。ROEの目標は7.5%、グループとして安定的に当期純利益1兆円の実現を目指している。
第2位,三井住友フィナンシャルグループ<8316>:歴史ある三井・住友系総合金融グループ
三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)は三井住友銀行を中心とした複合金融グループである。
傘下には、SMBC日興証券、三井住友ファイナンス&リース、三井住友カード、三井住友DSアセットマネジメントなどがあり、グループとして幅広く事業を展開している。
顧客や社会とともに発展する「グローバルソリューションプロバイダー」を目指すというビジョンを掲げて、金融事業を展開している。
第3位,みずほフィナンシャルグループ<8411>:デジタル化の徹底など、構造改革を推進
グループ全体として、デジタル化の徹底推進を筆頭に、「ビジネス」、「財務」、「経営基盤」の3つの構造改革に取り組んでおり、5ヵ年経営計画では「次世代金融への転換」を目指している。
今後は、キャッシュレス化の推進や、スマートフォンを起点とする新たな生活圏・経済圏へのアクセス拡大、イノベーション企業への成長支援など、「金融を巡る新たな価値」を創造しながら、顧客との新たなパートナーシップの構築を図る。
ランキング上位の銘柄に投資できるおすすめ証券会社はこちら
国内株式個人取引シェアNo.1

|
投資信託に強い

|
LINEアプリで小額投資

|
1000円から始められる

|
| 詳細こちら (公式サイトへ) |
詳細こちら (公式サイトへ) |
詳細こちら (公式サイトへ) |
詳細こちら (公式サイトへ) |
(公式サイトへ)
「預金口座数」ランキングTOP10……ネット銀行の人気の高さを口座数で比較
一般的な銀行の口座数は、多くの場合ホームページなどでは公表されていない。利用者一人が複数の銀行で口座を開設していることも多く、休眠口座も散見するため、口座数と銀行の人気度が相関するとは言い難いからだ。
ただし、新興のインターネット専用銀行の大半は、口座数をホームページで開示している。ここでは、2021年6月2日現在で、ホームページ上で預金口座数を確認できるネット銀行8行を対象に、口座数ランキングを作成した。
ネット銀行「預金口座数」ランキングTOP10
| 順位 | ネット銀行名 | 預金口座開設数 (2021年3月末) |
|---|---|---|
| 1 | 楽天銀行 |
1,052万1,000口座 |
| 2 | イオン銀行 | 733万口座 (2020年9月末) |
| 3 | PayPay銀行 (旧 ジャパンネット銀行) |
500万超口座 (2021年2月5日) |
| 4 | 住信SBIネット銀行 | 451万口座 |
| 5 | セブン銀行 | 236万4,000口座 |
| 6 | ソニー銀行 | 158万口座 |
| 7 | 大和ネクスト銀行 | 150万5,000口座 |
| 8 | SBJ銀行 | 39万8,000口座 |
口座数ランキング上位のネット銀行はいずれも、比較的規模の大きな顧客基盤をもつ企業グループに属している。口座連携などにより、グループ内の既存顧客を銀行の顧客として取り込むことで、業務の拡大を図っている。
◇取引ごとに貯まる楽天スーパーポイント!
>>「楽天銀行」の詳細を見る(公式サイトへ)
◇スマホだけで簡単に口座解説可能!
>>「PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)」の詳細を見る(公式サイトへ)
◇24時間365日、ATMの出金手数料が無料!
>>ソニー銀行の詳細を見る(公式サイトへ)
第1位,楽天銀行:楽天カードや楽天会員との連携で顧客層を広げる
楽天グループの一員である楽天銀行は、楽天会員であることによるメリットを最大限に活かしながら利便性を高めることができるため、楽天会員による口座開設も多い。
楽天会員として口座を開設する、あるいは楽天銀行の顧客が楽天会員になることで、楽天証券や楽天カードなどとの連携が可能になり、より多くのポイントを貯められる。貯まったポイントを買い物や投資に利用することもできる。
楽天会員であることと銀行の顧客であることによる相乗効果を期待できる仕組みが大きなメリットになっている。
◇取引ごとに貯まる楽天スーパーポイント!
>>「楽天銀行」の詳細を見る(公式サイトへ)
第2位,イオン銀行:イオンショッピングセンター店舗内に銀行窓口を設置
イオン銀行は実店舗をもつ銀行でありながら、他行以上に、生活に密着した店舗あるいはATM展開を強みとする銀行である。
イオン銀行のキャッシュカードとクレジットカード機能を融合させたイオンカードセレクトには、イオン系列店でのショッピング特典が付与されており、イオングループの銀行ならではのメリットがある。
店舗はすべてイオンモールやイオンタウン内に設置されており、買物のついでに利用できる。無料で利用できるATMも全国に6,000台以上あり、土日祝日や年末年始でも利用できるのも特長となっている。
第3位,PayPay銀行:日本初のインターネット専業銀行、ジャパンネット銀行から改名
旧ジャパンネット銀行は、2000年に日本初のインターネット専業銀行として誕生した。近年はヤフー(Zホールディングス)や三井住友銀行との資本・業務提携を進め、口座振替やインターネットバンキングの無料化、他社とのAPI連携などを実現した。
2018年にはヤフーによる連結子会社化やPayPayとの決済提携を開始。2020年にPayPayと銀行代理業の業務提携契約を締結し、2021年4月5日にPayPay銀行に改名した。
ネット銀行の先駆者としての20年間の知見と、人気のキャッシュレス決済であるPayPayの利便性を融合し、入出金手数料無料を背景に、PayPayユーザーの取り込みも期待できる。
(公式サイトへ)
「経常収益」ランキングTOP10……一般企業の「売上高」に相当、三菱UFJが強い
一般企業が商品や製品を販売することで得た収益は「売上高」と呼ばれており、もっとも注目される勘定科目の一つに数えられる。
売上高は、証券取引所に提出する決算短信の経営成績や、財務局に提出する有価証券報告書の損益計算書で簡単に確認できる。
一方、銀行や証券会社の売上高に相当する勘定科目は「経常収益」であり、経費などを差し引く前の、業務上のサービス、例えば金融仲介業で得た収入がこれに該当する。
3大メガバンクのように、上場企業を持株会社に持つ銀行単体の営業収益は、それぞれの銀行が作成する有価証券報告書だけでなく、持株会社が作成する決算短信や決算報告資料などでも確認できる。
銀行の経常収益は、銀行の本業で得られる収益の大きさを他行と単純に比較できる便利な指標である。この経常収益に焦点をあてて、2021年3月期の実績でランキングTOP10を作成した。結果は以下のとおりである。
「経常収益」ランキングTOP10
| 順位 | 銀行名 | 経常収益 (2021年3月期) |
|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJ銀行 | 2兆6,354億円 |
| 2 | 三井住友銀行 | 2兆2,833億円 |
| 3 | みずほ銀行 | 2兆1,329億円 |
| 4 | ゆうちょ銀行(連) | 1兆9,467億円 |
| 5 | 三井住友信託銀行 | 8,455億円 |
| 6 | 三菱UFJ信託銀行 | 7,327億円 |
| 7 | りそな銀行 | 4,585億円 |
| 8 | 千葉銀行 | 2,329億円 |
| 9 | 横浜銀行 | 2,150億円 |
| 10 | 静岡銀行 | 1,801億円 |
国内の都市銀行4行や国内屈指の財閥系信託銀行、大手地方銀行が営業収益TOP10にランクインした。
銀行業務でもっとも利益をあげている国内TOP3の銀行を簡単に紹介する。
(公式サイトへ)
第1位,三菱UFJ銀行:堅実な経営体質と都市銀行最大の店舗網
三菱財閥系の都市銀行であるため、堅実な経営体質として認知されてきた。一方で、IT利用による業務効率化の加速、活発な国際業務や外為取引、積極的な海外M&Aや海外事業支援の評価も高い。
近年では、個人顧客のネットバンキング利用やAIの導入による非対面チャネルへのシフトが進み、窓口業務やコールセンター業務、与信業務などの縮小・効率化が進んでいる。
3大メガバンクの業務内容には著しい違いは見られないが、三菱UFJ銀行の特異性は圧倒的な事業規模にある。他のメガバンク2行の営業収益(売上高)とは一線を画しており、業界第1位の営業収益は、顧客からの三菱UFJ銀行への信頼の高さの証でもある。
三菱UFJ銀行は国内銀行最大の店舗網を有しており、国内には565支店、海外に110拠点(2020年3月末現在)のネットワークを誇る。
第2位,三井住友銀行:勤勉で意欲的な社員とチャレンジングな社風が特徴のメガバンク
三井住友銀行は、「勤勉で意欲的な社員が、思う存分にその能力を発揮できる職場を作る」という経営理念を掲げており、社員による企画提案から実現までのチャレンジがスピーディに行われる企業文化がある。
顧客に「より一層価値あるサービスを提供し、共に発展する」、ならびに「事業の発展を通じて、株主価値の永続的な増大を図る」ことも三井住友銀行の使命とされており、顧客からの満足度の高さも営業収益の高さの裏付けになっていると考えられる。
三井住友銀行は国内営業、とりわけ国内ホールセール事業に力を入れており、国内営業力の高さも業界第2位の営業収益を支えている。
三井住友銀行の国内本支店数は452カ所、海外支店は19カ所(2021年3月末現在)にのぼる。
第3位,みずほ銀行:銀行、信託、証券の一体戦略による店舗展開が特徴
みずほ銀行は、銀行単体ではなくOne MIZUHO戦略(銀行、信託、証券による一体戦略による高度なワンストップサービス)による業務展開が特徴である。メガバンクでは唯一、全国47都道府県での国内支店ネットワークを展開しているのも注目に値する。
国内の実店舗では、人生100年時代のライフデザインサポートや事業承継ニーズに応えるためのコンサルティング業務に力を入れている。デジタルチャネルを融合した次世代店舗の導入も進んでおり、国内営業力の強化につながっている。
みずほ銀行の国内ネットワークは464支店、海外は86拠点(2020年6月末)であり、数の上では三井住友銀行を上回る。
5,「業務粗利益」ランキングTOP10……決算説明資料で確認できる業務上のネット収益
銀行の「業務粗利益」とは、各銀行が独自に作成する決算説明資料などで用いられる、損益の状況を示す科目の一つである。
業務粗利益は、銀行法24条によって開示が義務づけられている銀行本来の業務による収支のこと。業務上発生する、「資金運用収支」、「役務取引等収支」、「特定取引収支」、「その他業務収支」の4つの収支を合計したネット利益である。
もともと業務粗利益は、国内の銀行の収益性や健全性を把握する目的で、金融庁が開示を義務づけた銀行の経営指標である。そのため、業務粗利益は、上述の経常収益以上に、銀行業務の収益力を直接的に測る指標だといえる。
2021年3月期の業務粗利益によるランキングTOP10は以下のとおりである。
「業務粗利益」ランキングTOP10
| 順位 | 銀行名 | 業務粗利益 (2021年3月期) |
|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJ銀行 | 1兆5,511億円 |
| 2 | 三井住友銀行 | 1兆4,817億円 |
| 3 | みずほ銀行 | 1兆3,478億円 |
| 4 | ゆうちょ銀行(連) | 1兆3,190億円 |
| 5 | 三井住友信託銀行 | 4,519億円 |
| 6 | りそな銀行 | 3,393億円 |
| 7 | 三菱UFJ信託銀行 | 3,316億円 |
| 8 | 横浜銀行 | 1,573億円 |
| 9 | 千葉銀行 | 1,560億円 |
| 10 | 静岡銀行 | 1,384億円 |
第1位から第3位までは、経常収益とまったく同じランキングになっており、開示様式が違っても、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行による銀行業務の収益力の高さは変わらないことがわかる。
参考までに、ここではランキング上位3行に代えて、第4位から第6位の銀行の概要について触れておきたい。
第4位,ゆうちょ銀行:邦銀最多の口座数と国内各地に張り巡らされた店舗ネットワーク
業務粗利益は、営業収益と同様に、日常的な銀行業務で得られる収益を表す。この業務粗利益において、ゆうちょ銀行は業界第4位の実績を上げている。
ゆうちょ銀行の銀行業務は国内のみに特化しているが、営業収益第4位を支えるのは、ゆうちょ銀行の国内随一の顧客基盤と店舗ネットワークである。通常貯金口座は約1億2,000万口座、全国各地に広がる店舗網は約2万4,000店舗にのぼり、3大メガバンクの国内店舗数をはるかに上回る規模となっている。
第5位,三井住友信託銀行:三井トラスト・ホールディングスの中核銀行
三井住友信託銀行は、三井トラスト・ホールディングスの中心的な銀行であり、国内最大級の信託銀行でもある。
近年では、相続や老後の資産管理に対するニーズが高まっており、過去20年間で遺言信託の契約件数は約6倍に拡大している。人生100年時代の到来とともに、老後のための管理系信託も増えている。
このような環境変化に合わせて、三井住友信託銀行では、過去5年間で「おひとりさま信託」、「セキュリティ型信託」、「医療支援寄付信託」といった時代に沿った新商品・サービスを開発し、信託銀行ならではの商品ラインアップで、安心・安全を提供している。
第6位,りそな銀行:都市銀行でありながら3大メガバンクとは異なる独自性をもつ
りそな銀行は、国内に4行ある都市銀行のうちの一つであるが、以下の点において、同じ都市銀行である3大メガバンクと大きな違いがある。
・首都圏と関西圏を中心とする地域に根差したリテール中心の営業基盤をもつ
・資産、事業承継、不動産仲介業務といった信託機能を銀行本体で取り扱う
・裾野の広い顧客基盤と広大な店舗ネットワークによるスケールメリットがある
リテールに特化しているため、貸出利回りの低い大口顧客が少なく、不良債権等のリスクも抑えられるため、高い利益率を維持できるのが特徴である。継続的な財務改革と堅実経営も奏功し、安定的な黒字決算を維持している。
(公式サイトへ)
「自己資本比率」ランキングTOP10……銀行の財務基盤の安全性を示す指標
銀行業務には、貸出金が戻ってこない信用リスクや、市場取引によるマーケットリスク、システム障害や自然災害などによるオペレーショナルリスクなどで、大幅な損失を被るリスクがともなう。
想定されるリスクが生じても、顧客の資金を守り、銀行業務を安定的に遂行するために、銀行は自己資本を強化して、強固な財務基盤を維持することが求められる。
こうした自己資本強化によるリスク管理を徹底する目的で、グローバル展開する金融グループや銀行に対しては、自己資本比率規制のための国際的な統一基準(「バーゼルⅢ」あるいは「バーゼル規制」と呼ばれる)が適用される。
バーゼルⅢによる自己資本比率は「自己資本÷リスクアセット×100」で算出される。
自己資本(分子)として定義されるのは、損失吸収力の度合いに応じて分類される3種類(「普通株式等Tier1」、優先株等の「その他Tier1」、劣後債や劣後ローン等の「Tier2」)に限られる。
分母に用いられるリスクアセットは、信用リスク、マーケットリスク、オペレーショナルリスクの3つのリスクを合計した金額として定義されている。
自己資本の組み合わせによって、自己資本比率の最低水準が以下のように定められている。
・普通株式等Tier1÷リスクアセット×100≧4.5%
・Tier1(普通株式等+優先株等)÷リスクアセット×100≧6%
・総自己資本(Tier1+Tier2)÷リスクアセット×100≧8%
なお、国内だけで銀行業務を行っている銀行には、バーゼル規制に準じた日本独自の自己資本比率規制が適用されている。
分子となる自己資本は、普通株式等(コア資本)から控除項目を差し引いた金額として定義されており、自己資本比率は、「(コア資本-控除項目)÷リスクアセット×100≧4%」に規定されている。
グローバル展開する銀行と、国内のみで業務を行う銀行の財務基盤の安全性は、単純に比較することができない。したがって、各行のホームページを参照して(2021年6月2日現在)、国際基準による自己資本比率と国内基準による自己資本比率を分けた上で、それぞれの自己資本比率ランキングTOP10を紹介する。
国際基準による「自己資本比率」ランキングTOP10
| 順位 | 銀行名 | 国際統一基準(バーゼルⅢ) 自己資本比率 |
||
|---|---|---|---|---|
| 総自己資本比率 | Tier1比率 | 普通株式等 Tier1比率 |
||
| 1 | みずほ信託銀行 | 28.64% | 28.63% | 28.63% |
| 2 | 三菱UFJ信託銀行 | 21.91% | 19.73% | 17.92% |
| 3 | 三井住友銀行 | 16.96% | 15.08% | 13.09% |
| 4 | みずほ銀行 | 16.96% | 14.28% | 11.14% |
| 5 | 三菱UFJ銀行 | 15.04% | 12.78% | 11.17% |
| 6 | 横浜銀行 | 14.02% | 12.68% | 12.67% |
| 7 | 三井住友信託銀行 | 13.35% | 11.10% | 9.69% |
| 8 | 静岡銀行 | 14.45% | 14.45% | 14.45% |
| 9 | 千葉銀行 | 12.09% | 11.57% | 11.57% |
国内基準による「自己資本比率」ランキングTOP10
| 順位 | 銀行名 | 国内基準 自己資本比率 |
|---|---|---|
| 1 | セブン銀行 | 54.59% |
| 2 | 大和ネクスト銀行 | 43.50% |
| 3 | ゆうちょ銀行(連) | 15.53% |
| 4 | 埼玉りそな銀行 | 14.45% |
| 5 | SBI新生銀行 |
13.26% |
| 6 | 常陽銀行 | 11.48% |
| 7 | 京都銀行 | 11.24% |
| 8 | あおぞら銀行 | 11.13% |
| 9 | りそな銀行 | 10.85% |
| 10 | SBJ銀行 | 10.51% |
バーゼル規制は、リスクテイクが重要視される国際業務に携わる銀行に対して適用される国際金融規制である。
そのため、バーゼル規制による自己資本比率と、決算短信などで開示される自己資本比率(企業会計原則にもとづいて、「自己資本÷総資産×100」で算出される)とは、分母・分子に該当する資産の定義が根本的に異なっているので、取り扱いには注意してほしい。
国際基準第1位,みずほ信託銀行:信託業務に特化することで、最強のリスク耐性に
みずほフィナンシャルグループでは、One MIZUHOにより、銀行、信託銀行、証券の住み分けを明確にしながら連携する体制をとっている。グループ傘下のみずほ信託銀行は銀行業務を行っておらず、信託業務に特化しているのが特徴である。
貸付業務を行っていないため、必然的に貸し倒れリスクの発生が抑えられるだけでなく、質の高い自己資本にもとづいた堅実経営が行われていることが、自己資本比率第1位の要因となっている。
国際基準第2位,三菱UFJ信託銀行:国際基準を大幅に上回る高い自己資本比率で、万が一に対応
三菱UFJ信託銀行のバーゼル規制による自己資本比率は、邦銀中第2位である。国際基準では8%が最低要件であることを鑑みると、三菱UFJ信託銀行の総自己資本比率21.91%は高い水準を達成している。
これは、普通株式や劣後債などの潤沢で良質な自己資本を確保することよって、損失吸収力の高い財務基盤が整備されていることを示している。
自己資本比率業界第2位の実績は、万が一、深刻な金融危機が発生した場合にも、安定的な金融システムを維持できることの裏付けになる。
国際基準第3位,三井住友銀行:堅実経営が高い自己資本比率に影響
三井住友銀行の社風は三井財閥由来の堅実経営であり、それが良質な自己資本の割合を高く押し上げているとも考えられる。
スピーディな意思決定と、先進的な取り組み、高い利益率が特長の三井住友銀行であるが、安定的な財務基盤による信頼性の高さも大きな魅力の一つである。
国内基準第1位,セブン銀行:ATM事業と決済口座事業が主体
インターネット専業銀行の中でも、セブン銀行の事業内容は特異であり、主な事業はATMプラットフォーム事業である。決済口座事業も行っているが、預金、ローンサービス、送金サービスといった身近な口座サービスが主体になっている。
ATM事業と決済口座事業以外の金融サービスは現状では行っていないことが、高い自己資本比率につながっている。
国内基準第2位,大和ネクスト銀行:大和証券利用者専用銀行で、リスクアセットも小さい
大和ネクスト銀行は、基本的に大和証券の口座開設者のための銀行であり、2021年6月現在では、大和証券に口座を持たない人は、大和ネクスト銀行に口座を開設することはできない。
大和ネクスト銀行のサービスであるフリーローンは事業性資金としての利用は認められていない。2021年6月現在では、フリーローンの新規申し込みも受け付けていない。現状では、大和ネクスト銀行は融資業務を行っておらず、一般的な銀行のような貸付金がほとんど発生しないことになる。
バーゼル規制に準じた自己資本比率を算出した場合、分母となるリスクアセット(中でも信用リスク)が小さくなる結果、自己資本比率が高くなっている。
国内基準第3位,ゆうちょ銀行:国際基準を上回る自己資本比率の維持が目標
ゆうちょ銀行の銀行業務の対象は国内市場だけであるため、バーゼル規制に準じた自己資本比率は本来、国内基準の4%以上であればよい。
それに対して、ゆうちょ銀行(連)の2021年3月期の自己資本比率の実績は15%を超えている。ゆうちょ銀行では、国際分散投資の拡大を前提に、国際基準による最低自己資本比率を視野に入れたリスク管理を行っており、これが、自己資本比率の高さの理由となっている。
(公式サイトへ)
「預金残高」ランキングTOP10……預金残高NO.1は国内最多店舗数のゆうちょ銀行
銀行の預金残高は、銀行業務の根幹をなす、顧客から預かる資金量を示す。預金残高は顧客への融資や資金運用の原資になるため、金額が大きいほど、規模の大きな銀行業務を行うことができる。
ここでは、持株会社が作成した決算短信に添付されている銀行単体の損益計算書、あるいは各銀行の決算短信を参照し、2021年3月末の各銀行の預金残高が多い銀行をランキング形式で紹介する。
預金残高ランキング上位銀行と、経常収益や業務粗利益などのランキング上位銀行を比較するなど、銀行評価の参考にしてほしい。
「預金残高」ランキングTOP10
| 順位 | 銀行名 | 預金残高 (2021年3月末) |
|---|---|---|
| 1 | ゆうちょ銀行 | 189兆5,000億円 |
| 2 | 三菱UFJ銀行 | 182兆2,399億円 |
| 3 | 三井住友銀行 | 134兆6,856億円 |
| 4 | みずほ銀行 | 128兆2,790億円 |
| 5 | 三井住友信託銀行 | 33兆1,742億円 |
| 6 | りそな銀行 | 32兆897億円 |
| 7 | 横浜銀行 | 16兆2,404億円 |
| 8 | 埼玉りそな銀行 | 15兆6,327億円 |
| 9 | 千葉銀行 | 14兆878億円 |
| 10 | 福岡銀行 | 12兆4,208億円 |
TOP10にランクインしている銀行の顔ぶれは、他のランキングと大きく変わっていない。ただし、第1位がゆうちょ銀行である点は、預金残高ランキング特有の現象である。
第1位,ゆうちょ銀行:邦銀最大の店舗数を背景にした預金残高第1位の実績
ゆうちょ銀行最大の特長は、都心部から地方まで、全国各地に張り巡らされた郵便局ネットワークを活かした国内最大級、約2万4,000にものぼる店舗数である。郵便局を利用するあらゆる地域住民が潜在的な顧客層であることから、邦銀の中では貯金口座数も桁違いである。
ゆうちょ銀行の預金残高第1位の実績の背景には、こうした郵便局由来の特性を活かした広範な顧客基盤がある。
第2位,三菱UFJ銀行:全国に広がるメガバンク最大の店舗網がメリット
三菱UFJ銀行は都市銀行であり、全国各地に店舗ネットワークを広げている。店舗数は国内565店舗、海外110店舗(2020年3月末現在)であり、ゆうちょ銀行を除くと、都市銀行、地方銀行など、一般銀行の中ではダントツの第1位である。
充実した店舗展開だけでなく、近年ニーズの高まっている顧客本位のコンサルティング体制の強化やデジタル化推進による預金額拡大も、預金残高第2位につながっている。
第3位,三井住友銀行:国内を重視した営業体制が預金残高第3位を支える
三井住友銀行は、個人向けコンサルティングを持続的な収益力の柱の一つとして位置付けている。
過去20年で国内支店数や従業員数は大幅に削減されている。その一方で、現存する国内452カ所(2021年3月末現在)の本支店に専門拠点を増設するなど、積極的に経営資源を投入することで、顧客のコンサルティングニーズに的確に対応している。こうした取り組みが、業界第3位の預金残高獲得につながっている。
「貸出金残高」ランキングTOP10……融資の多さでも圧倒的存在感の三菱UFJ銀行
銀行の収益を生み出す源泉は顧客への融資であり、貸出金が大きいほど、収益となる貸出金利息の拡大につながる。
各銀行の開示資料を参照し、2021年3月末の貸出金残高を基準に作成したランキング表は以下のとおりである。
「貸出金残高」ランキングTOP10
| 順位 | 銀行名 | 貸出金残高 (2021年3月末) |
|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJ銀行 | 88兆4,470億円 |
| 2 | みずほ銀行 | 82兆0,746億円 |
| 3 | 三井住友銀行 | 81兆9,377億円 |
| 4 | 三井住友信託銀行 | 30兆6,916億円 |
| 5 | りそな銀行 | 21兆1,711億円 |
| 6 | 横浜銀行 | 12兆1,328億円 |
| 7 | 福岡銀行 | 11兆2,823億円 |
| 8 | 千葉銀行 | 11兆1,663億円 |
| 9 | 静岡銀行 | 9兆3,272億円 |
| 10 | 埼玉りそな銀行 | 8兆1,693億円 |
上位3行は、これまでのランキングで何度もTOP3にランクインしていた三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行である。順位にはやや変動はあるが、銀行の規模と貸出金残高に相関があることは見てのとおりである。
ここでは、これまで紹介されてこなかった貸出金残高ランキング第6位の横浜銀行、第7位の福岡銀行、第8位の千葉銀行について簡単に紹介する。
第6位,横浜銀行:国内最大の地方銀行
横浜銀行は地方銀行に分類されるが、支店は神奈川県だけでなく、東京都、群馬県、愛知県(名古屋市)、大阪府にも設置されており、地方銀行ながら広範な営業網が特徴になっている。
横浜銀行では、地域金融の担い手としての役割が重要視されており、神奈川県内を中心に、地方公共団体が策定する「地方版総合戦略」の実行支援を積極的に行っている。
さらに、地域社会の創生に向けて、デジタル地域通貨の活用や、移住・定住促進に向けた取り組みも支援しており、横浜銀行のさまざまな地域支援策が、地域社会の発展につながっている。
貸出金残高全国第6位の実績は、広範な営業ネットワークに加えて、地域社会に密着した支援体制によって顧客の信頼を獲得していることの表れだろう。
第7位,福岡銀行:中小企業支援体制が魅力の地方銀行
福岡銀行の強みは、中小企業への適切な段階的支援体制が整っていることである。それによって、九州地方の経済活性化を後方から支援している。
事業または企業のスタートアップ期には、福岡銀行の事業カウンセラーがコンサルティングにより起業者を全面的にバックアップし、成長期の企業に対しては、M&A専門チームによるビジネスマッチングで事業拡大を支援する。
中小企業に対する積極的かつ効果的な融資の実施が、福岡銀行の高い貸付金残高実績につながっているだけでなく、銀行自体の持続的な成長と地域経済活性化ならびに地方創生にも寄与している。
第8位,千葉銀行:地方銀行トップクラスの規模を誇る地域のリーディングバンク
千葉銀行は千葉市に本店を置く地方銀行である。預金残高と貸出金はともに、地方銀行としては国内トップクラス、千葉県内ではメガバンクを抑えて第1位の実績がある。
地方銀行として、地域創生と地方経済の活性化に重点を置いているのが特徴。中でも、地域の中小企業の事業承継業務に力を入れており、2003年の業務開始以来、2018年までに170件の事業承継のためのM&A案件を手掛けてきた。
地方公共団体との連携による地方創生支援にも積極的に取り組んでいる。
例えば、千葉銀行とグループが一体となって公立小学校跡地の再開発を全面的に支援し、交流人事と雇用増加による地方創生に貢献した。この実績が高く評価され、2018年に内閣府特命担当大臣(地方創生担当)より表彰を受けた実績をもつ。
千葉銀行が目指すのは「リテール・ベストバンク」。地域社会の活性化に向けた中小企業への貸出金残高(融資)を順調に伸ばしながら、他行との連携や業務プロセスの抜本的見直しによる経営態勢の強化も実施し、銀行の持続的成長を目指している。
メガバンク3行の規模と収益力は桁違い、特性を活かした地方銀行などにも注目
信用格付、時価総額、営業収益(売上高)など、さまざまな指標で、国内の各種銀行をランキング形式で比較した。その結果、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3大メガバンクが、規模や収益力など、あらゆる面で、ランキング上位を占めていることが明白になった。
TOP10にランクインした銀行の中には、第4の都市銀行であるりそな銀行、ゆうちょ銀行、国内有数の財閥系信託銀行、埼玉りそな銀行や千葉銀行など、国内トップクラスの地方銀行の名前が挙がっている。
規模や収益力ではメガバンクには及ばないものの、りそな銀行やゆうちょ銀行、信託銀行、地方銀行には、独自の経営戦略や事業領域がある。それぞれの守備範囲で顧客第一主義を追求することが利益を生み、持続的な成長につながっていることを、改めて確認できたのではないだろうか。
ネット銀行で口座を開設するなら
◇24時間365日、ATMの出金手数料が無料!
>>ソニー銀行の詳細を見る(公式サイトへ)
◇取引ごとに貯まる楽天スーパーポイント!
>>楽天銀行の詳細を見る(公式サイトへ)
◇スマホだけで簡単に口座解説可能!
>>PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)の詳細を見る(公式サイトへ)
◇口座を複数持てる「つかいわけ口座」が便利。
>>GMOあおぞらネット銀行の詳細を見る(公式サイトへ)
◇給与振込で普通預金の金利が0.1%に!
>>東京スター銀行の詳細を見る(公式サイトへ)
◇スタートアップ円定期預金金利3か月もの1.2%、1年もの0.85%
>>SBI新生銀行の詳細を見る(公式サイトへ)
◇ローソン銀行ATMの手数料がお得!
>>ローソン銀行の詳細を見る(公式サイトへ)
◇普通預金金利が驚異の年0.20%!(税引前・変動金利)
>>あおぞら銀行BANKの詳細を見る(公式サイトへ)

【関連記事】
・住宅ローンのおすすめ金融機関をFPが厳選!変動金利、固定金利のおすすめは?選ぶときの注意点は?
・iDeCo(イデコ)を40代から始めるのは遅いのか
・人気ゴールドカードのおすすめ比較ランキングTOP10!
・プラチナカードの比較ランキングTOP10!還元率や年会費、アメックスやJCB、自分に合った1枚はどれ?
・ポイント還元率の高いクレジットカード11選