なんでも声に出して学ぶのはよくないのかもしれません。
スペインの認知・脳・言語に関するバスクセンター(BCBL)で行われた研究により、新しい単語を直ぐに声に出して読み上げることが、学習に悪影響になる可能性が示されました。
研究では、黙って聞くか聞いてから4秒待って声に出すほうが、学習を促進できることが明らかにされています。
新しい単語を声に出して学ぶ方法はこれまで勉強法の鉄板のように思われてきましたが、私たちの脳はそれほど単純なものではないようです。
研究内容の詳細は『Language, Cognition, and Neuroscience』にて掲載されています。
目次
- 新しい単語を学ぶとき「直ぐに声に出す」はよくないと判明!
新しい単語を学ぶとき「直ぐに声に出す」はよくないと判明!
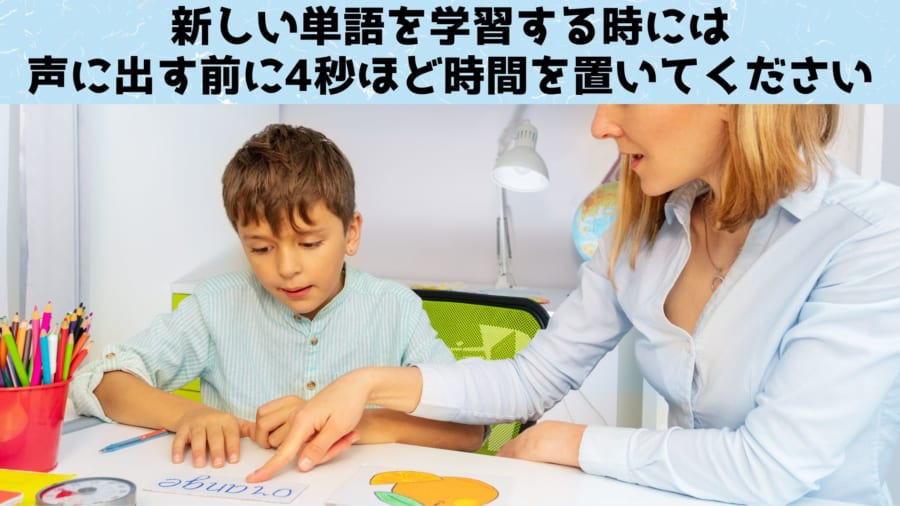
新しい外国語の単語を聞いたとき、声に出して繰り返すことが重要だとされています。
単語を声にするとき私たちの脳では単語のつづりを視覚で認識し、音を脳内で組み立て、言語として口から出力するという複合的なプロセスが働きます。
複数の脳機能を同時に動かすのは大変です。
しかしこれまでは、その大変さこそが新たな単語を脳に刻み込む「いい刺激になる」とされていました。
つまり「脳に多方面から負荷をかけたほうが学習効果が高くなる」という理論です。
しかし近年になって、必ずしもそうとは言い切れないことが明らかになってきました。
たとえば2022年に行われた研究では、新しい外国語の単語を直ぐに声に発することが、発音の学習にとって有害であることが示されています。
脳も筋肉と同じように、とにかく負荷をかければいいというものではなく、新しく聞いた単語を処理するためのインターバルが必要だからです。
そこで今回BCBLの研究者たちは「直ぐに声に出す」ことが知覚学習にどの程度の影響を与えるかを調べることにしました。









































