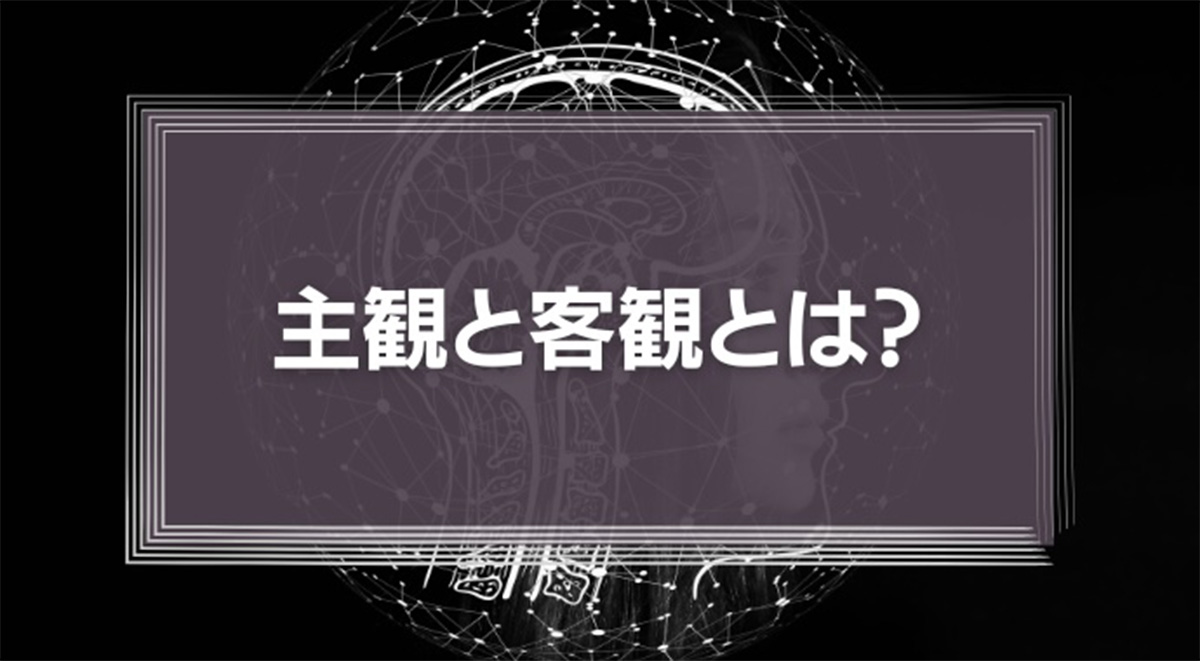
マネジメントにおいては、主観と客観の違いを正しく理解し、適切に使い分けることが求められます。
判断や評価が個人の主観に偏ることは、識学で言うところの「誤解」や「錯覚」を生み出す主要な原因です。
これにより、評価の属人化や不公平感が発生し、社員のパフォーマンス低下や組織運営そのものに深刻な悪影響を及ぼします。
こうした問題を防ぐ手段として有効なのが、数値による可視化です。
本記事では、主観と客観の基本的な違いを整理したうえで、数値化を通じて客観的なマネジメントを実現する方法を紹介します。
再現性と納得感のある判断基準を構築したい方におすすめの内容です。
主観と客観とは?
ビジネスにおける「主観」とは、個人の経験・感情・価値観に基づいた物事の見方を指します。
一方で「客観」は、第三者の視点やデータ、事実に基づいた判断を意味します。
マネジメントにおいて客観ではなく主観に偏ってしまうと、評価や意思決定が担当者ごとの感覚に左右されるため、同じ行動でも人によって評価が変わる属人化が発生します。
その結果、評価の一貫性が失われ、組織の公平性や再現性が損なわれるのも問題です。
特にリーダー層は、自らの思考が主観に偏る可能性があることを理解しなければなりません。
また、主観による判断を個人の“意識”に頼って是正するのではなく、組織として数値や明確な“定義”に基づいた客観的な判断軸(=評価ルール)を設け、それに従って判断する“仕組み”を構築・運用することが求められます。
識学式「守破離」ではまず数値化に取り組む識学式マネジメントでは、「守破離」の第一段階である「守」のステップにおいて、最初に徹底すべきこととして「数値化」が位置づけられています。
なぜなら、マネジメントは感覚や経験に頼るほど属人化し、再現性がなくなるからです。
上司と部下の間で認識のズレが生まれるのも、共通の判断基準がないことが原因です。










































