黒坂岳央です。
「貧乏が悪いのではない。貧乏思考が人をダメにする」
これは筆者が自身の人生経験から導き出した一つの結論である。自分は元々相当な貧乏人だったが、思考を変えたことで人生の流れが変わったという実感がある。親から受け継いだ能力や環境は固定値かもしれないが、思考は変動値であり、最も人生を大きく変えるレバレッジになる要素だと考えている。
そのため、仮に「貧乏思考」に囚われてしまうなら、たとえ一時的に経済的に余裕があっても長期的にはジリ貧になり、人生の満足度も低く留まりやすい。逆に言えば、思考習慣を変えられれば環境に制約があっても改善の余地はある。
本稿は注意喚起の意図を持って書かれたものであり、「貧乏を叩く」ためではなく、「貧乏思考を分析し、自分から切り離す」ことを目的としている。典型的なパターンを整理し、なぜ危険なのかを論じたい。
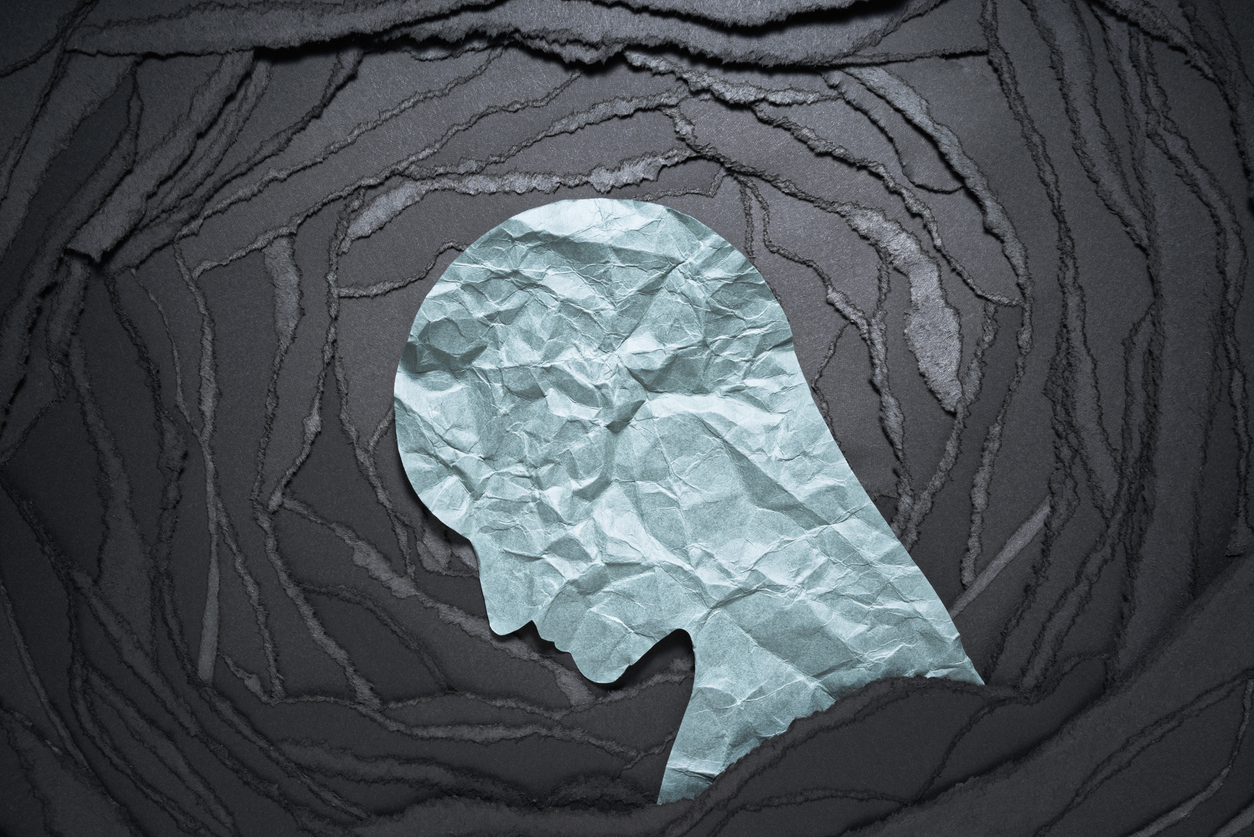
tadamichi/iStock
お金を使えない病
よく言われるのは「投資より消費を優先するとお金が貯まらない」という批判だが、実際にはある程度蓄財ができた人でも同じ罠に陥る。より解像度を高めると、その本質は「お金を使えない病」である。
「お金を使わない」は一見すると健全に見える。だが実態は「お金を使うこと自体が悪」「あらゆる出費が苦痛」という強迫観念に取り憑かれている。
このタイプはお金を使わないので貯蓄は進むが、大胆なリスクテイクができず、人生規模で見ると「小粒」で終わる。
人間関係への投資を惜しむため孤立しやすく、娯楽や経験を極端に避けるため年齢の割に精神的に幼くなる。
株式市場には手を出すが、自分のスキルや学びにお金を投じないため、幸福度が相場に連動してしまい、人生全体が不安定になる。
プライド最優先
もう一つの貧乏思考は「感情を最優先にする」パターンである。自分が論理的に得をすることより、その場の気分の良さやプライドを満たすことが常に優先される。









































