黒坂岳央です。
これまで日本のみならず、米国、欧州、中国といった主要国において、「高学歴」であることは非常に強力な武器であった。ひとたび良い学歴を獲得すれば、特に大企業においてはファーストトラックに乗ることができ、そうでない社員とは明確に異なるキャリアパスを歩むことができた。
だが今後、その「高学歴」の価値は大きく変容していくだろう。その最大のインパクト要因は、間違いなくAIである。一方で、代わって価値が高まるのが「リスキリング(学び直し)」だ。
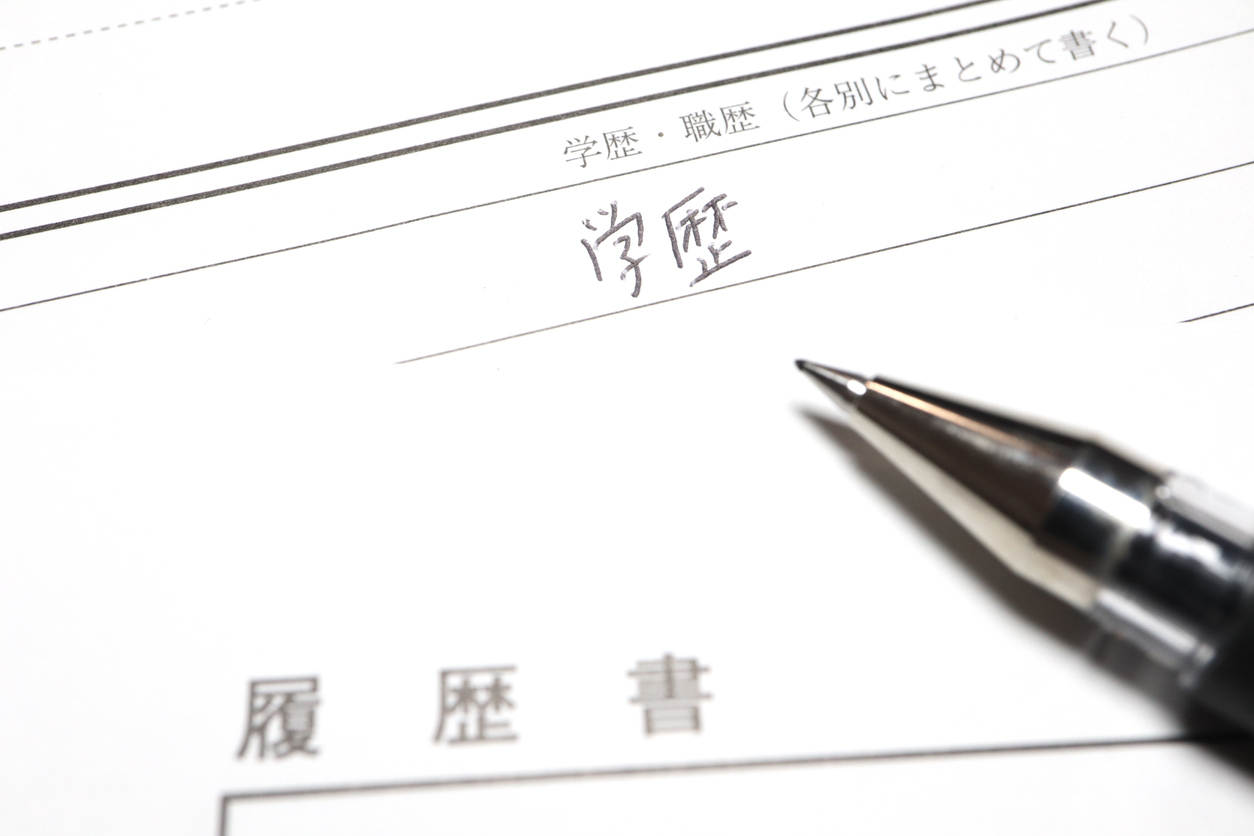
Yusuke Ide/iStock
学歴は「過去のスナップショット」に過ぎない
学歴とは本質的に、18歳あるいは22歳時点における知的水準や努力量、戦略的思考力といった「過去の学力の証明」にすぎない。確かに、難関大学を突破したという事実は、一定の環境・能力・意欲の証左ではある。だが、本当に重要なのは「過去」ではなく「現在地」であるはずだ。
筆者自身、現在独立して営んでいる仕事や日々必要とされるスキルの9割以上は、学校ではなく社会に出てから独学で身につけたものである。大学を“就職予備校”のように位置づける見方もあるが、若い時期にわずか4年学んだだけの知識で、40年のキャリアを戦えるような牧歌的かつ変化の緩やかな時代は、すでに終わっている。今後は少子化で従来と比べて大学に入る難易度が相対的に下がる事情も手伝い、高学歴の信頼度は低下する。
そして今、AIの登場によって知識の陳腐化スピードはかつてないほど早まっている。たとえば、議事録作成や文字起こしといった分野は、すでに生成AIによって産業そのものが消滅しかけている。
事務職に関しても、データ入力・スケジュール調整・帳票作成などの業務の多くが自動化の対象となっており、むしろホワイトカラーほど「安泰」ではない。労働人口の減少が続く我が国ですら、事務職だけは猛烈な人余りとなりつつあり、今後も市場規模は縮小していく。










































