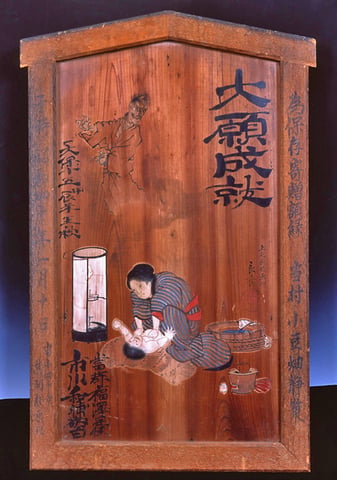現在先進国はどこも程度の差はあれ、少子化問題に苦しんでいます。
しかし少子化問題は何も全く新しい問題ではなく、江戸時代の日本でも起こっていました。
果たして江戸時代の人口が停滞した原因は何でしょうか?
本記事では江戸時代の人口動態について紹介しつつ、当時の人口が停滞した原因について取り上げていきます。
なおこの研究は、立法と調査260号に詳細が書かれています。
目次
- 開拓により人口が増加した江戸時代前期
- 飢饉だけではない、江戸の少子化の原因
- 江戸も東京も人口のブラックホールだった
開拓により人口が増加した江戸時代前期

江戸時代前期、日本の人口は急増しました。
江戸幕府が成立した1603年頃の日本の人口は1200万人程度であったのに対し、徳川綱吉が将軍として日本を統治していた1700年台初頭の人口は、3000万人まで増加していたのです。
その理由としては長かった戦乱の時代が終わって戦のない安定した時代に入ったことに加え、新田開発が積極的に行われたことも挙げられます。
江戸時代初期、幕府や藩は石高(コメの生産量)を少しでも増やそうとしており、それ故役人などが主導して湖や浅瀬を埋め立てて干拓したり、内陸部の荒れ地に灌漑の設備を作ったりすることがしばしばありました。
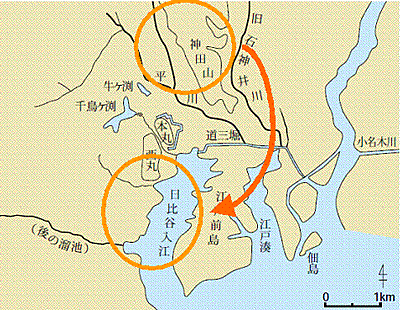
こうした1600年頃の関東の地形を見ると、現代と大きく異なること驚く人も多いでしょう。もともと江戸(現代の東京)では、海岸線が現代の皇居のあたりまで入り込んでおり、浅瀬や川で水浸しだったのです。
これを江戸時代初期に、現在の駿河台を切り崩して埋め立てるなどして整備することで利用可能な土地を大幅に増やしたのです。
それにより貧しい農民が開拓に参加することによって良質な田畑を手に入れることができ、彼らが世帯を持つことによって人口は急激に増加していったのです。
飢饉だけではない、江戸の少子化の原因