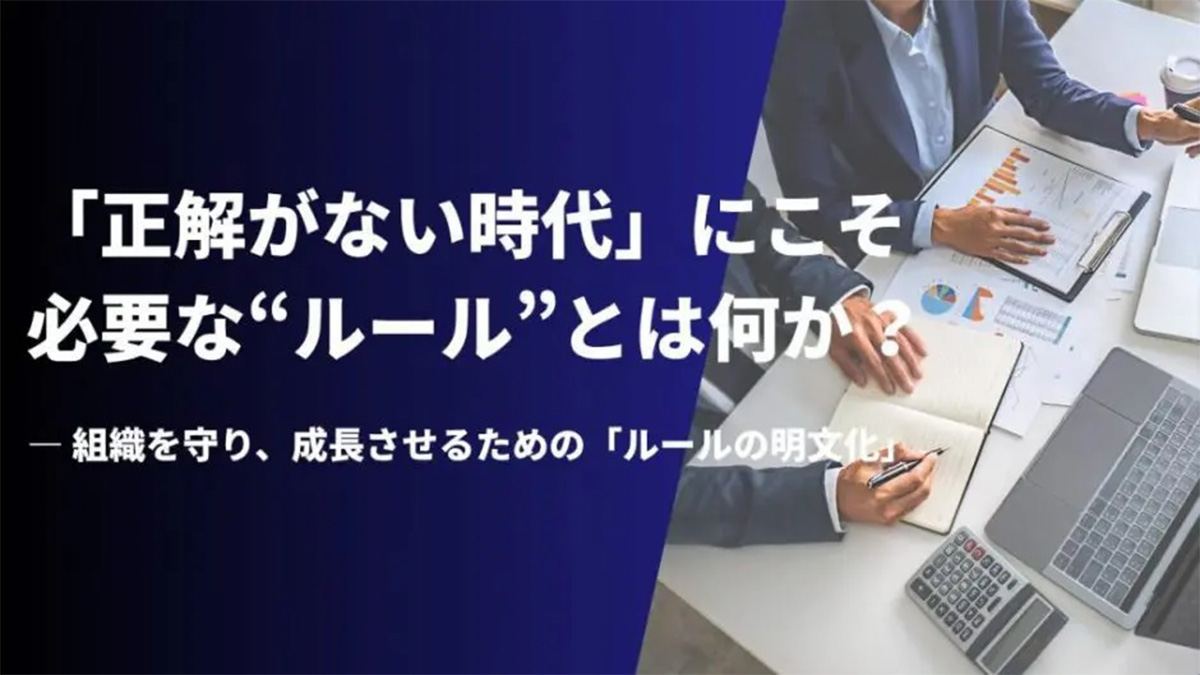
― 組織を守り、成長させるための「ルールの明文化」
現代は「正解のない時代」と呼ばれるほど、変化のスピードが速く、かつての成功体験や経験則が通用しなくなってきています。
このような環境下で組織を動かすために必要なものは、「柔軟性」ではなく、「共通の判断軸=ルール」です。本記事では、識学の理論をもとに、「なぜ今、ルールが必要なのか」「ルールがどう組織を変えるのか」について解説します。
1. 不確実な時代がもたらす「判断の分散」
テクノロジー、価値観、社会制度の変化が加速する現代では、「正解」が通用しない場面が増えています。昨日までの常識が今日には通じない。そんな状況で組織が陥りがちなのが、“各人が独自に判断して行動する”状態です。
この「判断の分散」は、一見すると自律性や柔軟性を重視しているように思えますが、実際には組織成果のバラつきや責任の不明瞭さを引き起こします。
上司ごとに指示内容が異なったり、部下が「どの行動が正解か」をその場の空気や雰囲気で測るようになったりすると、組織は次第に機能不全に陥っていきます。意思決定にかかるスピードも遅くなり、事後処理や感情でのマネジメントばかりが増えるのです。
このような状況下でこそ、組織には「判断の軸」が必要になります。それが、明文化された「ルール」です。
2.「ルール」の定義
ルールとは単なるマニュアルや規則とは異なります。
ルールの考え方として、以下の3要素を備えたものです。
明文化されていること
ルールは明文化され、誰でもそのルール内容を確認できる場所を認識できる状態でなければなりません。「暗黙の了解」や「なんとなくそうしている」は、ルールとして機能しないのです。
そのルールではすべてのメンバーが同じ動きになる事
特定の人だけに適用されるルールは「例外」を生み、不平等や感情的な摩擦の原因となります。ルールは「全員が守る」ものであり、だからこそ組織の統一性が保たれます。










































