例えば、学術講演や討論の場で「delve(掘り下げる)」「meticulous(綿密な)」「swift(迅速な)」「comprehend(理解する)」「boast(誇示する)」などの言葉が、それ以前の3年間と比べて約25〜50%も頻繁に使われるようになったと報告されています。
特に「深掘りする」や「掘り下げて考察する」という意味の“delve”という単語は、ChatGPTが文章を整える際によく付け加えるお気に入りの単語でした。
日本でも最近は「深掘りして解説する」という言葉を妙に聞くようになったという人もいるかもしれません。
研究者たちはこの“delve”などの会話での急増がAIから人への言語パターンの伝播を示す明確な証拠だと述べています。
重要なのは、こうした変化が台本のあるスピーチや番組内の決まり文句だけでなく、インタビューや対話といった即興の会話にも見られたことです。
「台本や決まり文句ならばAIが作成したものを読み上げてしまっただけなのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、生の人間の対話にまでAIっぽさの侵食が進んでいるという結果は、着目すべきでしょう。
一方、対照として調べた同義語ではこれほどの急増は確認されず、またChatGPT公開の1年前や2年前を「変化点」に置いた分析でも同様の増加は起こらなかったため、2022年末のChatGPT登場こそが語彙トレンドを変化させた決定的要因であると研究チームは結論づけています。
以上の結果は、ChatGPTのリリース後、人間の話し言葉における単語の頻度がAI生成文章の影響を受けて変化し始めていることを示しており、同時にAIシステムが人間文化そのものを変革しつつある可能性を示しています。
人間がAIを真似る時代
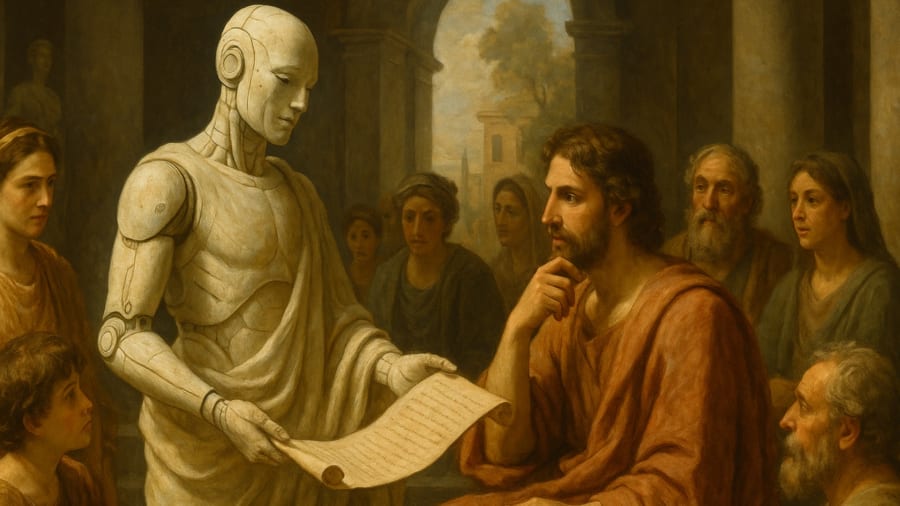
人間がAIの話し方を真似し始めた――この研究は、その明確な証拠を初めて示しました。






































