このような考え方は、「報酬予測誤差(reward prediction error, RPE)」という理論に基づいています。この理論では、「報酬を予想した量」と「実際に得られた報酬の量」の差がドーパミンの反応を引き起こすとされてきました。
予想より良ければドーパミンが出て、悪ければ出ない、あるいは減る。言い換えれば、ドーパミンは“得した”か“損した”かのシグナルのようなものだと考えられていたのです。
この理論は長い間、サルやネズミなどの動物実験によって支持されてきました。たとえば、レバーを押すとエサが出る装置を使い、報酬の出現確率を変えることで、ドーパミンの出方を観察するという研究が多く行われてきました。
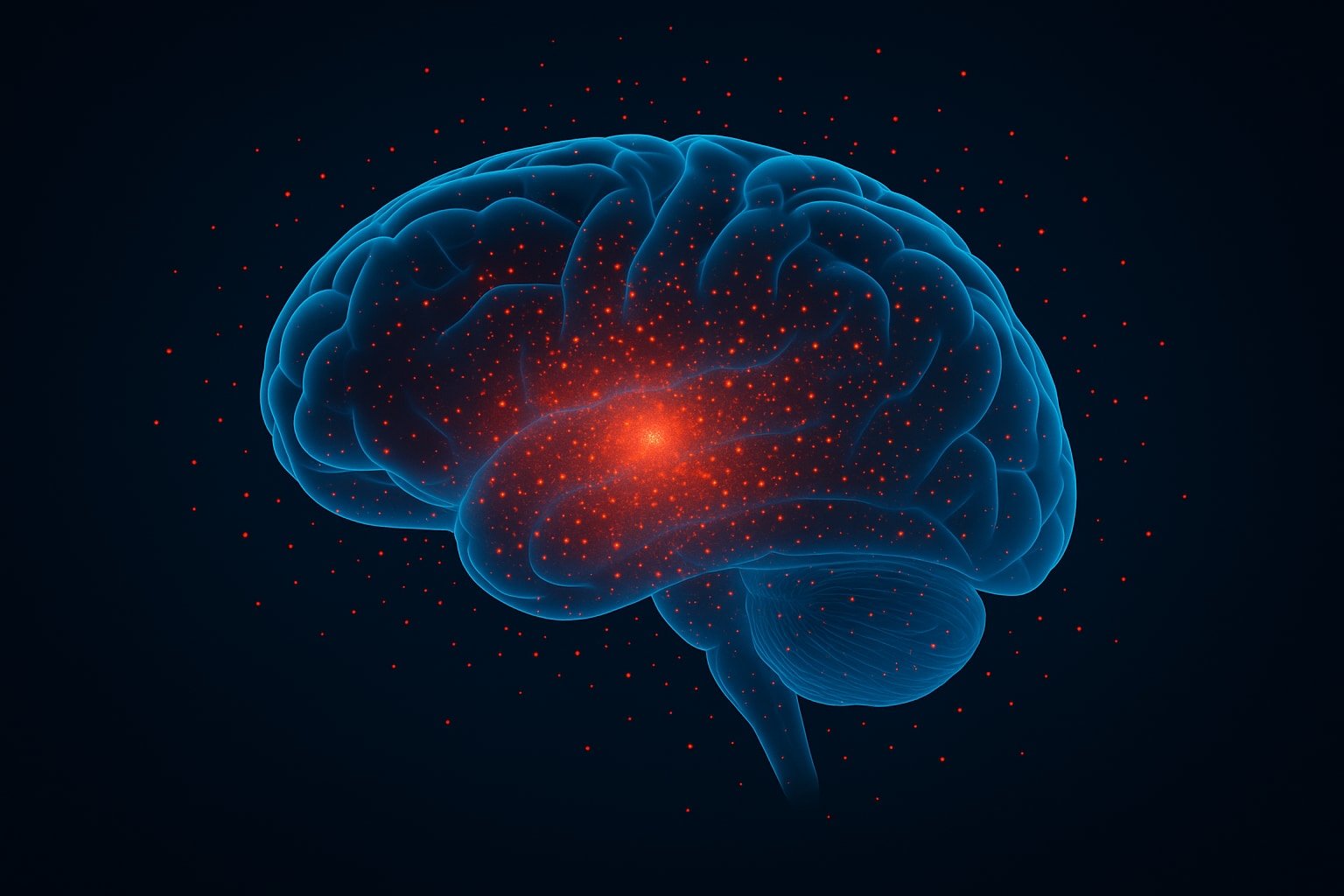
しかし、ひとつ大きな疑問が残っていました。それは「人間の脳でも本当に同じことが起こっているのか?」ということです。
ドーパミンは脳の奥深く、線条体(striatum)と呼ばれる領域などで働いています。この部分の活動をリアルタイムで観測するのは非常に難しく、動物ではできても、人間では直接的な証拠がなかなか得られなかったのです。
そんな中、アメリカ・コロラド大学医学部アンシュッツ校(University of Colorado School of Medicine, Anschutz Medical Campus)の研究チームは、ある方法を使ってこの壁を乗り越えました。
それは、脳深部刺激療法(Deep Brain Stimulation, DBS)という治療を受けている患者さんたちの協力です。この治療は、パーキンソン病や重度のうつ症状を軽減するため、電極を脳に埋め込み、電気刺激を与えるというもので、すでに多くの臨床で使われています。
研究チームは、この手術を受ける患者の同意を得て、実際に脳内のドーパミン濃度を非常に高い時間精度で計測できるセンサーを脳内に設置しました。こうすることで、人間の脳の中で、どのタイミングで、どの場所に、どれくらいのドーパミンが放出されているのかを、ミリ秒単位で観測することが可能になったのです。









































