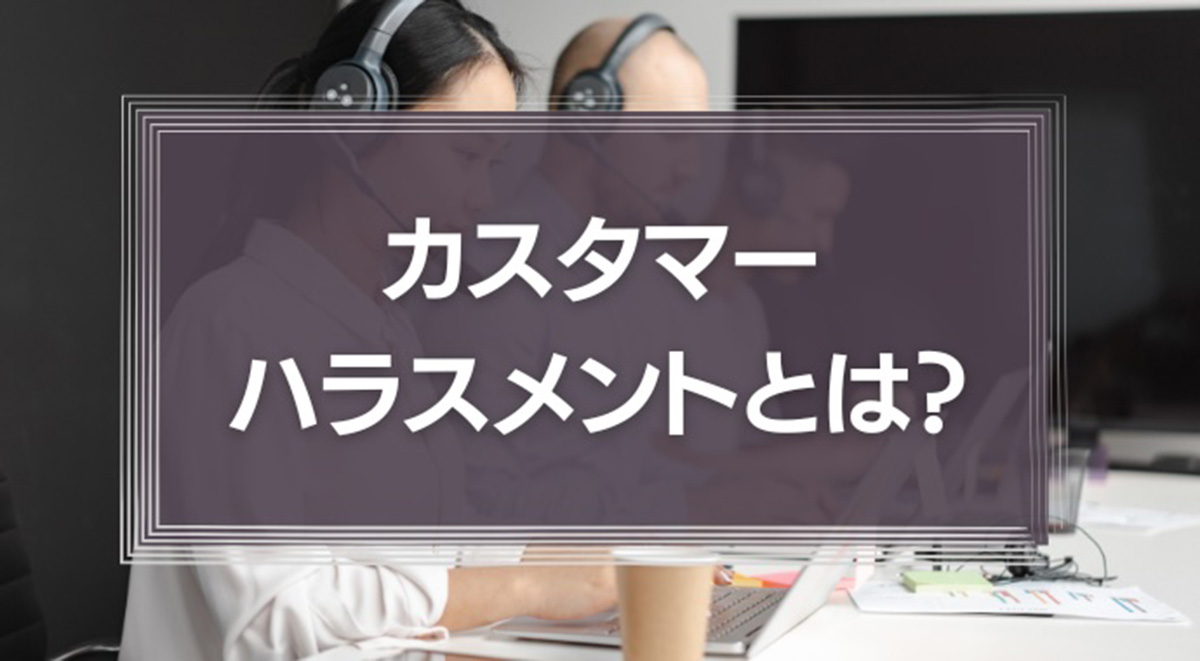
『カスタマーハラスメント』は、顧客がその立場を悪用し、企業や従業員に対して理不尽な要求や迷惑行為を行う問題です。
本記事では、具体的な被害事例を紹介しつつ、企業が知るべき法的対応のポイントと効果的な対策法を分かりやすく解説します。
カスタマーハラスメントとは顧客の立場を悪用した迷惑行為である
近年、顧客の理不尽な要求や暴言、長時間の拘束など、企業や従業員を苦しめる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が社会問題化しています。
顧客の立場を悪用したこうした迷惑行為は、企業に多大な影響を及ぼすため、正しい理解と対応が不可欠です。
本章では、カスタマーハラスメントの定義や背景、リスクを明確にします。
カスタマーハラスメントの定義カスタマーハラスメントとは、顧客が自らの「お客様」という立場を利用し、企業の従業員に対して過剰かつ不当な要求や迷惑行為を繰り返すことを指し、略して「カスハラ」とも呼ばれます。
厚生労働省は、カスハラを「業務上の対応の範囲を超え、労働者の心身の健康を害する行為」と定義。
具体例には暴言や脅迫、過度なクレーム、長時間の拘束、SNSでの誹謗中傷などが含まれます。
カスハラは従業員のストレスや離職の原因となり、労働環境の悪化につながるため、企業は正当な顧客対応と区別し、カスハラを認識すること、そして適切な対策をとることが重要です。
カスタマーハラスメント拡大の背景カスタマーハラスメントが近年増加した背景には、いくつかの社会的要因があります。
ひとつは、顧客至上主義の浸透です。
「お客様は神様」という考え方が根強く残り、企業側が過剰に顧客の要求に応じることが、逆に理不尽な行動を許す土壌となっています。
また、SNSの普及により、個人の不満が瞬時に拡散されるようになりました。
これにより、誹謗中傷や匿名での過激な要求が増え、企業の対応負荷が高まっています。
加えて、労働環境の変化や人手不足も、従業員の対応力を低下させ、カスハラの影響を深刻化させています。
混同されやすいクレームとの違い







































