
FatCamera/iStock
障害や病気の診断を受けた子どもの保護者は、深い悲しみと不安に直面することがあります。しかし、適切な支援と情報があれば、子どもの可能性を最大限に引き出すことができます。
今回は「難病の子のために親ができること」(大澤裕子著、青春出版社)を参考に、障害のある子どもの教育選択と家族支援について考えてみたいと思います。
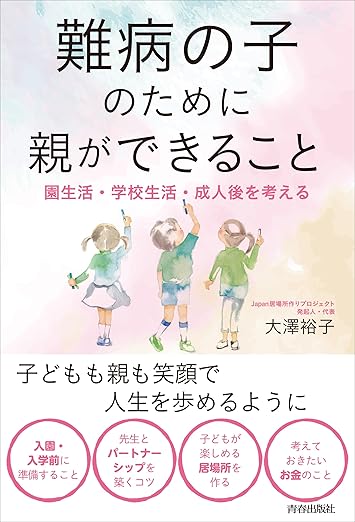
すべての子どもに教育を受ける権利がある
障害のある子どもの教育について考えるとき、その原点となる重要な理念があります。
1972年、米国のペンシルバニア州裁判所は「障害のいかんを問わず、すべての子どもはその能力に応じて教育を受ける権利を有する」(PARC判決)と宣言しました。これは、知的障害のある子どもたちが教育から排除されていた状況に対して下された画期的な判決でした。
この判決は世界中の障害児教育に大きな影響を与え、日本においても、すべての子どもが教育を受ける権利を持つという理念の確立につながりました。現在の日本の特別支援教育制度も、この「教育を受ける権利の保障」という考え方を基盤として発展してきたのです。
就学先選択のプロセス発達障害や知的障害など、教育的支援が必要な子どもの就学先選択は、保護者にとって重要な決断です。地域の学校の通常学級で学ぶか、特別支援学級に籍を置くか、あるいは特別支援学校を選ぶか。この選択は、単に教育の場を決めるだけでなく、子どもの将来の社会参加への第一歩となります。
大澤さんは著書の中で、就学先について相談したい場合は、市町村の教育センターで行っている「就学相談」に申し込むことを勧めています。
就学相談では、保育園や幼稚園の先生、療育機関の意見と、本人・保護者の希望を考慮して最終的に就学先を判断していきます。特別支援学級は知的障害学級と自閉症・情緒障害学級に分かれており、通級指導では通常学級で学びながら必要な支援を受けることができます。
選択における心理的な課題





































