100年以上解けなかった物理学の難問が、ついに数学の力で解けました。
アメリカのミシガン大学(U-M)で行われた研究によって、原子一粒の衝突から台風規模の渦までを貫く“一本の数学的な鎖”を初めて構築し、流体力学における3つの主要理論を統合することに成功したのです。
これまでの物理学では個々の粒子レベル、粒子の集団レベル、巨大な流体レベルを異なる数式で記述しており、まるで別々の法則のように扱われていました。
しかし今回の成果により3つの理論を連結させ、1900年から数学者たちを悩ませてきた「ヒルベルトの第六問題」の重要な部分を解決する大仕事となりました。
三つの理論を連結する“数学的鎖”は、どのように鍛え上げられたのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年03月3日に『arXiv』にて発表されました。
目次
- “ビリヤード球”と“連続体”を同じ教科書に載せる挑戦
- ヒルベルト第六問題ついに崩れる:粒子から台風まで“一本の数学的鎖”で貫通
- 理論の土台が固まると、空も海も計算しやすくなる
“ビリヤード球”と“連続体”を同じ教科書に載せる挑戦
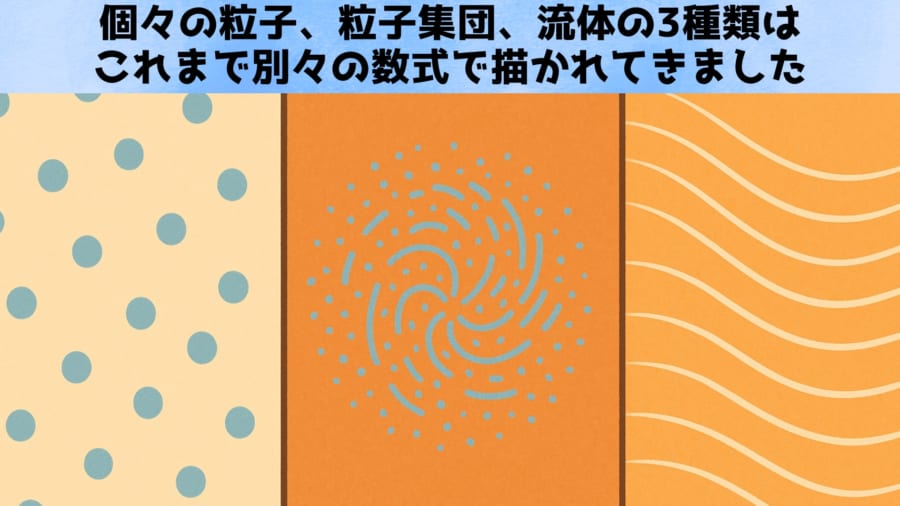
日常で目にする流体の動き(水の流れ、空気の渦など)は、実は無数の微小な粒子(分子)の集団運動です。
しかし、この現象を理解する方法には3つの視点(理論)が存在します。
1つ目はミクロ(微視的)な理論: 流体を構成する一粒一粒の分子に着目する視点です。
分子はまるで小さなビリヤード球のように動き回り、衝突します。
このレベルではニュートンの運動法則(古典力学)が適用され、各粒子の位置と速度を追跡することで振る舞いを説明できます。
しかし粒子の数は天文学的に多いため、全てを逐一計算するのは現実的ではありません。
2つ目は中間(メソスコピック)な理論: 巨大な粒子集団全体の振る舞いを統計的に捉える視点です。




































