研究チームはここに注目し、身長の測り方を三通りに整理しました。
第一に、同じ学年・同じ学校・同性の平均からどれだけ高いかを示す「学年内身長偏差(Zスコア)」。
第二に、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)の成長曲線に基づく「年齢別偏差」。
第三に、クラスでの背の順番を百分位ランクで表した指標です。
一方、学力テストの結果も標準化され、学年ごとの平均点をゼロ、標準偏差を1とすることで、学年間や科目間で比較しやすくしました。
もちろん、身長と成績の関係を見るだけでは十分ではありません。
ただ単純に比較しても、貧困率や家庭で英語を話す傾向など、背景要因が入り混じってしまい、もっとも影響を比較したい身長の影響が隠れてしまいます。
そのため研究者たちは、家庭の経済状況、家庭内言語、障がいの有無、誕生月(学年内での年齢差)など十数項目を統計モデルに投入し、それぞれの影響をできるだけ取り除きました。
さらに、同じ子どもを何年にもわたって追跡する「パネルデータ」の強みを生かし、子ども固有の「持って生まれた資質」、たとえば幼児期の栄養状態や家庭環境の違いを固定効果として差し引きました。
これにより、「その年に背が伸びた子は、成績も伸びたのか?」という視点から、より純粋な影響を見ることができたのです。
ではこの研究の結果はどうなったのでしょうか?
背が高いと成績も少し高い
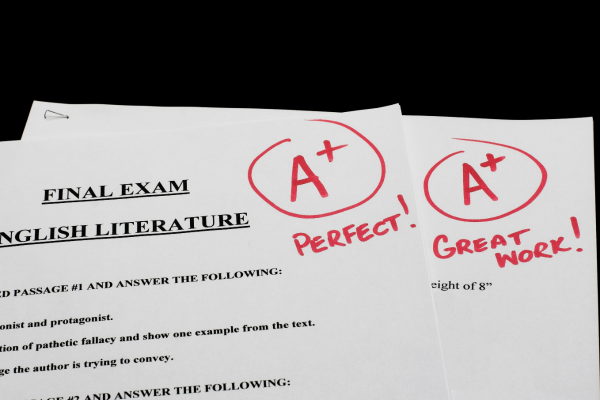
細かい調整をすべて加えたうえでも、背が高い子どもはわずかに高い学力テストのスコアを記録していました。
具体的には、学年内平均より約7センチ高い子ども(1標準偏差上)で、英語のスコアが平均して0.04〜0.06標準偏差、算数で0.03〜0.05標準偏差高かったのです。
標準偏差と言われてもわかりにくいですが、これはイメージするならクラス(30人規模)での順位が1〜2番ほど上がることに相当します。
また、最も背の高い2.5%と最も低い2.5%を比べると、英語ではおよそ0.2標準偏差、つまりクラス順位にして2~3番の違いが生じていました。





































