『誤解だらけの韓国史の真実 改訂新版』(清談社、5月4日発売)の刊行を機にした、日韓関係史の基礎知識の第3回である。
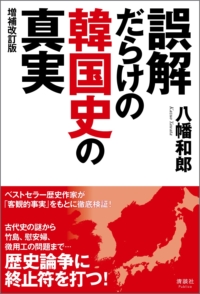
ヨーロッパでは経済社会の近代化は、ナポレオン戦争によるフランス軍占領のおかげでだいぶ進んだ。
しかしややこしいのは、結果として良い影響を及ぼしたことと、現地での評判にはまったく相関性がないことである。
ドイツでは、ハプスブルク家の神聖ローマ帝国を解消させ、中世からの多数の領邦国家による群雄割拠をまとまった州単位に近い形まで整理してビスマルクによる統一の基礎を作ったが、その功績は評価されていない。
イタリアではドイツ人による支配を形骸化させたので、評価は基本的に前向きである。
それは国内でも同じである。例えば、戊辰戦争で負けた東北の各藩では、上杉鷹山の米沢藩のような例外を除けば、ひどい悪政で餓死者が続出していたほどだったが、明治新政府になって民衆の生活は見違えるように改善された。
ところが、士族たちは仕事がなくなったので、「戊辰戦争で恨みがある」とか「明治になって差別された」とか言っては、「薩長けしからん」と主張する。とくに長州は恨まれているようだが、戊辰戦争で長州は越後で戦っており、東北戦の主役ではない。
しかも、江戸時代の武士たちの先祖は、ほとんど殿様についてよそから来た人たちであり、地元の人はほとんどいない。また、武士の子孫の多くは東京などに出て行き、地元にはあまり残っていないため、現在の地元民はだいたい農民の子孫である。ところが、それでも没落士族の怨みが地域で共有されている。
それはなぜか、私も考えたが、かつての負け組藩士が教師や言論人として地域に君臨し、彼ら自身が受けた不利益についての恨みを庶民にも共有させているのではないだろうか。何しろ教師と言論人は没落旧支配層にぴったりの職業であり、仕方のないことである。
韓国も同じで、日本統治により庶民の生活は良くなったが、両班などの特権は奪われた。その怨みを、日本統治の恩恵を享受したはずの国民が共有しているのは不合理だが、仕方のないことである。



































