進化の法則をのぞき込むと、数論が仕込まれていました。
英国のオックスフォード大学(UO)で2023年に行われた研究によると、私たち生物の進化は純粋な数学的な仕組みに基づいて繰り返されていたようです。
生物の進化のしやすさは耐性菌の出現などをみる限り強みにみえます。
しかし、変異速度が速すぎると優秀な能力を持った子孫が「繫栄する前に」次の変異が起きてしまい、生物は種として固定されず、異形の子孫が無限に生産される地獄絵図に陥ってしまいます。
そのためこの研究では最適な進化と種の保存を行うために必要な条件について数学的な分析が行われることになりました。
すると進化の背後には、雪の結晶や植物の枝葉、体の血管系など自然界の至る所に現れる「純粋な数学(数論)」が潜んでいることが判明しました。
研究内容の詳細は2023年7月26日に『Journal of The Royal Society Interface』にて公開されています。
目次
- 「数学」が進化の法則を制御していたと判明!
「数学」が進化の法則を制御していたと判明!
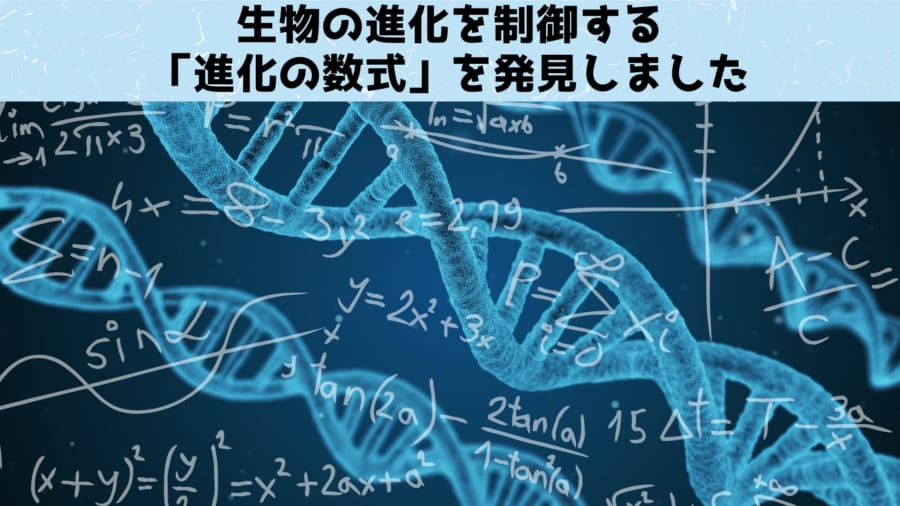
数論は純粋に数の性質のみを扱う分野であり、数学者以外には理解し難いストイックな分野とされています。
たとえば素数の出現パターンを解明するのも数論の分野となっています。
こうしたただの数の性質を論じているだけの分野でありながら、不思議なことに数論に関わる法則は、自然界のさまざまな場所に見ることが出来ます。
動物や植物の形態は実に多様で、そこには「堅苦しい」数学が入り込むスキがないように思えてきます。
しかし松ぼっくりのカサ、シダの葉、ヒマワリの種などの配列パターンを詳しく調べてみると、そこには数学をもとにした規則性が存在することが知られています。
特に有名なのは左右を「1」で囲まれたピラミッド型をした「フィボナッチ数列」や「フラクタル」と呼ばれる数学的概念であり、数論を構成します。













































