このように、平安の朝はただ単に夜明けとともに始まるのではなく、さまざまな鼓の音とともに、厳密に組織された儀式の中で「一日の始まり」が宣告されます。
いかにも幻想的でありながら、どこか機械的なまでに精緻なその様相は、現代の私たちが夢見た理想郷と現実の厳しさが、奇妙なまでに交錯する一篇の詩のようでもありました。
実質週休二日制だった平安貴族
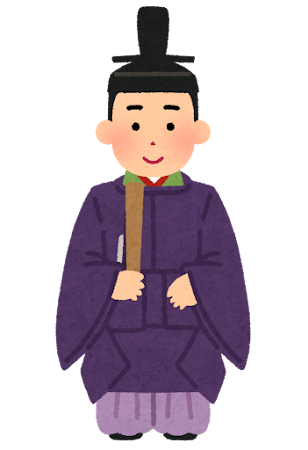
それでは平安貴族たちはどれくらい出勤していたのでしょうか。
『考課令』や『内外初位条』によると、上位の長上官は年間240日、番上官は140日以上の勤務が求められており、まるで月ごとのスコアを競うかのような日々が続いていたのです。
またそうでない平安貴族たちは休日として6日に1日のペースで休みをもらっていたということもあり、実際には25日が出勤日と計算されていました。
現在の週休二日制(週2日の休みが月に1回以上ある勤務形態)が取られている企業では大体月5日ほど休日がありますので、平安貴族の勤務形態はそれに近かったと言えます。
また位階が下がるにつれて、勤務日数は増えており、特に五位と六位の間には顕著な差が存在していました。
まるで、六位の官人たちは「皆勤賞」を狙うかの如く、欠かすことなく出勤し、夜勤も月に10日余りこなしていたといいます。
夜勤の件に関しては、『令集解』の「百官宿直条」によれば、最低でも4日に一度の交替勤務が規定されていました。
しかし実際にはその数字が微妙なばらつきを見せており、個々の勤め方には一種の風変わりな個性があったとのことです。
とはいえ、摂関体制の下で律令制度がいささか空洞化しているとの指摘があるにもかかわらず、貴族官人たちは形式上の規定にしっかりと従い、欠勤があれば帳面上で穴埋めするなど、規律という名の舞台で己の存在を輝かせていました。






































