コメは値上がりし続けるのか、と聞かれたら「当面はそう思う」と答えます。今の市場価格やテレビなどの報道を見て自分の家にコメの在庫を持っておきたい仮需に支えられているからです。平たく言えば国民みんなが「米投機」状態ということです。この行方は今年の秋の収穫が見えてくる頃にわかるでしょう。仮に不作であれば更に価格は高騰してしまいます。
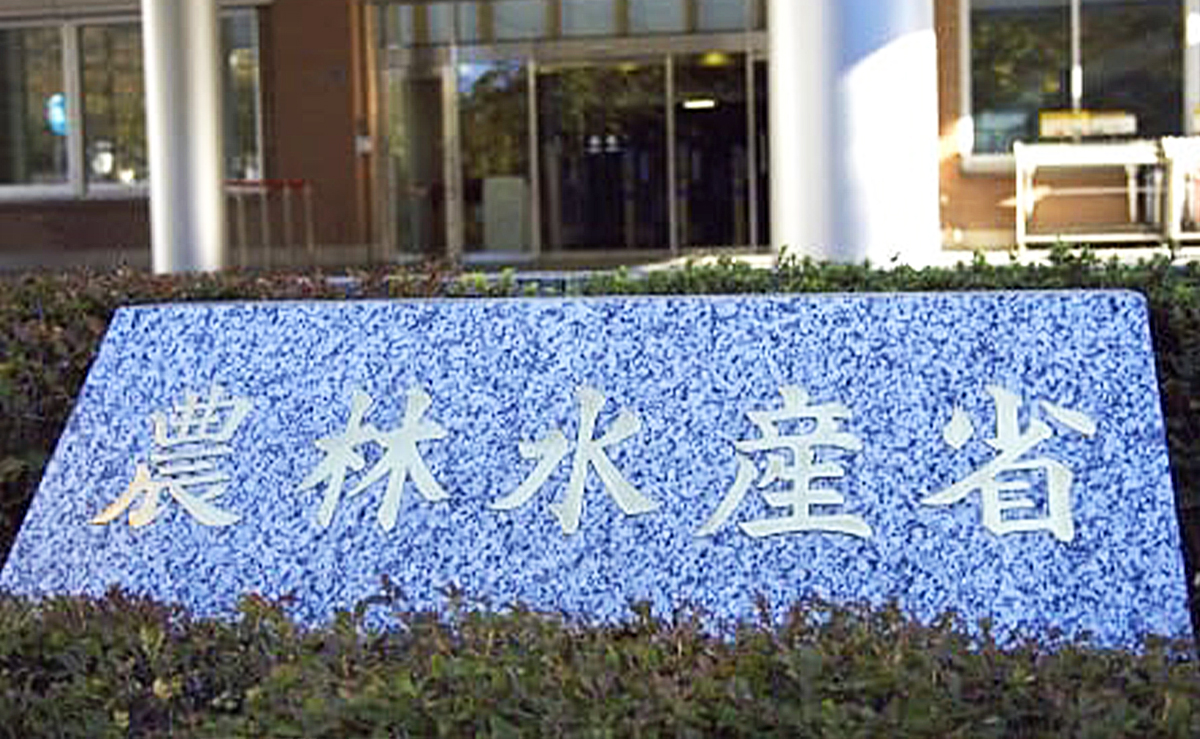
農林水産省
コメの価格問題は一種の社会問題と言ってもよいでしょう。日本の歴史の教科書でコメ不作で飢饉があった歴史をたどっているような気すらします。江戸時代にコメ作りが大きく進化し、米の主産地が東北地方にシフトしていきます。ところが時折起こる冷害でコメが取れない年が発生、これが大飢饉の原因です。故に日本のコメ作りは「寒さに強い」品種改良が主眼であり、今起きている「暑さに強い」という発想はないかと思います。
実際、ブランド米の多くは新潟、山形、宮城、秋田、更には北海道であって西日本産で著名なブランド米は兵庫や出雲など限られます。九州ではブランドの知名度アップのキャンペーンをしているぐらいです。ただ、東京の情報は東京をベースにしたもの故に東北、北海道のコメが目線に入りますが、西日本でも九州でも地元のコメを食べるのが基本だと理解しています。
我々が小さい頃は北海道で米が作れるというのは学校のテストでは不正解でコメ生産の北限は東北地方であったのです。コメの品種改良が進み、寒さに強いコメが北海道ブランドを育成したのですが、皮肉なことに日本全体が暑くなりこのままでは北海道がコメの主生産地になるのかもしれません。
仮に北海道でコメを主生産するならば思いっきり大規模機械化農業を取り入れ、ロボットにAI駆使での農業管理の最先端技術を導入し、生産コストを大幅に引き下げる努力をすれば日本のコメ市場も変わるのかもしれません。
もう一つのコメの生産と価格の問題は管理市場故であるということです。一番良い例えが電気です。電気は需要と供給が一致するように調整されています。余らせるわけにはいきません。ある意味極めて効率の良いビジネスなのですが、何かあればバランスを崩します。同様にコメ市場でも似たような発想を取り込んでいることがコトをややっこしくしているのではないかと思うのです。そして今までは不作の年でも曲がりなりに一定の価格の枠組みの中で収まったものの今回はそうは問屋が卸さなかった、ということだとみています。







































