しかし、すべてのデータを統合した解析では有意にリスク選好が高まる結果が示され、研究チームは「アセトアミノフェンを服用していると危険度を控えめに見積もる→もう少し続けても平気と感じる→風船が割れるリスクが増す」という連鎖を指摘しています。
この研究のどこか革新的だったのか?
第一に、世界で広く使われる鎮痛薬が脳や心の深い部分にある“怖さ”の感覚へ影響し、行動を左右している可能性を実験的に示した点です。
第二に、BARTなどのユニークな課題を使うことで、単なるアンケート結果の推測ではなく“実際にどれだけ危険な行動をとるか”を可視化できたことが大きな特徴です。
さらに、偽薬との比較を行う二重盲検という厳密な方法で、「アセトアミノフェンだと知っているから大胆になる」という思い込みの影響を排除した点も評価されます。
こうした複数の実験を総合し、「誰にでも身近な鎮痛薬が、私たちのリスク選好をわずかに増幅させるかもしれない」という疑問が浮かび上がりました。
研究者たちは「アセトアミノフェンを使うな、という話ではなく、こうした心理的影響があることを知ったうえで、意思決定に臨むことが大切」とコメントしています。
今回の結果は今後の議論をさらに活性化させる強い材料となるでしょう。
なぜアセトアミノフェンで恐怖が薄れる? 脳と薬の深い関係
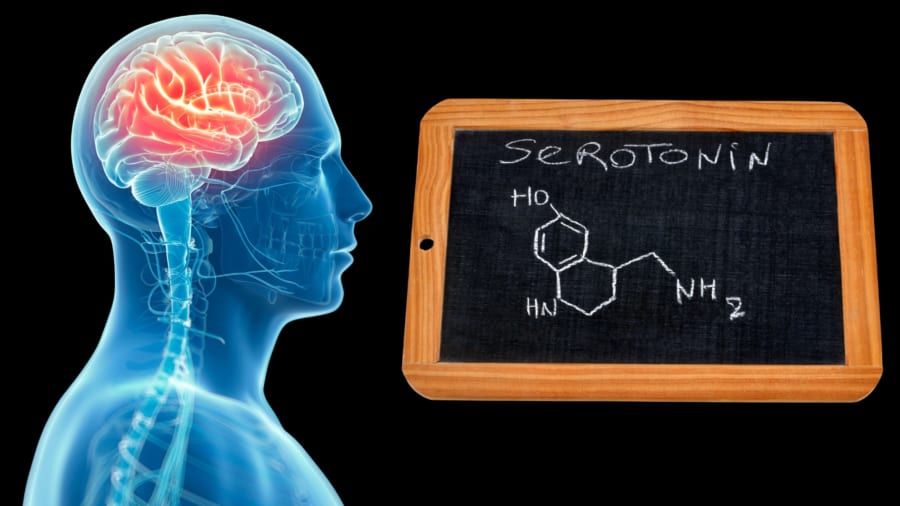
今回の研究でいちばん衝撃的なのは、「アセトアミノフェンが体の痛みだけでなく、“リスクを怖いと感じる感覚”までも和らげているかもしれない」という点です。
多くの人は頭痛や発熱を抑えれば、それで慎重さや警戒心まで変わってしまうとは想像しません。
しかし実験データからは、不安を抑える経路や、ミスを察知する脳の信号が弱まり、その結果リスクの大きい行動を選択しやすくなるケースがあることが見えてきました。







































