実は四十年ほど前にも、「暗黒物質がeVスケールの質量をもっていて、熱的に生成されたのではないか」という説が一部で唱えられてきました。
しかし、この程度に軽い粒子が本当に存在するかどうか確かめるには、高い感度と分解能をあわせ持つ分光観測が欠かせません。
そこでジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)やMUSEといった装置が活躍していますが、銀河中心部などは星やガス、背景放射が混ざりすぎていて“暗黒物質が出す光”だけを取り出すのは簡単ではないのです。
そこで新たに注目されているのが、暗黒物質の割合がとても高く、邪魔になる明るい天体がほとんどない「矮小銀河(dSph)」に目を向ける手法です。
なかでも超低光度のLeo VやTucana IIのような矮小銀河なら、もし暗黒物質が二次的な光を放っていればより見つけやすいと考えられます。
こうした背景から、「崩壊で生まれる微弱な光を高分散でピンポイントに探れば、暗黒物質の正体にグッと迫れるのではないか」というアイデアが生まれました。
そこで研究者たちは6.5mマゼラン望遠鏡に搭載された近赤外線高分散分光器WINEREDを使い、実際にLeo VやTucana IIの中心付近を狙って観測。
暗黒物質由来の線スペクトルが潜んでいないか、徹底的に調べることにしたのです。
暗黒物質の寿命は3.17京年以上ある
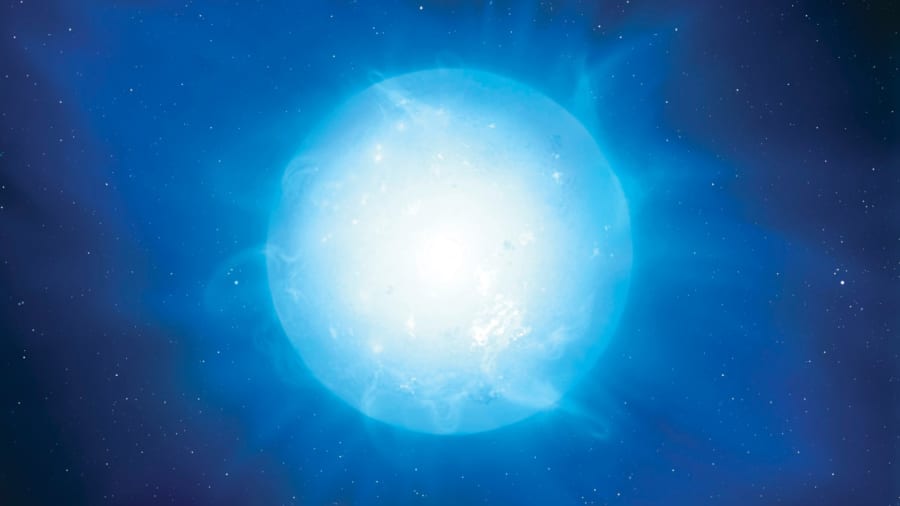
今回の観測に使われたのは、チリのラスカンパナス天文台にある6.5mマゼラン望遠鏡と、その先端技術を集めた近赤外線高分散分光器「WINERED」です。
普通のカメラで夜空を撮ると、星の光以外にも大気がわずかに光る“夜間大気光(ナイトグロー)”などが写り込んでしまいます。
これは暗黒物質が出すかもしれない微弱な光(シグナル)を見逃す大きな原因になるため、研究チームは「オブジェクト・スカイ・オブジェクト」という手法で観測対象(Leo VやTucana II)と背景の夜空を交互に同じ時間で撮影し、その差を取ることで雑音を徹底的に減らしました。






































