さらに、研究チームはこの相関を利用して、これらの物質がいつ供給されたかを調べたところ、太陽系最古の隕石が形作られる約90万年前(= 0.9百万年前)に爆発が起きたと推定され、しかもその爆発は太陽系の材料となった分子雲から見て100光年以内という近距離で起きた可能性が高いことがわかりました。
こうした結果を受けて浮かび上がってきたのが、「太陽系の元となる分子雲に、大質量星由来のアルミニウム26とチタン同位体が同時に混入し、外側ほど多く蓄積された」というストーリーです。
隕石はそのプロセスをありのままに封じ込めており、“母なる大質量星”の足跡を今に伝えてくれているのです。
ある意味で、大質量星の「最後の輝き」は太陽系にとっては「誕生の助走」でもあったわけです。
また技術的な面においても、今回の発見は重要です。
これまで隕石年代測定においてアルミニウム26が太陽系全体で均一だと想定することで算出してきましたが、それが外側に偏っていた場合、年代測定の結果が大きくズレてくるからです。
さらにアルミニウム26は、その崩壊熱によって微惑星や惑星胚(エンブリョ)の内部を温め、分化や核形成を促進する重要な熱源だったと考えられています。
今回明らかになった不均一分布や爆発時期を考慮すると、惑星の形成や進化がどのタイミングで進んだのかを、従来モデルからアップデートすることもできるでしょう。
超新星爆発の贈り物がなければ生命は誕生しなかったかもしれない
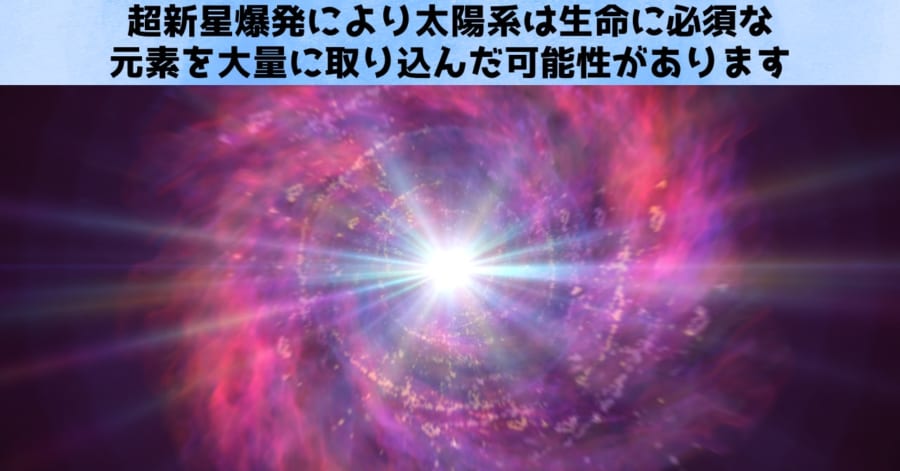
46億年前、私たちの太陽系は何もない静かな空間でひっそり生まれたわけではありませんでした。
近くにいた大質量星が起こした壮絶な超新星爆発によって撒き散らされた放射性アルミニウムやチタン同位体の痕跡を、隕石がしっかりと刻み込んでいたのです。
そこから見えてきたのは、私たち自身の“母なる星”が、その大質量星だったかもしれないという壮大なドラマでした。














































