『昭和東京ものがたり』単行本1990年 ライブラリー16巻、376頁 (強調は引用者)
もっとも、伊予のさつま飯は魚を「焼いた上で」ほぐして汁に仕立てるから、漁師めしでも調理に時間がかかる。なので、実はさつまの由来は薩摩でなく「佐妻」だとする説もあり、旅館もそちらの表記を採っていた。旦那ないし子供が事前に仕込み、後は白米にかけるだけの状態にして、忙しい妻(母)をサポートする飯、という趣旨だ。
もしそうなら本邦初(?)のフェミニストフードかもしれないが、私たちは稲作農業を「日本の伝統」だと思い込む癖がある分、異なる生業から育ってきた文化から、予想外に「新しい」暮らしの息吹を感じることも多い。
たとえば沖縄本島南部に糸満という漁業地があるが、昔から女性も行商に出て売り上げを「自分の財産」とする風習があったため、明治末~大正期には「男女同権で個人主義」の進んだ地域として採り上げる論説もあり、裏返って「糸満漁民は人種的にも欧米系」とする俗説まで流布していた史実は、だいぶ前に論文にまとめたことがある。
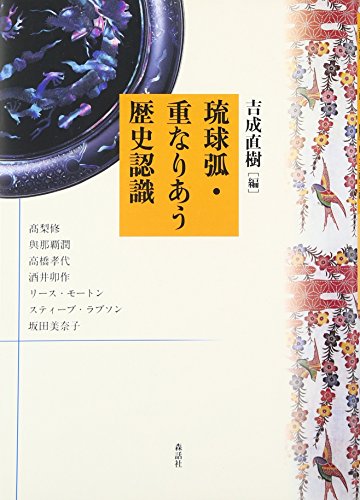
昭和の保守論壇誌のドンだった山本七平に、意外なほどマイノリティとしての繊細な感性が備わっていることには、キリスト教の信仰や戦場での過酷な体験など、いくつかの理由がある。しかし最も見落とされがちなのは、両親ともに和歌山(紀南)の捕鯨文化の中で育った漁民の出身で、本人も米食に思い入れがなかったことだろう。
私と妹はモチが嫌いで白米の御飯も嫌いだった。モチは今では全然食べないが、子供のころお正月には、お義理のように少しは食べる。ところが妹は頑としてモチを拒否し、みながお雑煮を食べている傍らで、一人でトーストを食べており、「妙な子だな」とか、「お嫁に行ったら困りますよ」とか言われていた。 妹は若くして世を去ったが、「御飯なし」は少しも苦にせず、「留学向きだね」などとも言われていたから、生きていれば今の私と変わらなかったであろう。私は一生「コメのメシ」抜きで一向に苦にならない。








































