
NiseriN/iStock
ミッシェル・フーコーはかの有名な「フーコーの振り子」のフーコーではない。左翼思想に毒されている人や学者、政治家の多くは、フーコー的善と悪の解釈の考古学(アルケオロジー)において、歴史上の社会情勢等の変化で善と悪の価値観が転換し得ることを説いた学問として有名であり、その影響を多大に受けていると考えられる。
フーコー的考古学的善悪の解釈論は何が善で何が悪か?の尺度について論じているのではなく、その価値観は時代の変化とともに変わるものだと言う意味だ。それは法治国家の法治とは何か?に通じる。
民意の具現としての選挙と立法が民主主義の依って立つ場所、依拠する場所であるとするならば、民主主義は法律で「のみ」定義つけられ価値観が法治によって固定された概念として息をし続けることになる。これは、民主主義とは社会契約論と相争うのか?と言う古典的論争のテーマでもある。
したがって、左翼思想に毒された人たちが陥る、マイノリティへの過剰な思い入れを背景とする権利主張は、フーコー的善悪論に立てば、アルシーヴ(社会背景上の資料収集・要素収集)を等価で判断材料とする上において、感情論に左右されることを否定されなければいけないことになり、やはり左翼思想による自己承認欲求と解釈しても言い過ぎでは無いように思う。
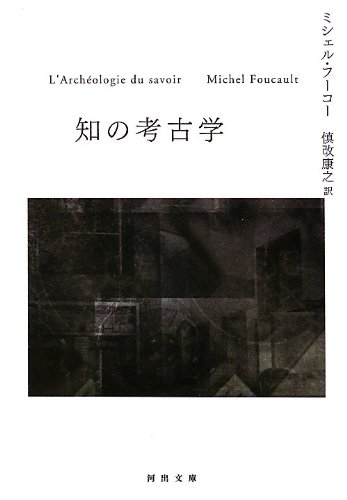
と当時に、フーコーは社会を構成する人に対して、ディシプリン(規律)をささやかなことであっても重要な要素と定義付けたが、これが後の、忌まわしき社会主義国家のパノプティコン(一望監視施設)による監視社会を生み出すことになる。つまり、この監視する側と監視される側が相互に監視している社会の具現だ。
社会主義とはこのようなフーコーの機械論的な人間の有り様に起因する。フーコーは人間を機械的な存在と見做したわけではなく、社会を秩序だった社会として成り立たせるには、この機械論的要素(種々のアルシーヴ)が必要だと考えた。
王政が倒れ、資本主義が席巻すると当時に、果たして社会はこのまま人間を自由なるものとして放置していていいのか?への問いに対するフーコーの答えが、ディシプリン(規律)による、機械論的な解釈としての人間と社会だったと言えるだろう。



































